2025年度 ポスター賞受賞の皆様
2025年度LS-BT合同研究発表会のポスター賞受賞者は、以下の4名の皆様です。 大変おめでとうございます。
受賞にあたり、研究を始めるきっかけやご苦労等をインタビューさせて頂きました。
P53 頭痛メカニズム解明に向けた神経細胞間隙の分子動態イメージング
Imaging dynamics of biological molecules in inter-cellular spaces of the brain
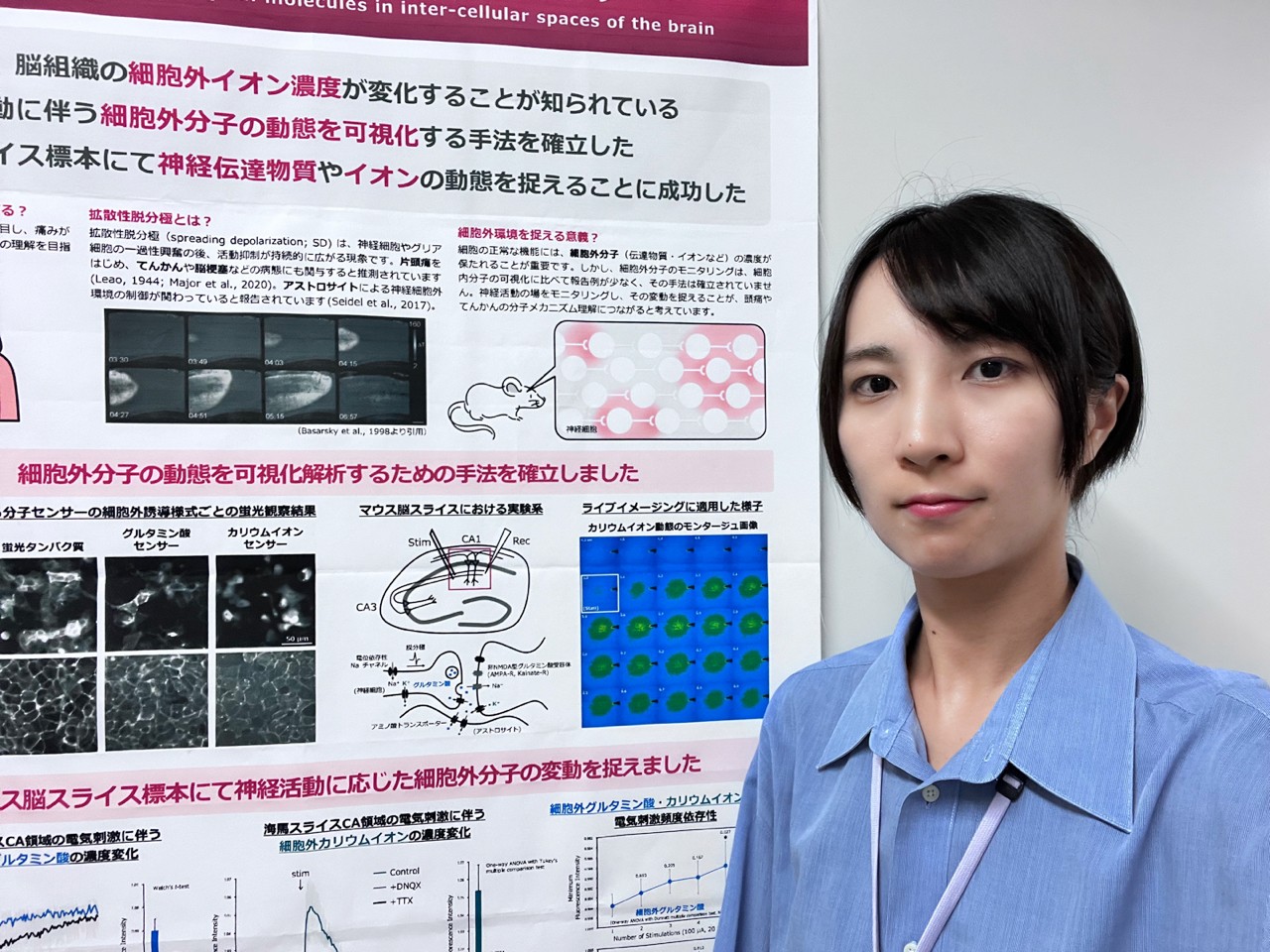
産総研 モレキュラーバイオシステム研究部門 三田 真理恵 研究員
片頭痛の痛みは日常生活に支障をきたすだけでなく、労働生産性の低下によって日本経済に毎年約2.3兆円もの損失をもたらすと試算されています。 日本における片頭痛の罹患者は約1000 万人にものぼり、私自身も片頭痛に悩まされるひとりです。 予防的治療と痛み止めによる対症療法をおこなうなかで、頭痛の根本となる現象は何なのかを明らかにし、新たな治療法や対処法に繋げたいと思うようになりました。 現在は大脳でおこる拡散性脱分極に着目した研究をおこなっています。 拡散性脱分極は、片頭痛をはじめ、てんかんや脳梗塞などの病態にも関与すると考えられており、神経細胞やグリア細胞が一過的に興奮し、そのあとに活動が抑制される状態が広がる現象です。 グリア細胞による細胞外環境の制御が、その発生や伝播に関わるとも報告されています。
これまで私は、バイオイメージング技術によって生体内分子の情報を可視化し、生体分子の機能解析を行ってきました。
生体で細胞や組織が正常に機能するためには、細胞間コミュニケーションの担い手である、細胞外に存在する分子(伝達物質やイオンなど)の局在や濃度が適切に保たれることが必要です。
しかし、細胞外分子のモニタリングは、細胞内分子の可視化に比べて報告例が少なく、その手法は確立されていませんでした。
そこで、脳内に存在するいくつかの分子に着目し、細胞外での動態を、ライブイメージングで捉える手法を確立しました。
神経活動に応じた細胞外分子濃度の変動を捉えることに成功し、神経細胞とグリア細胞がつくりだす神経活動の場を可視化することができました。
片頭痛の病態には、脳内で起こる拡延性脱分極だけでなく、脳血管や三叉神経の変化も関与するといわれています。
ヒトの臨床試験では痛みの情報が得られますが、細胞やモデル生物での実験ではその分子基盤を理解するための情報を得ることができます。
まずは拡延性脱分極を含めた片頭痛の分子メカニズムを捉えることを目指しますが、将来的には個体レベルで得られる情報との統合や、罹患者の遺伝的バックグラウンドなどとの関連を解析していきたいです。
イメージング(可視化技術)をテーマに研究していますが、日常生活でも「可視化」を大切にしています。
考えることが好きで、頭の中だけで考えを巡らせることも多いのですが、メモやイラストで可視化すると情報を整理しやすくなります。
なにが分かっていてなにが分かっていないのか、現状の課題はどこにあるのか、どの部分に対して自分が興味深く思ったのかなど、可視化しておくとのちに役立つことがあります。
また、物事を自分の言葉で他者に説明できるようになることも意識しています。自分の考えや得た知識を人に伝えられる形にできるかどうかで、自分の理解度を測っています。
今回はそのプレゼンテーションについて、賞という形で評価いただけたと思うので嬉しいです。
私がひとりでできる研究には限りがあると思っています。本発表も、共著者のみなさまのご協力のもとで得られた成果です。
信頼でき、尊敬できる方々に囲まれ、恵まれた環境にいると感じています。
共著のみなさまだけでなく、日々のディスカッションに応じてくださった生命工学領域のみなさまにも、この場を借りて感謝申し上げます。
(2025年6月現在)
