2025年度 ポスター賞受賞の皆様
2025年度LS-BT合同研究発表会のポスター賞受賞者は、以下の4名の皆様です。 大変おめでとうございます。
受賞にあたり、研究を始めるきっかけやご苦労等をインタビューさせて頂きました。
P19 細胞融合を促進するペプチド結合高分子材料の開発
Development of Peptide-Conjugated Polymers to Promote Cell Fusion
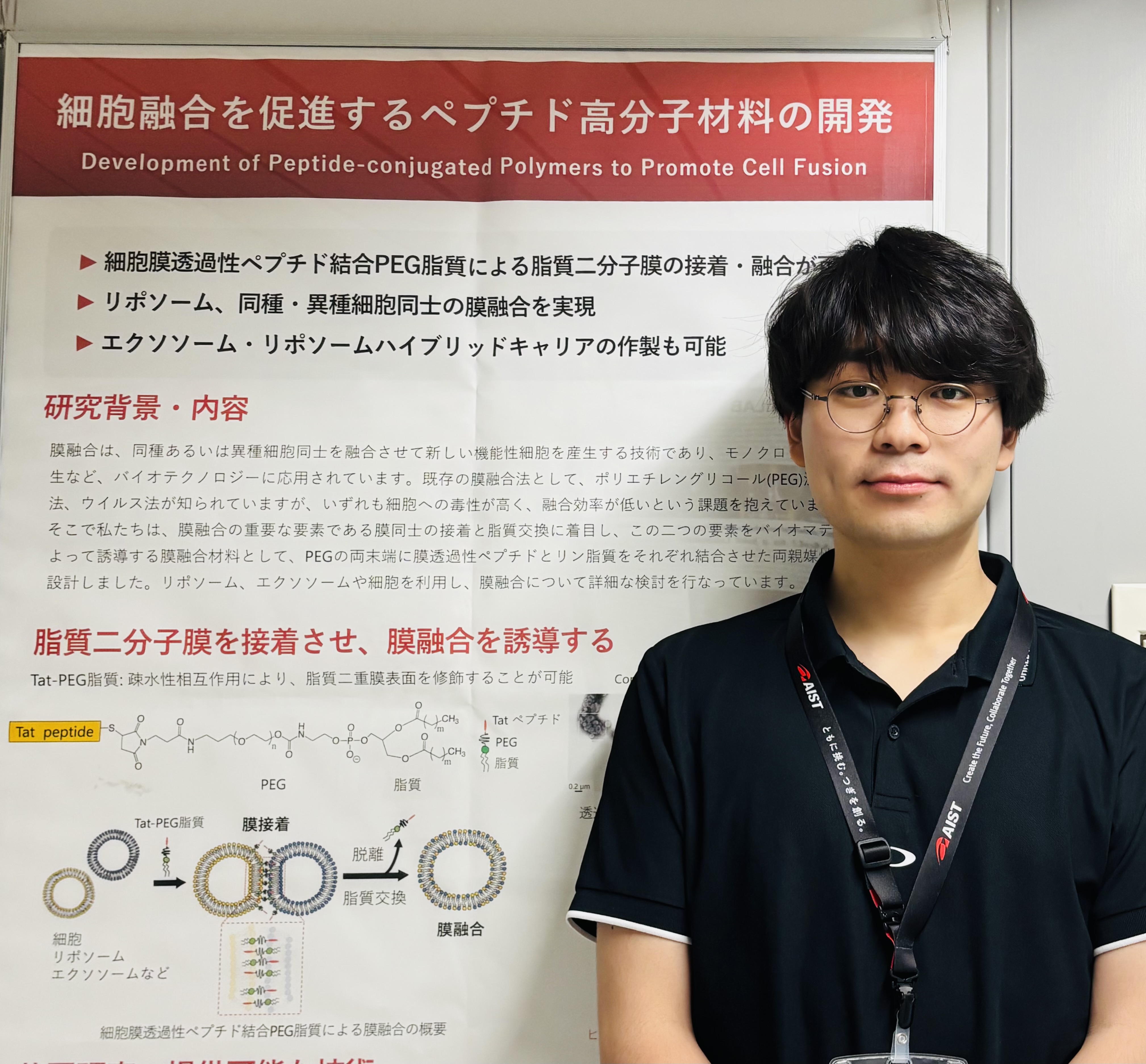
産総研 細胞分子工学研究部門 佐藤 佑哉 研究員
細胞やリポソームを基板に吸着・脱着させる高分子材料研究に取り組む中で、浮遊系細胞が基板に接着し、さらに細胞が伸展して形態を変化させるという、非常に興味深い現象がありました。
これは、接着性の乏しい細胞が、材料の存在によって形態まで変化するという、常識を覆すものでした。
この現象を、今度は「細胞対細胞」で起こしたらどうなるのかという素朴な好奇心から、細胞懸濁液中に高分子材料をそのまま添加してみたところ、思いがけず細胞融合現象が観察されました。
最初は、膜融合が本当に起こっているのか半信半疑で、信じたくても信じられない気持ちでした。
しかしその「本当なのか?」という疑問こそが、以降の研究を突き動かす強い原動力となりました。
この驚きと疑念が、現在まで研究を継続してきた大きなモチベーションになっていると感じています。
膜融合の仕組みをより明確に捉えるために、まずは構造がシンプルで再現性の高いモデル系であるリポソームを用いて検証を重ねました。
蛍光標識などの物理化学的手法を駆使し、融合の過程を多角的に観察することで、材料によって膜融合が確かに促進されることを確認しました。
さらに、細胞外小胞(extracellular vesicles, EVs)や実際の動物細胞を用いた実験にも展開し、単なるモデル系にとどまらない汎用性と応用可能性を評価しました。
異なる脂質組成、温度条件、分子設計を組み合わせながら、融合促進のメカニズムを掘り下げていきました。
今後は、本材料が従来法と比較して、より高効率に融合細胞(ハイブリドーマなど)を作製できるかどうかを実証していく予定です。
また、融合後の細胞の生存性や分化能への影響についても詳細に解析し、抗体生産や再生医療といった応用分野への展開可能性を探っていきたいと考えています。
さらに、材料合成プロセスの簡便化も重要な課題と捉えています。
将来的には、新たな機能性細胞種の創出やプロセスのスケールアップにも対応しつつ、他分野の研究者との連携を通じて、より実用的かつ広範な応用展開を目指していきたいと考えています。
研究において何よりも大切にしているのは、「好奇心を大事にし、思いついたことはまず試してみる姿勢」と「小さな現象を見逃さないこと」です。 今回の研究も、そうした直感的な仮説検証と偶然の観察から始まりました。リポソームやEVs、さらには細胞での膜融合が確認できたときは、何度経験しても感動的でした。 さらに、この現象は懸濁液中に材料を添加するだけというシンプルな操作で再現可能であり、自分以外の方が実際に再現してくださったときは、自分の研究が確かな技術となった手応えを感じ、とても嬉しく思いました。 一方で、大きな困難やつらさを感じることはあまりなく、それだけ研究を楽しめている証なのかもしれません。
本研究は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 細胞分子工学研究部門にて、技術研修生として取り組んできたものです。
受け入れ指導教員であり、現在の上司でもある寺村裕治 研究グループ長をはじめ、多くの先生方や共同研究者の皆さま、そして産総研の恵まれた研究環境の支えがあってこそ、このような研究成果を得ることができました。
改めて感謝申し上げます。
今後も、社会課題の解決に貢献できる技術の創出を目指し、バイオマテリアル研究の道を探究し続けてまいります。
(2025年6月現在)
