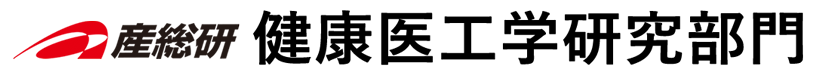バイオイメージング研究グループ
 多種多様なスケール・濃度で存在する生体分子や生体組織などの対象試料の高性能イメージングやセンシングを可能にする基盤技術を開発しています。
多種多様なスケール・濃度で存在する生体分子や生体組織などの対象試料の高性能イメージングやセンシングを可能にする基盤技術を開発しています。
研究紹介
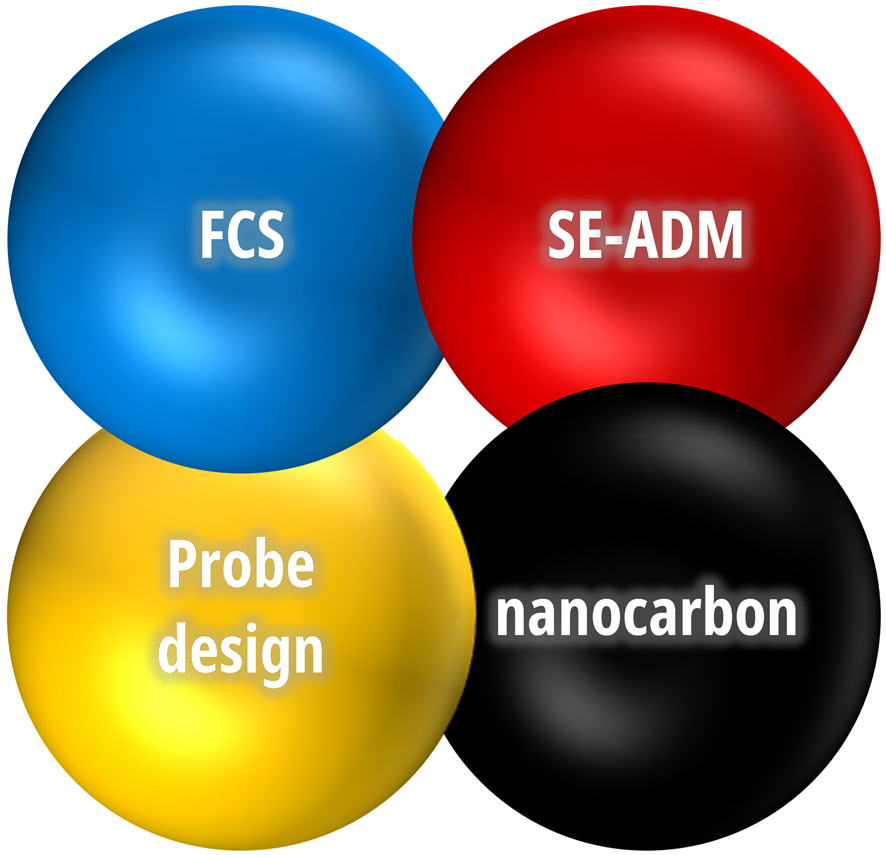
生体分子や生体組織、あるいは食品・環境物質などの対象物質は、それぞれ多種多様な スケール・濃度で存在しています。これら対象物質に対して、より高性能なイメージング やセンシングを達成するためには、新たな基盤技術開発が必要となります。当グループで は新たなイメージング・センシングプラットフォームの開拓に向け、以下の独自性の高い 観察・計測のための装置や材料、ならびに方法論に関する研究開発を進めています。さらに、 得られた成果の社会実装にも積極的に取り組んで行きます。
メンバーと主な担当課題
研究成果
氏名 役職
主な研究テーマ
機能性有機材料の開発と生体分子センシングへの応用
極微量物質センシングのためのナノカーボン電極材料の創製
走査電子誘電率顕微鏡とインピーダンス顕微鏡の開発
拡散計測による溶液中ナノ環境評価手法の確立
光ファイバー光学系による簡易分子拡散計測法の開発
<研究成果の凡例>
<お問い合わせ> Eメール:M-hmri-ic-ml@aist.go.jp