Sustainable Remediation コンソーシアム
Sustainable Remediationについて
Sustainable Remediationとは、土壌汚染対策において、 リスクやコストだけでなく、外部環境負荷(環境面)を低減しつつ、 社会面、経済面を含めた浄化の意思決定を推進する考え方であり、 技術ベース思考、リスクベース思考と進んできた土壌汚染対策において、 更に広範な概念として持続可能性(環境・社会・経済)を取り込んでいく、 という考え方です。
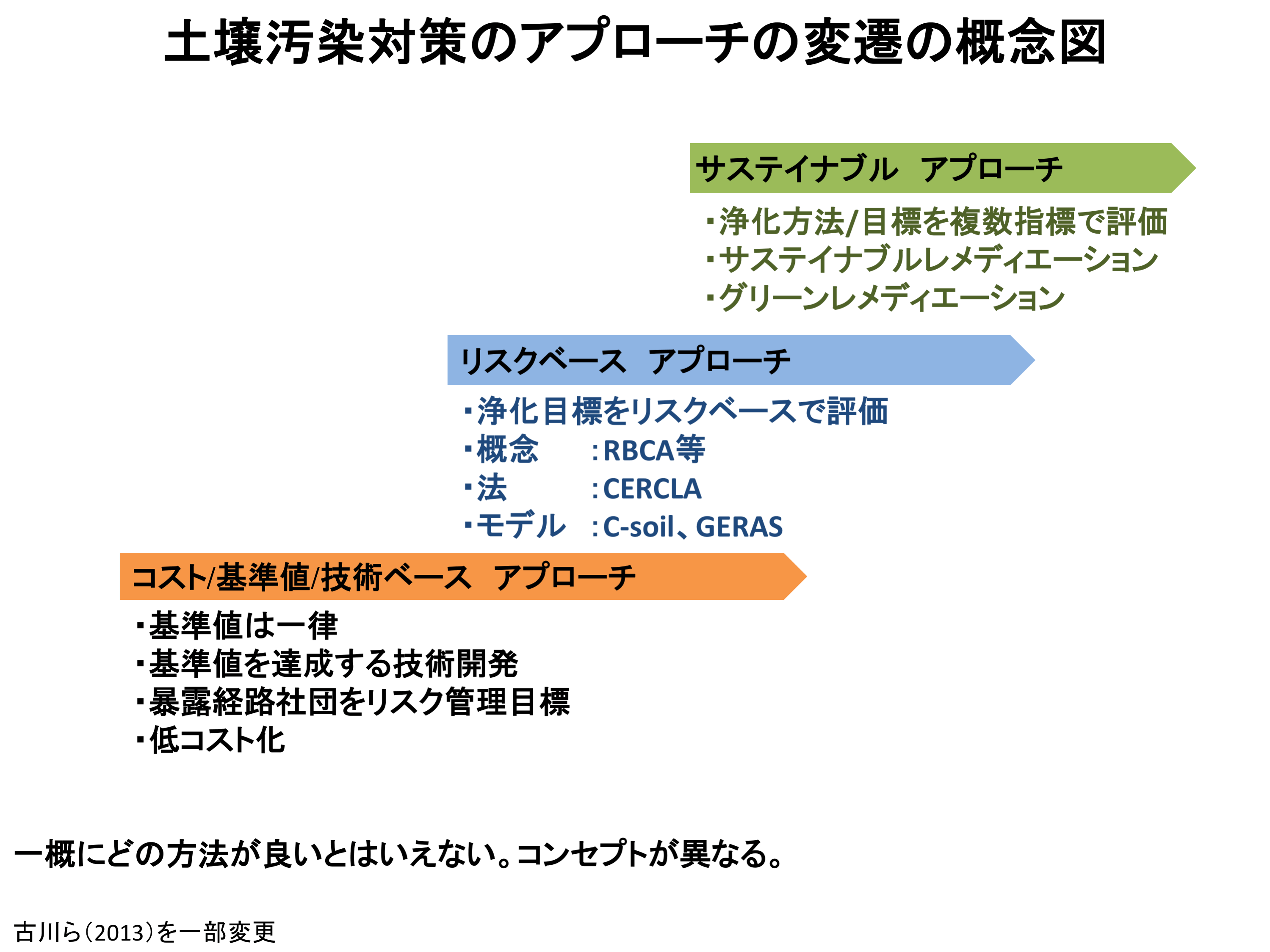
土壌汚染対策のアプローチの変遷の概念図
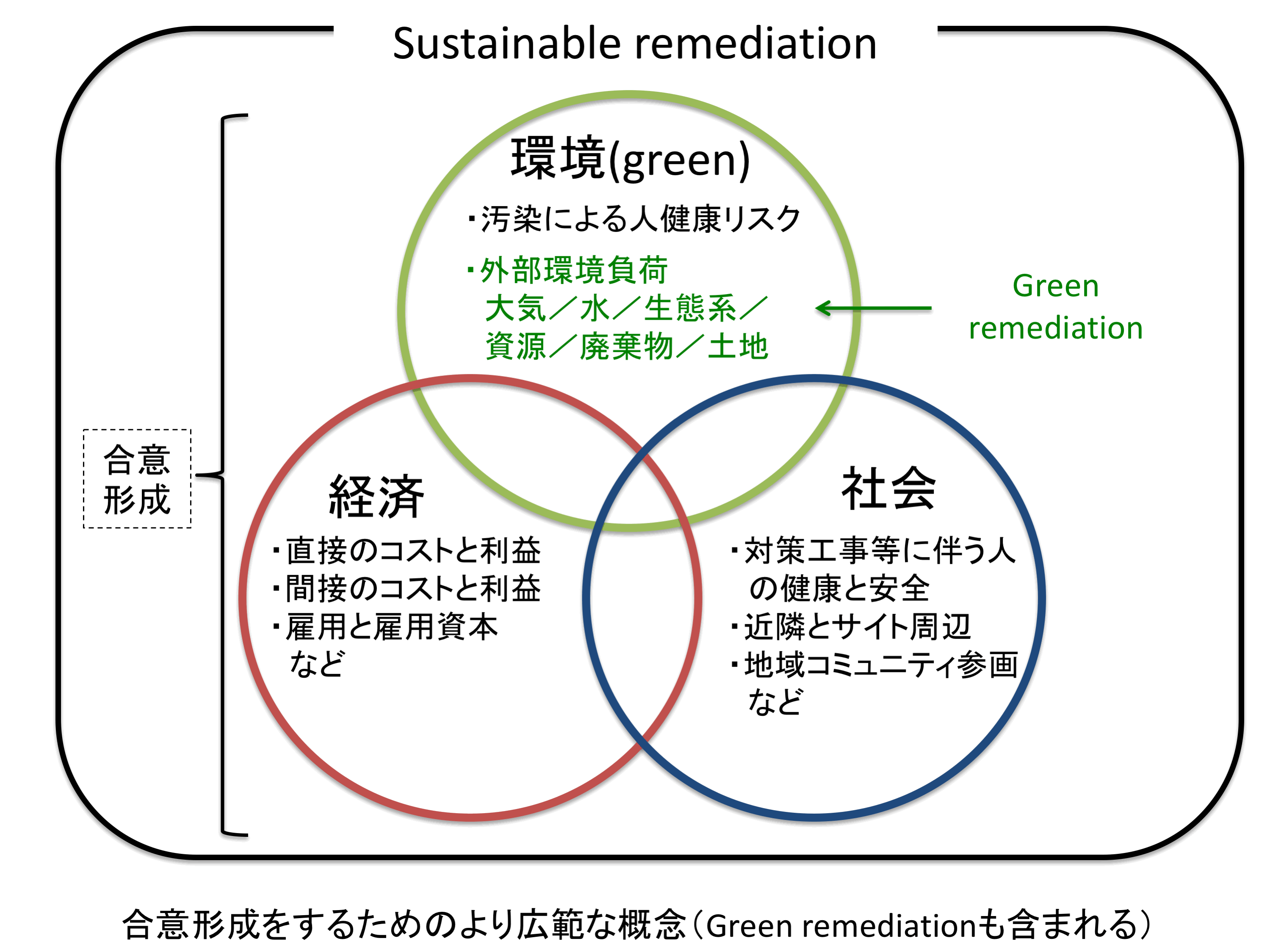
Sustainable RemediationとGreen Remediationの関係性の概念図
国際的には、国際組織SuRF(Sustainable Remediation Forum)が設立され 各国にその支部が設立されつつあること、ASTMの規格化、 さらにはISO/TC 190 “Soil Quality“ SC7/WG12”Sustainable Remediation”による 国際標準化が進められるなど、Sustainable Remediationの考え方についての 国際規格化・標準化の動きが活発化しています。 一方、我が国では、低コスト・低環境負荷型の土壌汚染調査・対策は 基本的な概念として取り組まれてきましたが、 SRの概念としては包括的な整理はされていない状況でした。
Sustainable Remediationの取り組みは、 大きく、Sustainable RemediationとGreen Remediationにわけられます。
Green Remediation
Green Remediationは、主に土壌汚染の調査対策における外部環境負荷の低減を目的とした考え方で、
Sustainable Remediationの中の環境面を中心に評価していくのが一般的です。
外部環境負荷の評価項目としては、
水、大気、廃棄物、資源、エネルギー、生態系、土地
などが用いられています。
具体的な評価方法としては、1)BMP(Best Practice Management)による定性的な評価、2)LCAの概念を用いた定量評価の2つがあり、調査・措置における外部環境負荷の低減や、外部環境負荷を考慮した措置方法の選定に用いられています。US-EPAが中心となり2008年ごろから取組を進めています。
日本では、LCAの概念を用いたモデルの開発が進んでおり、土壌環境センターが開発した土壌汚染調査・対策におけるCO2排出量推定モデルであるCOCARA、広範な環境影響の評価が可能な東京都・産総研の開発したモデル等があります。
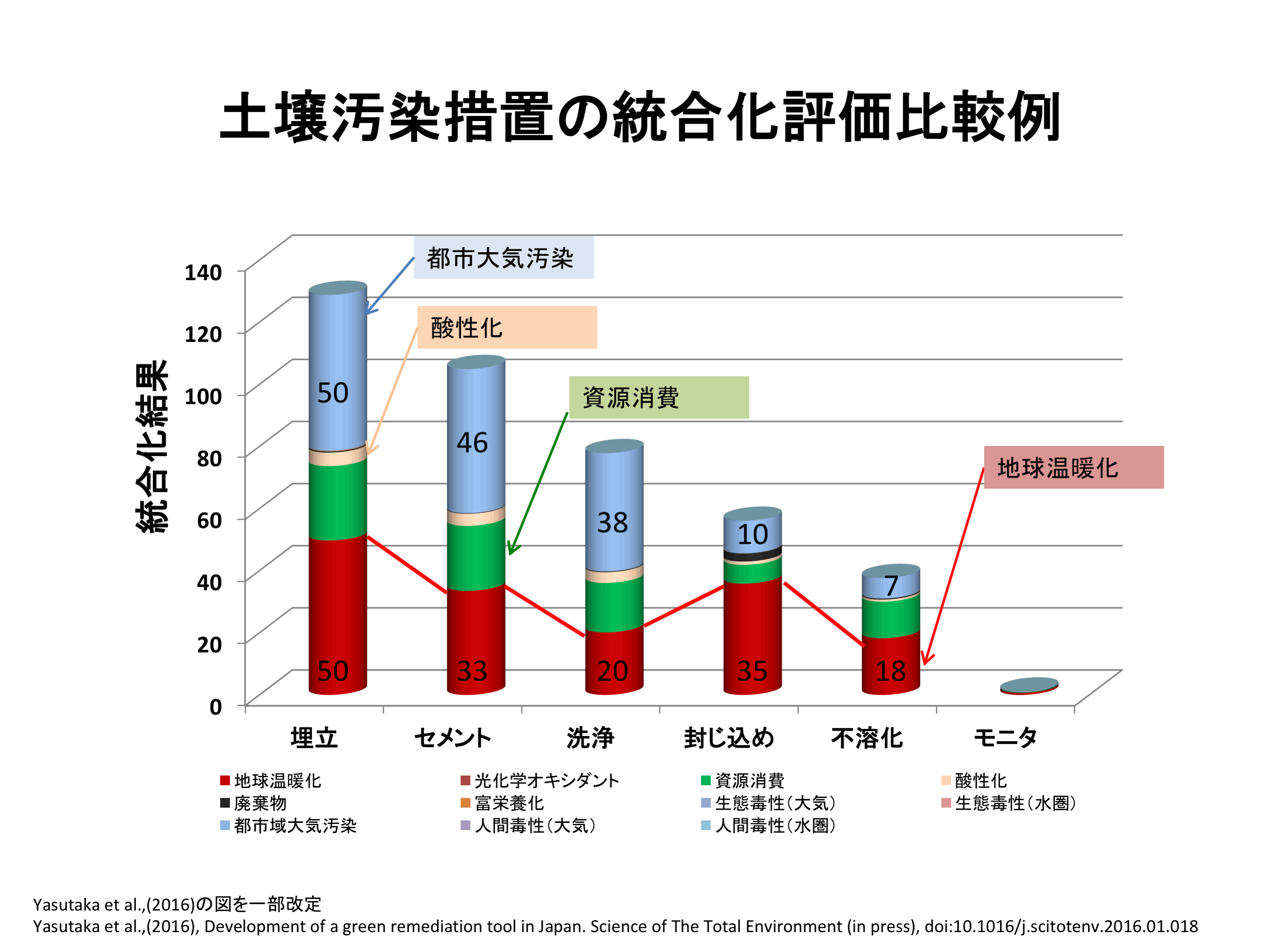
Green RemediationのLCA定量評価の一例
Sustainable Remediation
Sustainable Remediationは、環境だけでなく、 社会的、経済的側面を含めて評価し、より持続可能な土壌汚染対策を目指す動きです。 Green Remediationよりもより広範な影響を考慮しており、 環境に限らず、社会・経済という人間にとっての利益を総合的に見て 最大化することが目的とされています。 欧州のThe Network for Industrially Contaminated Land in Europe(NICOLE)、 The Sustainable Remediation Forum(SURF)、Surf−UKなどの団体が取り組んでいます。
- Surfのサイト(英語)
- 土壌汚染対策における環境負荷評価手法ガイドライン(東京都・産総研)
(日本語:主に2章にSustainable Remediationに関する説明があります。)