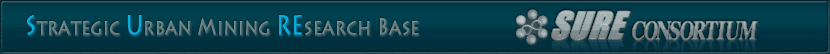第6回 JOGMEC 座談会
-

資源開発部技術課
担当調査役♦古谷尚稔氏
-

金属海洋資源部海洋資源技術課
課長代理♦髙橋達氏
-

金属資源技術研究所
副所長・主任研究員♦砂田和也氏
-

資源開発部技術課
課員♦榊原泰佑氏
-

金属資源技術研究所
研究員♦小野竜大氏
-

資源開発部技術課
担当調査役♦古谷尚稔氏
-

金属海洋資源部海洋資源技術課
課長代理♦髙橋達氏
-

金属資源技術研究所
副所長・主任研究員♦砂田和也氏
-

資源開発部技術課
課員♦榊原泰佑氏
-

金属資源技術研究所
研究員♦小野竜大氏
独立行政法人 エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、鉱山調査、採鉱、開発、生産、備蓄、リサイクル等、多岐にわたって、日本の金属資源の安定供給確保のために貢献しています。今回は、JOGMECの様々な部署で、「選鉱」に携わっている方々をお招きして、海外や海底での選鉱についてや、選鉱技術の開発にかける思いなどを伺いました。
~海底探索からリサイクルまで~
あらゆる角度から金属資源開発に挑む(1)
尾形:SUREコンソーシアム広報委員として司会進行役を務めさせていただく、産総研の尾形です。本日はどうぞよろしくお願いたします。まずは、入構順にお一人ずつ自己紹介をお願いできますか?
古谷:JOGMECに入りまして16年目の古谷です。入構から8年ほどは鉱害防止に係る業務に携わり、そのうち4年間は金属資源技術研究所で、バクテリアを使った坑廃水処理技術の開発に取り組んでいました。その後4年ほど、海底熱水鉱床の選鉱製錬に係る技術開発に携わり、現在は、陸上の鉱物資源を対象とした生産技術開発を行う部署で、各種案件の取りまとめを行っています。
尾形:学生時代から、選鉱関係の研究をされていたのですか?
古谷:学部時代は土木工学を専攻していたのですが、リサイクルに関心を持ち、大学を変えて、リサイクルについて勉強ができる大学院に進みました。そこでリサイクル技術が鉱山の生産技術であることを知り、鉱山開発にも関心を持つようになり、入構しました。
尾形:リサイクルを研究されていたのですね。続いて髙橋様、お願いします。髙橋様には、SUREアカデミーの「浮選結果予測システム検討会」でご一緒させていただいて、お世話になっています。
髙橋:こちらこそお世話になっています。私は12年目です。大学で海底熱水鉱床とコバルトクラストの選鉱をやっていまして、引き続き研究したいと思ってJOGMECに入ったのですが、最初の3年は、坑廃水処理技術の開発でした。その後、金属資源技術研究所に選鉱関係の設備を導入したり、導入した設備を使った研究をしたりしました。昨年から金属海洋資源部海洋資源技術課に配属となり、入構の動機でもあった、海洋資源の選鉱製錬の業務に携わっています。
砂田:11年目の砂田です。私は、大学で坑廃水処理の研究をしていて、JOGMECと共同研究もしていたので、そういう繋がりもあって入構し、そのまま坑廃水処理の部署に入りました。通算6年くらいその部署にいまして、坑廃水処理の技術開発をする他に、海外政府関係者に対し、休廃止鉱山の鉱害防止対策の技術指導をしたりしました。あとは、2年ほどペルーにある日本の民間企業の鉱山で選鉱について学んできまして、戻ってからは、その知識を生かして、JOGMECの金融支援の案件審査を幾つかやりました。今は、金属資源技術研究所で、難処理鉱石の選鉱や湿式製錬の技術開発に携わっています。
尾形:JOGMECでは、海外での技術指導も行っているのですね。
砂田:私が入構してちょっとしてから始まりました。日本はかなり以前から、休廃止鉱山の鉱害防止対策をやってきている歴史がありますから、南米やアジアの資源国に対する資源開発の側面支援として、鉱害防止対策をする技術者の人材育成を行っています。
榊原:次は私ですね。 7年目の榊原です。大学では、坑廃水処理や選鉱の研究をしていました。キャリアは砂田さんとほぼ被っています。私も海外での技術支援をやりました。他には、日本国内の休廃止鉱山のコンサルのような業務もやっていました。ペルーへの出向から戻り、今は、資源開発部技術課で、製錬やリサイクルに関する技術開発を委託して、進捗管理をする仕事などをしています。
尾形:砂田様と榊原様は、ペルーの鉱山に赴任されていたということですが、赴任先ではどのような仕事をしていたのですか?
榊原:鉱山の操業管理と選鉱プロセスの改善です。現場のラボを使いながら、その時々の問題を解決するためのプロセスのマイナーチェンジをしていました。
尾形:日本の研究室での研究とは何か違いますか?
砂田:本質的には変わらないのですけれど、環境が違うので、いろいろ難しい点がありました。言語はスペイン語ですし、勤務地は標高4000メートル位のところにありますし。その場で採ってすぐに試験できる、というところはすごくやりやすかったです。その場で改良すれば、すぐその時から利益が増えていくので、達成感はありましたが、お金に直結する分プレッシャーも大きかったです。
榊原:鉱山のラボ試験は、鉱山の選鉱上のリソースを考えた上で、「そのリソース内でできることは何か」というのが根底にあって、そのリソース内で条件を変えていくというような感じです。日本でのラボ試験は、採ってから日にちが経って、性状が変わっているサンプルもあるので、どちらかというと、基礎試験レベルでメカニズム解析に着目するというような感じですね。
尾形:最後に、入構3年目の小野様、お願いします。
小野:一番下っ端の小野です。大学時代は、亜鉛精鉱からさらに脈石を分ける選鉱に関する研究に取り組んでいました。入構してからは、金属資源技術部生産技術課(現:資源開発部技術課)で、銅原料中の不純物低減技術開発や、難処理鉱石の選鉱技術開発等のプロジェクトについて、進捗管理をしていました。2020年より、金属資源技術研究所に異動になりまして、最近は、選鉱以外にも溶媒抽出や乾式製錬などに取り組んでいます。