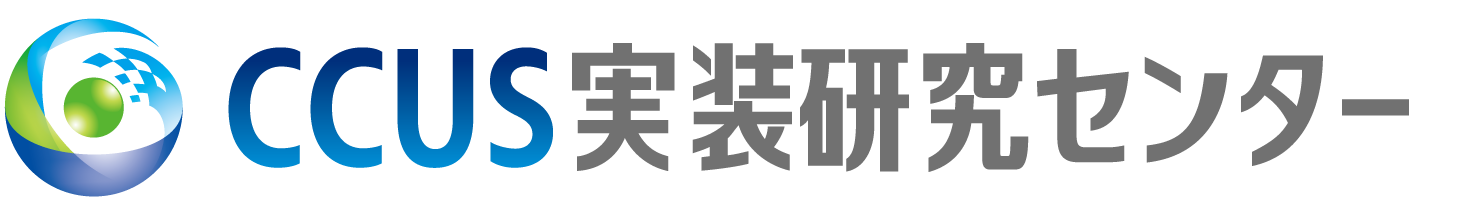CCUS実装研究センター紹介
CCUS実装研究センターについて
2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、省エネルギー化、再生可能エネルギーの導入、水素やバイオ燃料などへの燃料転換に加えて、 産業排ガス、燃焼排ガス、大気などからCO2を分離回収し、燃料や化学品への再利用、あるいは地中への貯留や鉱物への固定を通じて、 大気へのCO2排出を抑制する、CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)技術の社会実装が必須です。
2025年4月に設立されたCCUS実装研究センターは、CO2分離回収から資源化、貯留、固定、LCA(Life Cycle Assessment)/TEA(Techno Economic Assessment)評価 に至るまでの要素技術を統合し、ベンチスケールやパイロットスケールでの実証とCCUSシステムの優位性の提示を通じて、「高効率CCUSバリューチェーン」の構築と社会実装を目指します。 民間企業、大学、公的研究機関、行政など、幅広いステークホルダーと連携し、日本発のCCUS技術を日本から世界に展開する中核的研究拠点として活動を推進していきます。
研究センター長あいさつ

我が国が目標としている2050年カーボンニュートラル達成のためには、再生可能エネルギー等カーボンフリーのエネルギーを最大限導入することに加えて、 化石資源の燃焼などから発生するCO2を分離回収して地中などにためておく貯留(CCS)の実現が有効です。 また、カーボンニュートラル実現までの過渡期には、分離回収したCO2を燃料や化学品に再利用することで、化石資源の使用量を減らすCCUも有効です。
CCUS実装研究センターでは、こうした社会課題に対応するため、CCUについては、これまで開発してきた液体燃料や化学品の製造に関する産総研の先進的な要素技術を統合して、
分離回収から電解・変換、製造に至るCCU一貫システムの実現を目指し、同時に原料から製造、廃棄までの環境影響を考慮したライフサイクルアセスメント(LCA)と
コスト評価可能な評価ツール開発を行い、CCUによる燃料や化学品のCO2排出削減量やコストも含めた環境価値を容易に提示可能にすることを目標としています。
また、CCSは、CCS事業法が制定され、国内で貯留事業が進行中ですが、課題である安定した貯留を実現するための管理マネジメント手法を開発し、安定的な貯留の実現を目標としています。
私たちは、「CO2を削減、活用して未来の資源へ」を掲げ、これらの技術開発と社会実装を実現することで、産業界の「高効率CCUSバリューチェーンの早期実現」に貢献する所存です。
組織
| 研究センター長 | 玄地 裕 |
|---|---|
| 副研究センター長 | 倉本 浩司 |
| 副研究センター長 | 牧野 貴至 |
| 首席研究員 | 徂徠 正夫 |
CO2回収プロセス研究チーム
| 研究チーム長 | 牧野 貴至 |
|---|---|
| チーム員 | 長谷川 泰久(兼務)、河野 雄樹、藤井 達也、池田 歩 |
化学品製造研究チーム
| 研究チーム長 | 松本 和弘 |
|---|---|
| チーム員 | 中村 功、高田 尚樹(兼務)、鷲見 裕史、田中 洋平、宮澤 朋久、長江 春樹、馬場 宗明(兼務)、百相 瑞貴、小泉 博基 |
合成燃料製造・評価研究チーム
| 研究チーム長 | 石山 智大 |
|---|---|
| チーム員 | 瀧川 悌二(兼務)、中川 実徳(兼務)、陳 仕元、伊藤 覚、重信 咲季、鳥海 創、堀口 元規 |
CO2変換・固定プロセス研究チーム
電気化学と化学工学の知見と経験を結集し、当該技術をプロセスとして完成させ、早期の社会実装を目指します。
| 研究チーム長 | 倉本 浩司 |
|---|---|
| チーム員 | 劉 彦勇、高坂 文彦、笹山 知嶺、小野 祐耶、佐山 和弘(兼務)、三石 雄悟(兼務)、草間 仁(兼務)、 小寺 正徳(兼務) |
CO2地中貯留研究チーム
| 研究チーム長 | 徂徠 正夫 |
|---|---|
| チーム員 | 加野 友紀、後藤 宏樹、西山 直毅、朝比奈 大輔、藤井 孝志、西木 悠人(兼務)、堀川 卓哉(兼務) |
CCUSシステム評価研究チーム
| 研究チーム長 | 森本 慎一郎 |
|---|---|
| チーム員 | 片岡 祥、小澤 暁人(兼務)、原 伸生、GUZMAN URBINA ALEXANDER、Nguyen Thuy、GONOCRUZ RUTH ANNE(兼務)、Tantiwatthanaphanich Thanapan |