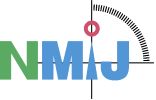お知らせNEWS
お知らせ 「講演会3件のお知らせ」 NEW!
★講演会 1
包括的計測法国際標準化調査研究会ワークショップ
~ 海外における包括的計測手法の環境規制への活用動向 ~
主催:一般社団法人産業環境管理協会
#谷保ほか講演予定
〇参加費:無料
〇日 時:2025年2月13日(木) 13:30~15:40(WEB 開催)
参加リンク:https://jemai-meeting.webex.com/jemai-meeting/j.php?MTID=m1445a766f7b2277a5cf966235b731e55
ウェビナー番号: 2519 725 9886
ウェビナー パスワード: zmPh4WdtG82
★講演会 2
NSC定例勉強会「PFAS汚染に対し企業はどう取り組んでいくか」
主催:サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク(NSC)
協力:サステナビリティ日本フォーラム、環境経営学会、環境監査研究会
https://www.gef.or.jp/news/event/nscseminar250219/
〇日 時:2025年2月19日(水)14:00~16:00
〇開催方法: Zoomミーティングによる開催
#山下ほか講演予定
# 二件の講演の後にPFAS対策に取り組む企業の事例紹介を何件か予定しています。自社技術・事例紹介をご希望の方は下記、主催元にお問い合わせください。
〇お問い合わせ先
NSC事務局
京極 絵里(KYOGOKU, Eri) Email: nsc"at"gef.or.jp ("at"を@に直してから送信してください)
★講演会 3
【産学連携学会 九州支部 セミナー開催のご案内】
令和6年度産学連携ネットワーク会議セミナー
「 PFAS対策技術の問題点 - 半導体産業を例として -」
PFAS対策技術コンソーシアム会長 山下信義
講演概要「日本国内のPFAS対策技術が欧米に比べ、大幅に遅れていることがSEMICON Japanや地盤技術フォーラムなどで明らかになったが、その原因と対策についてPFAS対策技術コンソーシアムの4年間の活動を通じて解説する。特に半導体産業を具体例として分析化学的観点から考えてみたい。」
〇日 時:2025年2月26日(水)13:30-14:30
〇参加費:無料(非会員の方も聴講可能です)
下記サイトにアクセスしお申し込みください(Googleフォーム)
https://forms.gle/Cg7wsHohmSDquAoH8/
〇申込締切:2月24日(月)
〇お問い合わせ先
〒860-8555 熊本市中央区黒髪2-39-1
熊本大学 熊本創生推進機構 緒方智成
E-Mail : t_ogata"at"kumamoto-u.ac.jp ("at"を@に直してから送信してください)
更新日:令和7年1月24日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアムホームページの (新館) の公開」
★PFAS対策技術コンソーシアムホームページの (新館) を公開しました。
2025年3月までは旧ホームページと並行してアップデートしますが、2025年4月1日以降は新館に統一されます。
「PFAS対策技術コンソーシアム (新館) 」
更新日:令和6年12月3日
お知らせ 「Nature Communications誌掲載のお知らせ」
★南京大学のSi Wei教授と環境創生研究部門の山下信義上級主任研究員、谷保佐知副部門長の共著論文がNature Communicationsに正式受理されました。
12月初旬にopen access として公開されます。
特にSi Wei教授は12月11日にサーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、横浜アナリティカルセンターで開催される、PFASエキスパート勉強会「PFAS-AI, 人工知能を用いた3000種類のPFAS迅速分析」のために来日講演されます。Nature Communicationsに掲載された研究成果についてもご講演いただきますので、皆様、是非ご参集ください。 申し込み先は下記となります。(募集中参照)
PFASセミナー「PFAS-AI, 人工知能を用いた3000種類のPFAS迅速分析」のご案内
Nature Communications掲載論文タイトル
Two-Layer Homolog NetworkとDatabase Mining 人工知能技術を用いた地球規模有害物質汚染の歴史的再現
(Global and Historical Use of Novel Contaminants Revealed by Two-Layer Homolog Network and Database Mining)
著者:Zhaoyu Jiao, Sachi Taniyasu, Nanyang Yu, Xuebing Wang, Nobuyoshi Yamashita, Si Wei
概要
分子構造ネットワークと、クラス予測の組み合わせであるTwo-Layer Homolog NetworkとDatabase Mining技術を用いた人工知能non-target analysis (PFAS-AI)により、
日本国内で採集した12種類の撥水剤製品と2種類の工業スラッジより94種類のPFASを検出した。その中でも「36種類の新規PFAS」は本報告が世界で初めての測定例である。
同様な手法を7か国の公開データベースに適用することで、地球規模のPFAS汚染の歴史の再現に成功した。本報告で、PFASの生産使用がどのように拡大されてきたか、その歴史的経緯を地球規模で再現する手法を提供する事で、有害化学物質管理・規制に関わる国際条約や政策決定に貢献が期待される。
更新日:令和6年11月29日
お知らせ 「2024年12月開催国際講演会「PFAS対策技術の将来」の講演プログラムを更新しました。」
こちらをクリック
更新日:令和6年11月15日
お知らせ 「株式会社キャンパスクリエイトの「PFAS対策支援」情報を公開しました。」
こちらをクリック
更新日:令和6年11月15日
お知らせ 「PFASエキスパート勉強会「PFAS-AI, 人工知能を用いた3000種類のPFAS迅速分析」(12月11日)について」
★PFAS対策技術コンソーシアムのコアメンバーの協力によりPFASエキスパート勉強会「PFAS-AI, 人工知能を用いた3000種類のPFAS迅速分析」を
12月11日午後にサーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、横浜アナリティカルセンターにおいて開催します。
12月12日、13日のPFAS対策技術コンソーシアム国際講演会及びSEMICON Japan サステナビリティー・サミットと協調するイベントです。
機械学習技術を利用したPFASの全球汚染の解析(Science Advances,こちらをクリック) 他、世界で最も進んだ人工知能 (AI) を用いてPFAS対策技術を開発している 南京大学や香港城市大学のPFAS専門家を招へいし「現場」で講義いただき、「実際の分析装置を用いたノンターゲット分析デモンストレーション」
も用意します。先のダイオキシン国際会議でオットーハッチンガー賞を受賞した研究発表も含め、環境研究総合推進費「環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発」 の研究計画についても解説予定です。
特に要望があれば来日されるPFAS専門家とコンソーシアム会員団体との個別面談も予定しますので、ふるってご参加ください。
下記よりお申し込みください。
こちらをクリック
更新日:令和6年10月22日
お知らせ 「PFAS対策技術マッチングのために、株式会社キャンパスクリエイト様にご協力いただきます」
★PFAS対策技術コンソーシアムを利用する産学官業界の急速な拡大のため、マッチングについては、株式会社キャンパスクリエイト様
(以後キャンパスクリエイト)にもご協力頂く事になりました。
25年以上の実績を有する政府認定の技術移転(TLO)専門家集団であるキャンパスクリエイトは、特定業種に限定される内部型TLOではなく、
産学官全てのニーズとシーズに対応可能な広域型TLOの利点を生かし、今までよりも柔軟に、相談元の立場に立った、マッチングサービスが可能です。
PFAS対策技術コンソーシアム事務局と株式会社キャンパスクリエイト様【pfas.info”at”campuscreate.com(”at”を@に直してから送信してください)】
のどちらにご連絡して頂いても構いませんので、 お気軽にご相談下さい。
更新日:令和6年10月15日
お知らせ 「「総PFAS分析技術」の精度管理試験参加者の募集」
★環境研究総合推進費「5-2401 環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発」において開発中の「総PFAS分析技術」の
精度管理試験を行います。
募集要項をご確認いただき、精度管理試験に参加ご希望の方は10月18日までにコンソーシアム事務局までお知らせください。
試験参加機関には「参加費無料で分析操作手順書と試験試料を配布」します。
概要:下記三種類の測定技術について精度管理試験を行います。
・「総PFAS分析技術」として、ISO21675に代表されるPFASの多成分個別分析
・抽出態有機フッ素(EOF)測定、ISO21675の修正法となります
・TOP assay (総酸化法)
こちらをクリック
更新日:令和6年10月4日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアムがPacifichem 2025へ招待されました」
★アメリカ化学会前会長のAngela K. Wilson教授からの要請により、PFAS対策技術コンソーシアムのPacifichem 2025 (ハワイ, 2025年12月)
への参加が決定しました
Pacifichem は5年おきに、世界中の研究者が最新研究成果を共有するために、環太平洋の中心に位置するハワイ諸島で開催する世界最大規模の国際研究集会です。
PFAS対策技術コンソーシアムと連携する多数の国内外研究者・産業界の参加を予定しますので、ふるってご参加ください。
PFAS対策技術コンソーシアムの会員には参加特典も用意しております。
Pacifichem 2025 の開催情報は下記をご確認ください。
(こちらをクリック)
更新日:令和6年9月27日
お知らせ 「地盤技術フォーラム (9月18-20日開催) 報告、SEMICON JAPAN、コンソーシアム国際講演会「PFAS対策技術の将来」他」
9月18、19、20日に東京ビッグサイトで開催した「地盤技術フォーラム」では、驚くべきことに、展示内容の三分の一以上がPFAS対策新技術の紹介でした。
三年前にはリスク一辺倒の議論しか無かった国内PFAS問題の認識が、PFAS対策技術コンソーシアムの三年間の活動により、PFAS環境修復技術の国内普及へと大きくかじ取りに成功したことが明確になり、環境省も含め関係各所より高く評価していただきました。
一部の地方自治体ではPFAS環境修復事業者とのマッチングにも成功しております。
なお「地盤技術フォーラム」で18日に開催した専門家セミナー「国内外のPFAS対策最新技術について(こちらをクリック) 」の講演内容は会員限定ページで公開予定です。
関連して、12月12日と13日に開催予定のPFAS対策技術コンソーシアム国際講演会「PFAS対策技術の将来」では、8月に行った欧州PFAS対策技術現地見学会報告、ノルウェー環境省やストックホルム条約事務局からのPFAS対策方針の説明など、多数の国外専門家よりPFAS対策技術最新情報をご提供いただきます。
特に、半導体産業の中心組織であるSEMIジャパン様とも協力させていただき、SEMICON JAPAN (こちらをクリック) と同時開催することで、講演内容の相互配信も予定しておりますので、業種にかかわらず、最新のPFAS対策技術の情報収集・実用化を目指す団体・個人の方の参加を歓迎いたします。
# 具体的には、12月12日のPFAS対策技術コンソーシアム国際講演会「PFAS対策技術の将来」のオンライン会議のURLをSEMICON JAPANのサステナビリティ・サミットのウェブサイトに掲載させていただきます。
また12月13日午後のSEMICON JAPAN サステナビリティ・サミットのオンライン講演をPFAS対策技術コンソーシアム会員限定で配信いたします。
これによりSEMICON JAPANの参加者とPFAS対策技術コンソーシアムの会員の両方でPFAS対策に関する最新技術の共有が可能になります。
# これ以外にも、PFAS対策技術コンソーシアムのコアメンバーと共同で「PFAS-AI : 人工知能による3000種類のPFAS迅速分析」の勉強会等、
同時開催イベントも予定しておりますので、ご期待ください。
更新日:令和6年9月27日
お知らせ 「環境研究総合推進費について」
環境研究総合推進費1G-2102「ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発」事後評価ヒアリングにて
Sランク評価 (総合評価点 122点)が決定しました。
また、実質的な継続課題である「5-2401 環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発」において「総PFAS」分析技術の精度管理試験を行います。
参加費無料で分析操作手順書と試験試料を配布します。本ホームページで参加者を募集しますので、しばらくお待ちください。
参考) マッチング 4-B.環境研究総合推進費5-2401「環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発」参画機関又は協力機関としての
人材育成と社内分析システム確立のためのエキスパート派遣
更新日:令和6年9月17日
お知らせ 「2024年8月26日から9月5日にかけて開催した『欧州PFAS対策技術現地見学会報告簡易版』を公開しました。」
会員向け詳細報告は後日、会員ページに掲載予定です。
欧州PFAS対策技術現地見学会報告簡易版
更新日:令和6年9月6日
お知らせ 「PFAS対策技術事業者総覧の作成について」
国内ニーズが急速に高まっているPFAS環境調査・処理技術について、対応可能な事業者を探すことが難しい、事業公開している事業者についても本当に効果があるのか分からないため、コンソーシアム事務局に「信頼できる事業者を紹介してほしい」という依頼が増えております。そのため、環境省様他コアメンバーのご要望により、「PFAS対策技術事業者総覧(調査・処理技術編)」を、コンソーシアム事務局で取りまとめることとなりました。
総覧には会員外の情報も含めますので、総覧に掲載をご希望のPFAS対策事業者様には、記入フォームを事務局までご提出いただければ幸いです。
対象は、分析/調査事業者・処理事業者・基本技術提供事業者・コンサルタント事業者とします。
# コンソーシアム会員外の事業者様には提供情報の確認をさせていただくこともありますので、予めご了承ください。
※記入フォームの事務局への提出締め切り:10月21日月曜日
# 提出していただいた情報については目的以外の使用は行いません。
# 記入フォームに記載の注意事項を十分ご確認ください。
PFAS対策技術事業者総覧記入フォーム
更新日:令和6年8月20日
お知らせ 「閲覧可能な一般公開用資料及び会員限定公開資料に下記追加しました。」
★データベース:閲覧可能な一般公開用資料
A-29. 「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の環境研究の動向~分析方法を中心に~」谷保佐知、2023年度産学連携学会九州支部ネットワーク会議
(2024年3月19日)
★会員限定:会員限定公開資料
「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)測定技術の最新動向と将来展望」谷保佐知、第62回環境化学講演会「PFAS分析技術に関する講演会」
(2024年3月18日)
更新日:令和6年7月29日
お知らせ 「地盤技術フォーラム特別セミナー「国内外のPFAS対策最新技術について」のセミナープログラムが公開されました。」
★特別セミナー「国内外のPFAS対策最新技術について」
開催日時:9月18日㈬ 13:00-16:00
「PFAS対策技術コンソーシアムの活動について」山下信義
「国内土壌中PFASの安定化技術について」山﨑絵理子
「土壌を含む農業環境中のPFAS について」殷 熙洙
「PFAS分析の信頼性確認に必要な標準物質について」羽成修康
「ISO21675他、PFASの国際標準分析技術と大気中PFAS分析技術について」谷保佐知
「欧州におけるPFAS対策最新技術について」Leo Yeung教授
スウェーデン、エーレブルー大学のYeung博士のオンライン講演、先日公開した「農地土壌に含まれるPFASを分析する暫定マニュアル」他、PFAS対策最新技術が広く一般に公開される貴重な機会ですので、下記ご確認いただき、ご参集ください。
会場スペースは100名前後のようですので、早めの入室をお勧めします。
セミナープログラム
更新日:令和6年7月23日
お知らせ 「PFASの評価に必要な分析技術 Webセミナー(2024年4月18日開催)での依頼講演」再配信
★「PFASの評価に必要な分析技術 Webセミナー(2024年4月18日開催)での依頼講演」更新日:令和6年3月1日、の再配信を下記のとおり行います。
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社様の依頼により「PFASの評価に必要な分析技術 Webセミナー(2024年4月18日開催)」で、
当コンソーシアムの谷保が行った講演「PFASの包括的な評価のための測定技術の開発」の再配信を行います。
どなたでも視聴できますので、下記よりご入室ください。MS Teamsイベントとしての再配信となります。
開催日時:8月2日㈮ 13:00より
「PFASの包括的な評価のための測定技術の開発」
更新日:令和6年7月5日
お知らせ 「農研機構より農地土壌に含まれるPFASを分析する暫定マニュアルを公開」
以前から、下記などの文献で予告してきましたが、7月3日付で農研機構より「農地土壌に含まれるPFASを分析する暫定マニュアル」が公開されました。
これにより国外で先行する土壌中PFAS全国調査について、国内でもようやく端緒につく事が期待できます。
特に国際標準分析規格であるISO21675の分析対象、「30成分のPFASの土壌分析」が国内分析事業者レベルでも可能になったことは大きな進歩といえます。
本マニュアルの基本技術であるISO21675を開発した谷保が農研機構の殷博士と共同で、第3回環境化学物質合同大会(第32回環境化学討論会/第28回日本環境毒性学会研究発表会)(広島市・JMSアステールプラザ・7月2日~5日)で説明を予定しますので、ご参集ください。
★農地土壌に含まれるPFASを分析する暫定マニュアルを公開 (農研機構)
こちらをクリック
閲覧可能な一般公開用資料
A-9.「Environmental kinetics of PFASs in rice paddy field, Japan – the lysimeter experiment - 」(Panほか、DIOXIN2016、2016、Firenze, Italy)
A-19.「Accumulation of perfluoroalkyl substances in lysimeter-grown rice in Japan」(山崎ほか、DIOXIN2019、2019、Kyoto, Japan)
日本語文献
14.山下 信義, 谷保 佐知, 山﨑 絵理子, 羽成 修康「ペル及びポリフルオロアルキル化合物分析技術」— PFAS 海洋化学からPFAS 農業化学へ—
土壌の物理性, 2024 年 156 巻 p. 41-48
13.殷 熙洙, 山﨑 絵理子, 谷保 佐知, 山下 信義「農業環境におけるPFAS について」土壌の物理性, 2024 年 156 巻 p. 49-57
12.谷保佐知、山下信義、「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物の測定技術の最新動向と将来展望」月刊技術士、2024年2月、p.8-11
11.山﨑絵理子, 谷保佐知, 羽成修康, 三木芳恵, 金子蒼平, 山下信義「液状活性炭注入による黒ボク土中PFAS安定化技術のISO21675を用いた評価」
分析化学、2024 年 73 巻 1.2 号 p. 31-37
更新日:令和6年7月5日
お知らせ 「12月開催予定、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会「PFAS対策技術の将来」のお知らせ」
2023年10月にSONY CITY品川で開催したPFAS対策技術コンソーシアム国際講演会「国内PFAS研究の失われた15年を取り戻し日本発新技術を国際普及することは可能か?」は、それまでリスク以外の議論が不在であった国内PFAS問題を大きく変える契機となり、これ以降、国外で実用化されているPFASの環境修復・分解技術の国内普及にPFAS対策の焦点が移ることになりました。
従って世界最新のPFAS研究成果・対策技術を国内に周知する事で、国内PFAS対策の遅れを取り戻すことが期待できます。
そのため今年12月に再度、世界最新のPFAS研究・対策技術についての国際講演会「PFAS対策技術の将来」を開催します。
2024年12月初めに東京ビッグサイトで一般参加も可能な形で予定しますので、詳細情報をお待ちください。
特に、9月18日に地盤技術フォーラムで開催する特別セミナー「国内外のPFAS対策技術について」と、8月26日から9月4日に開催する「欧州PFAS対策技術現地見学会」と合わせ、広域環境のPFASを効率的に回収、回収されたPFASを閉鎖系でフッ素まで分解、最終的にフッ化カルシウム等として回収まで可能な新技術等、PFASにかかわる全ての産業活動の見直しにもつながる最新科学技術の紹介を予定していますので、ご期待ください。
「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会」東京ビッグサイト
更新日:令和6年7月1日
イベント情報 「日本イオン交換学会第36回イオン交換セミナー(2024年7月19日開催)での依頼講演について」
★ 日本イオン交換学会第36回イオン交換セミナーでの依頼講演を行います。
開催日時:令和6年7月19日(金) 10:00~17:00
講演タイトル:「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物の測定技術の研究動向」
発表者:谷保佐知
詳細および申し込みは下記
こちらをクリック
更新日:令和6年6月7日
お知らせ 「6月24日 コンソーシアム打ち合わせ会議について」
★ 6月24日に下記内容でコンソーシアム打ち合わせ会議を行います。
1. 地盤技術フォーラム(東京ビッグサイト、9月18日~20日、参加無料) 及び 同時開催の特別セミナー「国内外のPFAS対策最新技術について」
農業環境中PFAS分析法の規格化をリードしている農研機構の殷博士、PFASに対する総合戦略検討専門家会議委員の谷保博士に加え、スウェーデンエーレブルー大学のLeo Yeung博士他によるオンライン公演を開催します。また産総研が費用負担する事で会員団体の技術紹介用のブースを準備します。ブース利用は先着順となります。
2. 欧州PFAS対策技術現地見学会について。
日程は8月26日より9月2日で決定しました。現地見学・打ち合わせ機関は、ノルウェー環境省、ノルウェー大気科学研究所(NILU)、スウェーデン農業科学大学(SLU)、エーレブルー大学、ドイツBAM、デンマークARAGORN、ベルギーOVAM (3M社)の予定です。特に、世界で最も進んだ有害物質管理システムを社会構築しているノルウェー環境省との打ち合わせは、事前調査で訪問したドイツ(ボン・バイエルン)環境省、昨年10月の国際講演会にご参加いただいたBiegel-Engler博士のご講演と合わせて、欧州におけるPFAS対策立案の中心に参加する機会となります。個別参加は締め切りましたが、業界団体などの現地参加は可能です。
3. 2)に関連して以下3件の講演動画と最新論文の日本語解説を予定します。昨年10月の国際講演会にご参加いただいたドイツ環境省のBiegel-Engler博士のご講演「PFAS in Soil and Groundwater – Progress and Comprehensive Challenges in Germany」(これについてはホームページへの掲載予定はありません)、会員限定公演動画12. 「SWATH-F: A Novel Nontarget Strategy Based on the SWATH-MS Deconvolution Method Assist in Annotating PFAS Homologs(分子ネットワークモデルと機械学習を応用した全てのフッ素化合物の人工知能網羅分析技術 : SWATH-F:)」、会員限定公演動画8.「PFAS analytics and their relation to PFAS remediation(PFAS分析技術と環境修復技術の連携について)」の日本語解説を予定します。特に、会員限定公演動画8のメカノケミカル分解技術はPFAS処理技術として最も有望な最新技術として注目されています。また、環境研究総合推進費(1G2102及び5-2401)の最新研究成果である「Machine learning–enhanced molecular network reveals global exposure to hundreds of unknown PFAS」(Sci. Adv. 10, eadn1039 (2024) 23 May 2024)についてもごく簡単に解説を予定します。
こちらをクリック
4. その他、PFASエキスパート養成講座、技術相談・コンサルタント・マッチングなどについて
更新日:令和6年6月3日
お知らせ「第48 回(令和6年度)環境研究合同発表会 (参加無料・オンライン同時開催)」について
主催:神奈川県市環境研究機関協議会(神奈川県環境科学センター、横浜市環境科学研究所、川崎市環境総合研究所)
開催日時:令和6年6月12 日(水)(午後1時00 分~午後4時45 分の予定)
特別講演
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 上級主任研究員
PFAS 対策技術コンソーシアム会長 山下信義
講演タイトル「国内PFAS問題解決のためのストラテジー、基礎から応用まで」
(特に地方自治体が抱えるPFAS問題対応について「PFAS対策技術コンソーシアムデータベース」を用いた具体的対策立案について、平易な説明を予定する)
その他のプログラムは主催元に問い合わせのこと。こちらをクリック
更新日:令和6年5月10日
お知らせ「中国におけるPFAS対策技術の最新情報に関するレポート」について、調査リクエストのアンケートを行います。
昨年10月の国際講演会で「過去23年間の中国と日本のPFAS研究の総括」についてご講演いただきました、Paul KS Lam教授他の著名専門家の方々に「中国におけるPFAS対策技術の最新情報に関するレポート(英語版)」の作成を依頼しました。PFAS対策技術コンソーシアムがセッションオーガナイザーとして寄与するSETAC-Asia-Pacific (2024年9月21-25日、中国、天津)でも、アジアにおけるPFAS最新技術についての講演を予定しますが、日本国内ではこれらの情報の入手は非常に困難です。国際的に置き去りにされつつある日本のPFAS対策技術底上げのためには、「PFASの安全利用, “pollution control”」により産業界の持続的発展を国策として進めている中国の現状理解がカギとなります。このため、本コンソーシアムの国外スーパーバイザーにご協力いただき、本レポートをコンソーシアム会員に提供予定です。
つきましては、どのような情報を本レポートに含めてほしいか、コンソーシアム会員だけでなく、一般の方のご意見も歓迎しますので、下記アンケートにご記入の上、5月31日までに事務局までメールでご提出ください。
なお、アンケート結果は提出元が特定されない形で、上記目的に使用させていただきます。
「中国におけるPFAS対策技術の最新情報に関するレポート」の調査リクエストこちらをクリック
詳細は、公開データベースA-28.「欧州PFAS対策技術現地見学会事前調査報告(一般向け概要版)と第一回欧州PFAS対策技術現地見学会申し込み方法」の概要報告9及び10をご参照ください。
# 本レポートは、当面の間は、概要報告9及び10で説明している国外エキスパートコンサルタントとの契約をご検討中の会員様のみへのご提供となります。
更新日:令和6年4月22日
お知らせ「欧州PFAS対策技術現地見学会事前調査報告(一般向け概要版)と第一回欧州PFAS対策技術現地見学会申し込み方法」をデータベースに公開しました。
会員向けの詳細版は後日アップデートしますが、8月から9月に予定する現地見学会の申し込み要領を記載していますので、希望される方はご確認ください。
更新日:令和6年3月15日
お知らせ「環境研究総合推進費5-2401 環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発(産総研・島津テクノリサーチ他)」採択のお知らせ。
「環境研究総合推進費5-2401 環境中PFAS の包括的評価を目指した総PFAS スクリーニング測定技術の開発(産総研・島津テクノリサーチ他)、研究期間2024-2026」が3月13日付で採択されました。本研究は、環境研究総合推進費「5B-1106 残留性有機フッ素化合物群の全球動態解明のための海洋化学的研究 2011-2013 事後評価S 評価」、1G2102「ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発 2021-2023 中間評価S 評価」等の研究成果をもとに、今後のPFAS対策のキーワードである「総PFAS」の国際標準分析技術の確立を目指すプロジェクトです。
関連情報はデータベースA-22、A-26、A-27、A-28、日本語文献9、11、英語文献58、68をご確認ください。
本プロジェクトにより「国内PFAS研究の失われた15年」を取り戻すだけではなく、アジア発科学技術を用いて地球上からPFASを取り除くターニングポイントを目指しますので、PFASエキスパート養成講座・共同研究等積極的なご参加をお願いいたします。
更新日:令和6年3月15日
イベント情報 「地盤技術フォーラム2024出展・特別セミナー開催・第一回欧州PFAS対策技術見学会の募集について」
9月に開催される地盤技術フォーラム2024(東京ビッグサイト9月18日-20日)にPFAS対策技術コンソーシアム事務局及び会員団体が出展します。
コンソーシアム会員団体が開発した様々なPFAS対策技術を一般公開するとともに、国内初の土壌中PFAS標準分析法やエーレブルー大学・産総研・ソニーグループの共同プロジェクトであるFORMAS「Development of novel porous carbon materials for reducing total PFAS emission including cost-benefit analysis and bioavailability of immobilized PFAS to terrestrial organisms」等、最新情報の初公開となります。
あわせて特別セミナー「欧州におけるPFAS対策最新技術について(詳細は近日公開)」を開催します。通常はコンソーシアム会員のみに配信している、海外著名専門家のご講演等をリアルタイムで行う予定です。
また8月から9月に予定する、第一回欧州PFAS対策技術「現地見学会」の申し込み窓口も地盤技術フォーラム2024に依頼しましたので、下記申し込み期間中にお問い合わせください。
★地盤技術フォーラム2024 こちらをクリック
開催場所:東京ビックサイト
開催日:9月18日-20日
# PFAS対策技術コンソーシアム会員は「会員特別価格」で出展可能
★第一回欧州PFAS対策技術見学会(今年8月から9月にかけて欧州著名研究機関の最新技術を見学します)
申込期間:4月1日より5月10日まで (タイトなスケジュールなので締め切り厳守、期間外の問い合わせには対応できません)
申し込み先:地盤技術フォーラム2024「お問い合わせ」に「欧州PFAS対策技術現地見学会申し込みについて」とお問い合わせください。
#会員外の一般参加も可能ですが、PFAS対策技術コンソーシアム会員は「会員特別価格」で参加可能
見学会の詳細は「募集中」に随時アップデートしますが、参加機関の希望内容に適した訪問機関を下記より数機関選択します。
旅費滞在費は自己負担ですが、コンソーシアム事務局が現地随行・通訳を行います。
ノルウェー大気科学研究所 (ノルウェー、Kjeller)、エーレブルー大学 (スウェーデン エーレブルー市)、スウェーデン農業科学大学 (スウェーデン ウプサラ市)、
ドイツ環境省 (ドイツ ボン)、Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology (ドイツ アウスブルグ(バイエルン))、
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)(ドイツ ベルリン)、デュッセルドルフ市PFAS環境修復事業現場、
Cornelsen Umwelttechnologie GmbH (ドイツ エッセン)、E.P.FIRE (ドイツ ムッフ)、ARAGORN(デンマーク コペンハーゲン)、
Public Waste Agency of Flanders (OVAM) (ベルギー フランドル)
# 各機関で見学可能な施設・技術の詳細は、2月末に行った「欧州PFAS対策技術見学会事前調査報告(データベースに近日公開予定)」を参照ください。
事前調査概要は連携先の一つである欧州有害物質汚染対策組織「ARAGORN」のニュースでも公開されています。
「From Japan to Sweden: an intercontinental view on how to discuss approaches to soil pollution」
こちらをクリック
更新日:令和6年3月12日
イベント情報 「3月27日開催CRDS俯瞰ワークショップの依頼講演のお知らせ」
国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター (CRDS)の依頼により、下記ワークショップで本コンソーシアムの山下が講演します。
主に政策提言立案のためのクローズド会議ですが、政府所管等重要なステークホルダーにはアナウンスがいくようですので、機会がありましたらご参加ください。
後日、政策提案報告書として一般公開される予定です。詳細は下記CRDSのホームページよりご確認ください。
開催日:3月27日(水)
「環境・エネルギー分野におけるナノテク・材料の可能性 - 水の利用 - 」
講演仮タイトル:「純粋科学研究としてのPFAS問題とその解決方法 - PFAS対策技術コンソーシアムからの提言」
俯瞰ワークショップ、過去の報告書リスト https://www.jst.go.jp/crds/report/by-report/05/index.html
更新日:令和6年3月8日
イベント情報 「4月18日開催の依頼講演のお知らせ」
★「PFASの評価に必要な分析技術 Webセミナー(2024年4月18日開催)での依頼講演」
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社の依頼により「PFASの評価に必要な分析技術 Webセミナー(2024年4月18日開催)」で、
当コンソーシアムの谷保が下記講演を行います。
講演タイトル:「PFASの包括的な評価のための測定技術の開発」
開催日: 2024年4月18日(木) 開催方式 オンライン(ON24)
申し込みは下記
こちらをクリック
講演概要
ペル及びポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、フルオロメチル基やフルオロメチレン基などを有する様々な有機フッ素化合物 の総称で、一部のPFASは難分解性で環境残留性などが懸念・指 摘されています。また、環境中で分解してより残留性の高いPFAS に構造変換するPFASもあります。このように、PFASは様々な物 理化学性を有することから、単一の方法で測定し評価することが 困難です。本セミナーでは、一般的に使用されるLC-MS/MSを用 いた測定の他、GC-Orbitrap-HRMSや燃焼イオンクロマトグラフ (CIC)などを用いたPFASを対象とした様々な測定手法につい て紹介します。
# コンソーシアムデータベースの下記を事前に参照いただくと理解の助けとなります。
A-27.「総PFAS測定と欧州ECHA規制案に関して (2023年12月1日)」 (2023年10月、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、NILU、 Vladimir Nikiforov博士)
英語文献68. Huiju Lin, Sachi Taniyasu, Eriko Yamazaki, Rongben Wu, Paul K.S. Lam, Heesoo Eun, Nobuyoshi Yamashita, Fluorine Mass Balance Analysis and Per- and Polyfluoroalkyl Substances in the Atmosphere. Journal of Hazardous Materials, 2022. こちらをクリック
日本語文献9.「GC-Orbitrap-HRMSを用いた日本及び中国環境大気中の揮発性ペル及びポリフルオロアルキル化合物分析法の開発」谷保佐知、山﨑絵理子、羽成修康、
山本五秋、山下信義、分析化学、Vol.72, No.7-8, pp.307-316 (2023)
更新日:令和6年3月1日
イベント情報 「3月18日開催の依頼講演のお知らせ」
★第62回環境化学講演会「PFAS分析技術に関する講演会」で、当コンソーシアムの谷保が下記講演を行います。
こちらをクリック
講演タイトル:「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)測定技術の最新動向と将来展望」
開催日:2024年3月18日(月)14:00~16:45
お申し込み:こちらをクリック
講演概要
ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)は、様々な物理的・化学的性質を有する幅広い化学物質の総称として用いられている。PFASを対象とした環境課題や化学物質規制は、対象となる化学物質が多岐にわたるため、限定した測定方法や対策で対応することが困難である。ここでは、現行のPFASの測定技術と、今後の研究や技術開発の課題に焦点を当てて紹介する。
更新日:令和6年3月1日
お知らせ 「データベースおよび会員限定ページの更新予定」
★データベースにPFAS対策技術コンソーシアムが参加する国際情報交換データベースの中で、比較的平易な英語で信頼できるポータルを2件追加しました。
各国のPFAS対応なども一目でわかる情報源となっています。
D.その他の情報
D-4 (PFAS対策技術コンソーシアムが参加する国際情報交換データベース-1)
・OECD Portal on Per and Poly Fluorinated Chemicals
こちらをクリック
・各国のPFAS対策(リスク低減と代替物質開発)情報
こちらをクリック
D-5 (PFAS対策技術コンソーシアムが参加する国際情報交換データベース-2)
・PFAS Central
(Green Science Policy Institute/Social Science Environmental Health Research Institute at Northeastern Universityを中心としたポータル)
こちらをクリック
★また、4月以降の予定で会員限定ページに下記を公開する予定です。(著作権確認に時間を要するため、引き続き会員有志のご協力を募集します。)
講演動画
12. 「SWATH-F: A Novel Nontarget Strategy Based on the SWATH-MS Deconvolution Method Assist in Annotating PFAS Homologs(分子ネットワークモデルと機械学習を応用した全てのフッ素化合物の人工知能網羅分析技術 : SWATH-F:)」(2023年10月17日、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、南京大学 Laihui Li 博士、会員有志による和訳版)近日公開予定
11. 「Legacy and Emerging PFASs from Eight Main Outlets of the Pearl River Delta, China: Phase Distribution, Temporal Variation, and Environmental Stress.(中国Pearl River Deltaの河口8地域における多様なPFASの動態・分布・環境ストレスについて)」(2023年10月17日、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、香港城市大学 Qi Wang 博士、会員有志による和訳版)近日公開予定
10. 「Atmospheric concentrations of particle and gas phase per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in Japan(大気中ガス・粒子中PFASの全国調査結果)」(2023年10月19日、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、大阪市立環境研究センター 浅川大地 博士、会員有志による和訳版)近日公開予定
9. 「Twenty-three years of collaboration between CityU and AIST on PFAS research in China and Japan.(香港城市大学と産総研との共同研究の23年、中国と日本のPFAS研究の歴史)」(2023年10月18日、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、香港都市大学 Paul KS Lam 教授、会員有志による和訳版)近日公開予定
8.「PFAS analytics and their relation to PFAS remediation(PFAS分析技術と環境修復技術の連携について)」(2023年10月18日、PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会、ドイツBAM Christian Vogel 博士、会員有志による和訳版)近日公開予定
会員限定公開資料
7.「総PFAS測定法マニュアル、EOF編」近日公開予定
6.「欧州PFAS対策技術現地見学会事前調査(2024年2月)報告」近日公開予定
5.「総PFAS測定法マニュアル、TOP Assay編」4月公開予定
更新日:令和6年2月14日
イベント情報 「3月19日開催の依頼講演のお知らせ」
★「産学連携学会九州支部セミナー(2024年3月19日開催)での依頼講演」
「熊本創生推進機構」の依頼により「産学連携学会九州支部主催セミナー(2024年3月19日開催)」として、当コンソーシアムの谷保が講演を行う予定です。
視聴のみ一般も可能、意見交換会は学会会員のみになります。セミナー詳細は下記、主催元にお問い合わせください。
講演タイトル:「ペルおよびポリフルオロアルキル化合物(PFAS)の環境研究の動向 ~分析方法を中心に~」
こちらをクリック
更新日:令和6年2月5日
お知らせ 1月22日に予定している「総PFAS」測定技術オンライン配信に合わせて「総PFAS測定技術見学会」と「TOP assayを用いたテスト試料中総PFAS依頼分析」を予定します。
基本的にコンソーシアム会員対象ですが、依頼内容によっては会員外のお申し込みも受けつけますので、ご希望者は事務局までお問い合わせください。★「総PFAS測定技術見学会」
1月18, 19, 23日のうち1日(希望者の多い日を選定)
参加申し込み:コンソーシアム事務局まで、参加希望日、人数、担当者氏名/所属/連絡先をお知らせください。
★「TOP assayを用いたテスト試料中総PFAS依頼分析」
希望者より提供いただいた分析試料について、TOP assay等を用いた「総PFAS測定」を行います。
測定結果は、Anonymous提供試料(提供元は秘匿)として、試料の種類のみ記載した論文公表を予定しておりますので、同意いただける方のみお申し込みください。
必要試料は、固体(十分小さく破砕し均一化された試料(5 g程度で試料代表性があること)、総量50 g程度)または液体(100 - 250 mL、PPボトルに密栓)となります。
※試料受入れに関して、さらなる情報をいただく可能性もございます。
参加申し込み:コンソーシアム事務局まで、試料の種類/性状、数、担当者氏名/所属/連絡先をお知らせください。
更新日:令和5年12月12日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会エキスパート講演要約版」1件を一般データベースに、会員限定データベースに2件を公開しました。
「総PFAS測定と欧州ECHA規制案に関して」については、Vladimir Nikiforov博士の講演の抜粋に、問い合わせの多い「総PFAS測定技術」と「ECHA規制案」との関係について追記しています。この二件については国内では正しい情報が少ないため、情報整理に役立てて頂ければ幸いです。また、その他のエキスパート講演の要約も事務局で準備中ですが、時間を要するため、会員有志による「勉強会」での要約作成も検討します。「勉強会」内で講演資料を共有しますので、参加いただける会員様には事務局までご連絡いただければ幸いです。
更新日:令和5年12月1日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会の概要報告」をデータベースに公開しました。
こちらをクリック
2023年10月17-19日に開催した「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会」の概要報告をデータベースに公開しました。
後日、重要な講演のみ日本語訳を会員限定ページに追加予定です。
更新日:令和5年11月13日
お知らせ 「環境研究総合推進費(1G-2102)『ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発』が環境省の行政推薦事業に認定」
環境研究総合推進費(1G-2102)「ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発」が環境省の行政推薦事業に認定されました。統合領域採択研究が環境省推進事業に認定されるのは初めての例ですが、これにより本事業で得られた多数の研究成果の社会実装加速が期待できます。
特に、中間評価S評価に甘んずることなく、成果の期待できない研究項目は縮小、得られた研究成果の社会普及を加速できるメンバーに刷新しました。現在の研究参画機関は代表機関以外に大阪市立環境科学研究センター、株式会社竹中工務店、株式会社東京久栄、株式会社環境総合リサーチ、フタムラ化学株式会社となりますが、30種類のPFASの一斉分析が可能な国際標準分析規格であるISO21675に最適化した国内初のPFAS吸着剤を開発しているソニーグループ株式会社など、「PFAS対策技術コンソーシアム」会員の積極的参加も大きく貢献しており、本事業終了後の波及効果の拡大が期待できます。
更新日:令和5年10月31日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (2023年10月17-19日開催)」一般参加について
「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (2023年10月17-19日開催)」について、地方自治体PFAS担当などからのお申し込みが多数のため100人規模の会場に変更しましたので、 一般のオンサイト参加枠を少し追加しました。一般参加ご希望の方は10月11日(水曜日)中に下記情報を事務局までメールでお知らせください。
早期に枠が埋まる可能性もありますが、参加可能な方は12日(木曜日)に入館方法をお知らせします。事前登録以外の方の入館はできません。
12日中に連絡の届かない方はオンサイト参加はできませんが、今回に限りコンソーシアム入会申し込み書を10月13日(金曜日)17時までに事務局にご提出いただいた方は会員枠でのオンライン参加を可能とします。
・申し込みに必要な情報 :希望日(特定日だけでも可)・氏名・所属・緊急時連絡先電話番号
・追加一般参加(オンサイト)締め切り :10月11日
・オンサイト参加可否連絡 :10月12日
・オンライン参加可能なコンソーシアム入会申し込み締め切り :10月13日
講演プログラムはこちら
更新日:令和5年10月6日
お知らせ 「アンケートについて」
★コンソーシアム会員のご要望により、二件のアンケートを掲載しました。会員外のアンケートも受け付けますので皆様のご意見をお寄せください。
1. ソニーグループ製多孔質カーボン素材を用いたPFAS対策製品開発についてのアンケート
2. PFAS分析技術についてのアンケート
アンケート提出先 : PFAS対策技術コンソーシアム事務局 『 m-pfas_consortium-ml"at"aist.go.jp(ご連絡の際は”at”を@に直してから送信してください。)』 まで、メールでお送りください。
特に締め切りは設けませんが、次回の打ち合わせ会議で集計する予定です。
更新日:令和5年9月22日
お知らせ 「『総PFAS』測定技術のオンサイト講習について」
★「総PFAS」測定技術のオンサイト講習を年度内(12月から2月予定)に予定します。
ポッドキャスト配信中の「マスバランス解析技術」の具体例として、同技術の専門家であるスウェーデン、オレブロ大学のYeung博士を産総研に招き、 総酸化法(TOP Assay)、抽出態有機フッ素(EOF)及び燃焼イオンクロマトグラフを用いたマスバランス解析技術のオンサイト講習を予定します。
日程決定から研修までかなりタイトなスケジュールとなりますので、参加ご希望の方は事務局まで早めにお申し込みください。
最大10人限定のPFAS専門家研修(コンソーシアム会員団体でPFAS分析経験のある方が対象です)となります。
申し込みには「PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続きについて」をご確認ください。
更新日:令和5年9月5日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアム会長挨拶、『PFAS対策技術コンソーシアム』三年目を迎えて、の追加とポッドキャスト配信開始のお知らせ」
★PFAS対策技術コンソーシアム設立より三年目を迎えましたが、先の会員アンケートの結果、設置期間延長が決まりましたので、 活動の現状と今後の予定について、会長挨拶をトップページに追加しました。
★6月26日会員向け講演会及び打ち合わせ会議で予告しましたボッドキャスト配信がスタートしました。
海外では大学の一般教養講座でも使われているポッドキャストを用いてPFAS対策技術情報を一般に啓蒙することで、PFAS問題解決のための正しい知識を世界に普及します。
第一回の配信は、欧米では「総PFAS」の測定技術としてUSEPAも含め広く使われている「マスバランス解析技術」についての紹介です。
下記タイトルでSpotify, Apple iTunes, Google Podcasts, Amazon Music他、様々なポッドキャスト配信ソースを検索していただければ無料で聴講できます。
ポッドキャストタイトル
「Mass Balance Analysis as a tool for investigating fluorine-based chemical pollutants」
オリジナルの配信は下記から聴講可能です。
こちらをクリック
更新日:令和5年8月8日
イベント情報 「ダイオキシン国際会議での研究発表のお知らせ」
★9月10日よりオランダで開催されるダイオキシン国際会議において、コンソーシアム関係者より下記の研究発表を行います。
特に農業環境中PFAS対策については現地で関係者ブースも予定していますので、皆様お立ち寄りください。
1. Sachi Taniyasu et al., GC-Orbitrap-HRMS Method for the Accurate Analysis of Volatile Per- and Polyfluoroalkyl Substances in Ambient Air from Japan and China (GC-Orbitrap-MRMSを用いた36種類の揮発性PFASの一斉分析技術の開発、日本および中国大気について)
2. Eriko Yamazaki et al., The seventy-nine footprints of PFAS pollution in India - Nationwide distribution in road dust (ロードダスト中PFASのインド全域調査、全国行脚79の足跡)
3. Eriko Yamazaki et al., Estimation of PFAS flux in paddy field during rice cultivation - A case study using Indica and Japonica rice (稲作環境におけるPFASフラックス、インディカ米とコシヒカリについて)
4. Daichi Asakawa et al., Atmospheric concentrations and phase distributions of ionic per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in five regions of Japan (イオン性PFASの国内大気中ガス・粒子中濃度の比較)
5. Toshiki Tojo et al. Survey of neutral PFASs in air using FM4 air sampler in five regions of Japan (FM4大気サンプラーを用いた国内大気中の中性PFASの調査)
更新日:令和5年8月1日
イベント情報 「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (2023年10月17-19日開催予定)」をアップデート
★「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (2023年10月17-19日開催予定)」をアップデートしました。
会議パンフレットはこちら
「国内PFAS研究の失われた15年を取り戻し日本発PFAS対策新技術を国際普及することは可能か?」
20名の海外著名専門家(15名前後来日予定)によるPFAS最新情報講演
開催日時 : 10月17,18,19日(一日7名程度の講演、三日間別々の講演となります)
開催場所 : ソニーシティ品川(東京都港区港南1-7-1)
定 員 : 50名 (会場規模で変更)
コンソーシアム会員のみ、現地参加とオンライン参加どちらも可能です。
講演会参加は無料ですが、一般参加は一日10名限定、事前登録現地参加のみです。
現時点の講演予定は下記になります。
ほとんどの講演は英語で行われますが、Teams自動文字起こしの発表原稿はコンソーシアム会員のみ、必要に応じて提供予定です。
特に重要な講演については後日、コンソーシアム会員向けに日本語に翻訳し再配信予定です。
会議情報は随時アップデートしますのでKeep in touch !!
講演リスト (講演者の都合により変更する場合があります)
1. 国連環境計画におけるPFAS対策立案
2. PFAS対策に関するストックホルム条約ガイドライン
3. Le Monde France, PFAS報道の真実
4. PFAS吸着活性炭の再処理技術 – ベルギー再処理施設を中心とした欧州リサイクル
5. 3M (ベルギー) におけるPFAS環境汚染と対策技術
6. アメリカにおける軍用地での泡消火剤汚染と環境修復技術の現状
7. 香港城市大学と産総研の国際共同研究の23年 – 中国と日本のPFAS研究の歴史
8. “PFAS-AI” 世界最強の人工知能網羅分析技術を用いた全ての潜在的PFAS分析 – Suspect screening からPrediction analysisへ
9. “SWATH-F” 全てのフッ素化合物の網羅分析技術は可能か?
10. 光化学反応による未知のPFASの発見
11. LIFE SOuRCE – PFAS地下水汚染環境修復技術開発 - 欧州における産官学連携国際プロジェクト
12. PFASの潜在的生物分解技術について
13. ロードダスト中PFASのインド全域調査と幼児への健康影響評価 – 全国行脚79の足跡 (英語文献70)
14. 稲作環境におけるPFAS汚染と人暴露影響評価、インディカ米とコシヒカリの比較(英語文献68, 69)
15. PFAS バルク分析技術の最新情報 - TOP assay、抽出態有機フッ素(EOF)等、マスバランス解析技術の国際標準化
16. PFAS 環境修復用新材料開発 – 特に農業環境について
17. PFASフリー農業の提案 – 耕作すればするほどPFASが減少する農業とは
18. 中国におけるPFASのマルチメディア分析
その他アップデート予定
更新日:令和5年7月21日
イベント情報 「International Symposium on Pollution Control of Perfluoroalkyl Substances(2023年10月20-22日開催)における招待講演のお知らせ」
★中国、天津で10月20-22日に開催される上記国際会議で、当コンソーシアムの山下が国際ボードメンバーとして参加、同時に招待講演を行う予定です。
詳細は下記となります。
・講演タイトル(予定)
「PFAS対策の地政学的問題、米国・欧州・中国のどれから日本は学ぶべきか」こちらをクリック
更新日:令和5年7月7日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアム会員限定データベースの更新について」
会員限定データベースを下記のように更新しました。
特に、一般公開していた下記について会員限定データベースに移動しました。
A-23.「PFAS環境修復技術関連の主要文献リスト」( 2022年まで, PFAS対策技術コンソーシアム版) (会員の要請により2023年2月20日公開)
A-25.「PFAS分解技術関連の主要文献リスト」( 2023年4月まで, PFAS対策技術コンソーシアム版) (会員の要請により2023年5月30日公開)
今後は「一般公開データベース」よりも「会員限定データベース」の充実を中心にする予定です。
2023年7月時点の会員限定データベース内容
・会員限定公開動画
1.「0.004 ng/LのPFAS測定を可能にするための精度管理技術とは?」
2. 基調講演「ストックホルム条約最新情報について」Global management of listed POP-PFASs in the Stockholm Convention and some related research needs
3. 基調講演「PFAS研究の過去・現在・未来」An update on legacy and emerging perfluoroalkyl substances(PFASs)_2
4. ISO21675他実演動画 (燃焼イオンクロマトグラフ, 土壌試料の分析方法の例, 結果の解析, 機器分析, 固相抽出, 器具洗浄)
その他3件準備中
・会員限定公開資料
1.「PFAS分解技術関連の主要文献リスト」(2023年4月まで, PFAS対策技術コンソーシアム版) (会員の要請により2023年5月30日公開)
2.「PFAS環境修復技術関連の主要文献リスト」(2022年まで, PFAS対策技術コンソーシアム版) (会員の要請により2023年2月20日公開)
3. ISO21675技術研修マニュアル (ISO21675他実演動画とあわせて視聴をお勧めします)
更新日:令和5年7月7日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアムデータベースの更新について」
PFAS対策技術コンソーシアムデータベースに、閲覧可能な一般公開用資料として下記を追加しました。神奈川大学 堀久男 教授よりご提供いただきました。
A-26. 「フッ素樹脂のリサイクルや廃棄物処理、環境影響に関する総説(英国王立化学会(RSC)発行)」(神奈川大学 堀久男 教授よりご提供「神奈川大学ホームページのNewsへのリンク」)
また、先に行いましたメーカー分科会でも、産官学と中立の立場で、特に残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約や欧州ECHAなどにも科学的知見を提供できる
「PFAS対策技術コンソーシアム」は、高度に独自性が高い組織であり、今後の人工フッ素化合物問題解決のために、ぜひ活動を続けてほしいとのご意見をいただきました。
継続の形式については今年度中に検討する予定ですが、今後は本コンソーシアムが提供する「客観的に信頼性が確認された一次情報」の拡充と、
会員団体のPFAS関連情報をコンソーシアムデータベースに集約することで「適切なPFAS対策技術を国民の目に見える形で共有する」ことを目的とします。
内容については事務局で精査させていただきますが、会員外からの情報提供も歓迎します。
更新日:令和5年6月16日
イベント情報 「ISO 21675他に関する技術研修/技術コンサルタント募集について」
5月19日に公開しました「PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続きについて」に関する反響が大きいため、
人数限定で「ISO 21675他に関する技術研修/技術コンサルタント」を募集します。日程は下記となります。なお、次回の募集は未定です。
募集締め切り:6月23日(金曜日)
事前に「PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続きについて」をご熟読いただき、研修内容について事務局と十分に打ち合わせをお願いします。
研修内容は5-Aから5-Kまで、具体的にどのレベルを希望するかを決めていただき、下記例を参考にお申込みください。
なお、5-Aと5-I以外は有料になります。
例:「LCMSMS使用経験のある技術者2名について、5-C及び5-Dの研修を希望します」
受け入れ開始:8月以降
*受け入れ人数が限られるため、受け入れ日程の変更をお願いする場合がございますので、誠に恐れ入りますがご了承のほどお願いいたします。
更新日:令和5年6月6日
イベント情報 「6月26日会員向け講演会のお知らせ」
講演日時: 6月26日(月曜日)13:00-15:30 Microsoft Teams
6月の会員向け講演会では下記三件の講演と一件の技術紹介を予定しております。
★「土壌中PFAS除去技術実証試験中間報告」
下記参考
・お知らせ(更新年月日:令和5年3月28日) 「土壌中PFAS除去技術実証試験の結果について」
・イベント情報(更新年月日:令和4年7月26日)「土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)のお知らせ」
★「ロードダスト中PFASのインド全域調査と幼児への健康影響評価 – 全国行脚79の足跡」(インド科学技術研究所ISTAR、英語の講演を適宜日本語訳して配信します)
データベース・英語文献 70
★「稲作環境におけるPFAS汚染と人暴露影響評価、インディカ米とコシヒカリの比較」(産総研他)
データベース・英語文献 69
★「技術紹介 ISO 21675を用いたPFAS分析受託事業について」(技術研修参加機関)
国内機関で一般に使われているPFAS測定技術の信頼性が懸念されているため、39種類のPFAS一斉分析法の国際標準分析規格であるISO 21675の国内機関導入が急速に進められています。現在、4機関の技術研修(データベース6. PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続きについてを参照)と合わせて、環境研究総合推進費「ペルフルオロアルキル
化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発」(中間評価S評価)において、地方自治体研究所の半数近くにISO 21675を導入中です。
これらの活動により、ISO 21675をベースとした土壌中PFAS分析技術の標準化と併せ、国内汚染状況の正確な理解と適切な対策立案が期待できます。
更新日:令和5年6月5日
お知らせ 「PFAS分解技術関連の主要文献リスト」をデータベースに追加しました。
「PFAS分解技術関連の主要文献リスト」をデータベースに追加しました。A-23「PFAS環境修復技術関連の主要文献リスト」と合わせることで、国外で実用化されているPFAS処理・分解技術が把握できると思います。翻訳AIなどを用いれば、一般の方でも容易に「信頼性の高い一次情報」の取得が可能となります。国内では「客観的に信頼性が確認されていないPFAS測定値」や「間違った二次情報」の流布が多いため、ご自身で「信頼性の高い一次情報」の確認をお勧めします。
特に、PFAS対策技術コンソーシアム会員向けには、データベースのA-21「PFAS含有泡消火剤環境修復技術のまとめ (抜粋版)」と同様に、関連技術の理解を助ける要約の公開を予定しています。
また、2023年10月17-19日に予定している、「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会」でも、関連する専門家に最新の情報をご提供いただきますので、事前に基礎となる文献情報の閲覧をお勧めします。
更新日:令和5年5月30日
イベント情報 「8月4日開催の依頼公演のお知らせ」
★「結果の妥当性を確保できるラボラトリであり続けるために-2023-(2023年8月4日開催)での依頼講演」
セントラル科学貿易・シグマ アルドリッチ ジャパン・サイエックス共催無料セミナー(2023年8月4日開催)で当コンソーシアムの谷保が招待講演を行う予定です。
詳細は下記となります。
・講演タイトル(予定)
「水試料中のペルおよびポリフルオロアルキル化合物を測定するための精度管理要件」 こちらをクリック
更新日:令和5年5月23日
お知らせ 「PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続きについて」
最近問い合わせの多い「PFAS対策技術コンソーシアムへの依頼手続き」についてトップページに追加しました。
特に、30種類のPFAS一斉分析技術である、国際標準分析法ISO 21675を用いることで、信頼性の低い民間分析データによる社会不安の防止・多様なPFAS環境修復技術の有効性評価が可能となります。ただし、標準規格文書通りの分析精度を得るためには、PFAS分析化学について十分な知識と技術習得が必要です。技術習得に必要な技術研修は、会員に限らず申し込みできますので是非ご検討ください。現時点で、産総研の監修によりISO 21675技術研修をクリアしている国内機関は2機関しかありません。
更新日:令和5年5月19日
お知らせ 「ISO 21675技術研修による事業化について」
現在国内で一般に使われている分析技術では数種類のPFAS成分しか測定できないため、発生源推定に必要な十分な情報が得られないことが懸念されていますが、客観的に信頼性の確保された国際標準分析規格であるISO 21675を用いることで最高39種類のPFAS多成分分析が可能となり、マスバランス解析技術を併用することで多くの環境試料中PFASの発生源特定が実現可能となります。
この度、産総研技術研修制度を用いISO 21675を用いたPFAS分析技術の事業化が開始されました。
ISO 21675を用いた事業化は下記企業が国内最初の例となります。
コンソーシアム会員にかかわらず、同様な技術研修をご希望の団体様は事務局までご連絡ください (相談は無料です)。
株式会社 東京久栄 こちらをクリック
更新日:令和5年4月21日
イベント情報
★「PFAS対策技術コンソーシアム国際講演会 (2023年10月17-19日開催予定)」
現在まで三回行ったPFAS対策技術コンソーシアム国際講演会の内容は抜粋して会員向けに配信しておりますが、四回目となる今回は10名近い国外エキスパートを招聘し、可能な限りface to faceの議論をしていただく予定です。一日はフルタイムの講演会、一日はコンソーシアム分科会ごとに会員ニーズに応じた相談会を行う予定です。
特に、世界で最も進んだ中国PFAS研究の専門家、国際連合(UN)のPFAS国際施策立案(inter-governmental policy making)者、欧州のPFAS対策技術をリードする専門家他にご講演いただきます。
現時点の講演予定は下記となりますが、変更となる場合もあります。
1. 国連環境計画におけるPFAS対策立案(Müller Grabher氏 オーストリア環境省)
2. PFAS対策に関するストックホルム条約ガイドライン(Roland Weber博士 他)
3. 香港城市大学と産総研の国際共同研究の23年 – 中国と日本のPFAS研究の歴史(Paul KS Lam博士 元 香港城市大学副理事長)
4. “PFAS-AI” 世界最強の人工知能網羅分析技術を用いた全ての潜在的PFAS分析(Wei Si博士 南京大学)
5. LIFE SOuRCE – PFAS地下水汚染環境修復技術開発 - 欧州における産官学連携国際プロジェクト(Lutz Ahrens博士 スウェーデン農業科学大学)
6. PFASの潜在的生物分解技術について(スウェーデン農業科学大学)
7. ロードダスト中PFASのインド全域調査と幼児への健康影響評価 – 全国行脚79の足跡(インド科学技術研究所ISTAR)
8. 稲作環境におけるPFAS汚染と人暴露影響評価、インディカ米とコシヒカリの比較(産総研他、参考文献Environ. Sci. Technol., 2023) こちらをクリック
9. PFAS バルク分析技術の最新情報 - TOP assay、抽出態有機フッ素(EOF)等、マスバランス解析技術の国際標準化(Leo Yeung博士 オレブロ大学)
10. PFAS 環境修復用新材料開発 – 特に農業環境について(産総研他)
11. その他
*会員向けの国際講演会ですが、後日一部を抜粋して一般向けの配信を予定しております。
★「土壌物理学会大会シンポジウム(2023年10月21日開催)での招待講演」
2023年度土壌物理学会大会シンポジウム(2023年10月21日開催)で当コンソーシアムの山下が招待講演を行う予定です。
詳細は下記となります。
・講演タイトル(予定)
「ペルフルオロアルキル化合物(PFAS)による環境汚染と環境修復技術について – なぜ国内では実用化されないのか」 こちらをクリック
更新日:令和5年4月21日
イベント情報 「国際ワークショップ(2023年9月19日開催)での招待講演のお知らせ」
ドイツBAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) 主催の国際会議(2023年9月19日開催)で当コンソーシアムの山下が招待講演を行う予定です。
詳細は下記となります。
・講演タイトル(予定)
The first mass balance analysis of PFAS in air - Why no reliable information of PFAS in air to date?
(世界初の大気中PFASマスバランス解析 - 大気中のPFASについて信頼できる報告が無いのは何故か? )
Advancements of Analytical Techniques for Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) – Second Workshop 2023
こちらをクリック
更新日:令和5年4月11日
日本環境化学会2023年度学会賞受賞のお知らせ
3月24日に発表された日本環境化学会2023年度学会賞において、第30回環境化学論文賞を共著者として受賞しました。
学会賞のホームページはこちらのリンクからご覧いただけます→一般社団法人日本環境化学会こちらをクリック
第30回環境化学論文賞
論文著者:Heesoo EUN, Kodai SHIMAMURA, Takuya ASANO, Eriko YAMAZAKI, Sachi TANIYASU, Nobuyoshi YAMASHITA
論文タイトル:Removal of perfluoroalkyl substances from water by activated carbons: Adsorption of perfluorooctane sulfonate and perfluorooctanoic acid
更新日:令和5年4月10日
お知らせ
★「PFAS対策技術コンソーシアム分科会のお知らせ」
PFAS対策技術コンソーシアムは、産業界、研究機関、政府所管が一堂に会する、産学官の情報交換の場であり、従来の勉強会よりも大きな波及効果が期待できます。その一方で、全員が会する場では、発言を控える傾向があるため、会員の種類に応じた分科会の開催について、一部の会員様よりご提案がありました。
このため、今後、会員様のご要望により臨時分科会を行うこととします。 発起会員のご要望により賛同会員を募集し、特定の会員ニーズに役立つ専門家会議などを予定しますので、積極的なご提案を事務局までお知らせください。既に二件の分科会を検討中です。
★「欧州PFAS研究組織との国際マッチングについて」
この度、PFAS対策技術コンソーシアム会員団体と欧州PFAS研究組織(オレブロ大学、スウェーデン地質調査所他)との国際マッチングに成功(現在、欧州側プロジェクト申請中)しました。これにより、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に非常に近い、欧州のPFAS専門家に当該コンソーシアム会員団体が開発したPFAS関連技術について評価してもらう事が可能になります。
日本発の新技術が欧州で採用されれば「国内PFAS研究の失われた15年」を取り戻す近道ですので、自社技術の世界展開等をお考えの会員様は「国際マッチング希望」と事務局までお知らせください。ヒアリング後、適した専門家を紹介させていただきます。
★「土壌中PFAS除去技術実証試験の結果について」
昨年10月に行った「土壌中PFAS除去技術実証試験」は無事終了し、参加機関においてISO 21675を用いた測定を行っていただいております。その中間結果から、日本の土壌においても「PFAS吸着剤土壌注入技術」によってPFAS漏洩を防止できることが判明しました。さらに、会員サービスとして行った「23種類のPFAS吸着剤性能評価試験」から、ISO/TC147/WG33/WD
18127にも使用可能なフッ素ブランクの低いPFAS吸着剤も特定できました。詳細については試験参加機関の承諾が得られる形でPFAS対策技術コンソーシアム内での共有を検討しております。
また、データベースとして公開している、さらに先進的なPFAS対策技術についても、会員ニーズに応じて技術移転が可能ですので、事務局までお知らせください。
加えて、6月以降に予定する「TOP assay・ISO/TC147/WG33/WD 18127等、マスバランス解析技術実習と国外専門家招へい」等、「PFAS対策技術コンソーシアム発の新技術」の実用化、国際普及について会員の皆様の積極的なご参加を頂ければ幸いです。
更新日:令和5年3月28日
イベント情報 「3月9日会員向け講演会のお知らせ」
講演日時: 3月9日(木曜日)13:00-15:30 Microsoft Teams
3月の会員向け講演会では下記三件を予定しております。
★「0.004ng/LのPFAS測定を可能にするための精度管理技術とは ?」
産総研では2004年の時点でPFOS, PFOAの高感度測定(それぞれ検出限界0.0008ng/L、0.005ng/L)を実現しており、最新技術ではPFOAの常用測定感度は0.002ng/Lで測定している。超高感度測定を実現するためにどのような精度管理技術が必要かを説明する。
参考文献
・ペルフルオロアルキル化合物の国際標準規格と今後の展望 (谷保ほか、環境技術、51(5)、2022)
・外洋海水中ペルフルオロ化合物微量分析のための固相抽出法の開発 (山﨑ほか、分析化学、64(10)、2015)
・Analysis of perfluorinated acids at parts-per-quadrillion levels in seawater
using liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Environ. Sci. Technol.
2004. 38(21): p. 5522-5528.
★「PFAS標準物質の現状」
正確な分析値を得るためには、校正用標準物質と組成標準物質の併用が望ましいが、PFASは対象物質数が多く、利用できる標準物質数が限られている。国家計量標準機関である産総研計量標準総合センターでは幾つかのPFAS標準物質を世界に先駆けて開発してきたので、その紹介及び他国を含めたPFAS標準物質の現状について説明する。
参考文献
・Development of a certified reference material for the determination of
perfluorooctanoic acid (Hanari et al., Accred. Qual. Assur. 2014, 19, 391-396)
・Certified calibration solution reference material for the determination
of perfluorooctane sulfonate from the National Metrology Institute of Japan
(NMIJ) (Hanari et al., Intern. J. Environ. Anal. Chem. 2013, 93, 692-705)
★「PFASの人工知能網羅分析技術とは ?」
環境研究総合推進費S評価の理由でもある、世界最先端の中国人工知能技術(予測解析、自己進化型ライブラリー他)と、産総研が世界をリードするISO国際標準規格の融合により実現した「PFASの人工知能網羅分析技術」について、基本的な考え方や、現在公表可能な成果について説明する。
参考文献
・Nontarget discovery of per- and polyfluoroalkyl substances in atmospheric
particulate matter and gaseous phase using cryogenic air sampler (Yu et
al., Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 6, 3103–3113)
・Suspect and nontarget screening of per- and polyfluoroalkyl substances
in wastewater from a fluorochemical manufacturing park (Wang et al., Environ.
Sci. Technol. 2018, 52, 19, 11007–11016)
更新日:令和5年2月6日
会長よりの新年のあいさつと会員向け講演会のお知らせ
PFAS対策技術コンソーシアム会員の皆様旧年中はご愛顧をいただき感謝申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。
2021年6月に設立されました「PFAS対策技術コンソーシアム」は現在参加団体数28、会員数60名(手続中も含む)となり、PFASにかかわる産・学・官の情報交換の場として大きな成果をあげつつあります。特に、過去の有害化学物質問題の失敗を繰り返さないように、計測・処理技術に特化したコンソーシアムとして、国外の優れた技術の紹介・国内企業への技術移転を中心に活動を行っております。2023年度は当初予定の最終年度ですが、会員のニーズに応じて更新する可能性もございます。更新しない場合でも会員向けデータベースは何らかの形で残す予定にしておりますので、入会を前向きにご検討いただければ幸いです。
現在まで「PFASの安全処理技術」を国内普及させることで「不用意な社会不安」を抑止できるだけではなく、「最新のPFAS計測技術」を用いることで、泡消火剤/温暖化ガス問題等の陰に隠されている、全ての人工フッ素化合物の環境内運命の科学的理解につながる産・学・官連携チームもコンソーシアム内に自然発生しつつあります。「いわゆる専門家」に惑わされず、ご自分の目と耳でコンソーシアムデータベースをご覧になることで、無理のないPFAS対策の立案と実行が可能になると考えております。ご意見・ご質問などございましたら、ご遠慮なくコンソーシアム事務局までお知らせくださいますようお願い申し上げます。
PFAS対策技術コンソーシアム 会長
---------------------------------------------------------------
3月の会員向け講演会では下記二件を予定しております。
---------------------------------------------------------------
★「0.004ng/LのPFAS測定を可能にするための精度管理技術とは ?」
参考文献
・ペルフルオロアルキル化合物の国際標準規格と今後の展望 (谷保ほか、環境技術、51(5)、2022)
・外洋海水中ペルフルオロ化合物微量分析のための固相抽出法の開発 (山﨑ほか、分析化学、64(10)、2015)
★「PFASの人工知能網羅分析技術とは ?」
参考文献
・Nontarget discovery of per- and polyfluoroalkyl substances in atmospheric particulate matter and gaseous phase using cryogenic air sampler (Yu et al., Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 6, 3103–3113)
・Suspect and nontarget screening of per- and polyfluoroalkyl substances in wastewater from a fluorochemical manufacturing park (Wang et al., Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 19, 11007–11016)
更新日:令和5年1月6日
Leo W.Y. Yeung博士来日公演(12月27日)のお知らせ
PFAS対策技術コンソーシアムスーパーバイザーの一人であるLeo W.Y. Yeung博士 (ダイオキシン国際会議でOtto Hutzinger Student Awardを受賞) の来日公演を下記の日程で行います。講演日時: 12月27日(火曜日)13:00-15:00 Microsoft Teams イベント
講演タイトル:「PFAS多成分分析の最新技術 – 網羅分析、マスバランス解析、ISO国際標準規格」(発表は英語のみですが、要旨のみ翻訳を行う予定です)
講演者:Leo W.Y. Yeung博士(オレブロ大学 及び 産総研)
今回の特別講演会は「どなたでも」視聴できますので、下記よりご参加ください。
「PFAS対策技術コンソーシアム特別講演会(12月27日)」
(こちらをクリック)
更新日:令和4年12月12日
募集情報(申込締め切り日:令和4年11月17日)「土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)、追加募集のお知らせ」
令和4年7月26日更新のイベント情報「土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)のお知らせ」で募集した実証試験について、多数のお申し込みをいただきました。一旦締め切りましたが、試験場所に余裕が出たため、数件の参加者枠が空きましたので、下記について追加募集をさせていただきます。
詳細は令和4年7月26日更新のイベント情報をご参照ください。今年度の募集は今回で最後となります。
追加の参加形態(下記以外の募集はありません)
・建設会社等 (現場作業に必要な技術者派遣2, 3人 x 3日間)
・分析機関等 (処理前後の土壌試料・浸出水・灌漑水の分析、試料数10-30程度) *事前にISO 21675の実習が可能です
申込締め切り 11月17日 木曜日
・産総研の担当研究者
環境創生研究部門 谷保佐知
・問い合わせ先
M-PFAS-EMRI-ml"at"aist.go.jp (ご連絡の際は”at”を@に直してから送信してください)
・問い合わせ内容
土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)追加の参加希望
更新日:令和4年10月31日
ダイオキシン国際会議での受賞のお知らせ (更新年月日:令和4年10月24日)
10月9-14日に米国ニューオーリンズで開催された第42回ダイオキシン国際会議において、PFAS対策技術コンソーシアムスーパーバイザーの一人であるLeo W.Y. Yeung博士の指導研究者2名がOtto Hutzinger Student Awardを受賞しました。PFASの環境挙動と処理技術両方のセッションでのダブル受賞となります。
今回の受賞内容はSwedish Institute for Standards (SIS) とPFAS対策技術コンソーシアムが共同で進めている有機態フッ素分析法の国際標準分析規格とも密接に関係します。
発表内容等を後日データベースに追加予定です。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The 42nd International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (October 9-14 2022, New Orleans, USA)
https://www.dioxin2022.org/(こちらをクリック)
Otto Hutzinger Student Award 2022
受賞者名:Mio Pettersson, Natalie Storm, Ingrid Ericson Jogsten, Leo W.Y. Yeung
組織名:Örebro University, Sweden
受賞タイトル:Utilization of organic and inorganic waste products for removal of per- and polyfluoroalkyl substances in highly contaminated water
受賞者名:Felicia Fredriksson, Anna Kärrman, Ulrika Eriksson, Leo W.Y. Yeung
組織名:Örebro University, Sweden
受賞タイトル:Bioavailability and biotransformation of technical mixtures containing side-chain fluorinated copolymers
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
なお、産総研では2003年の第23回ダイオキシン国際会議(米国ボストン)において谷保佐知 博士の発表 (PFASの海洋大循環、英語文献6) が、
スタンディングオベーションとともに同賞を授与され、その後10人以上の学生(第二、第三世代)が受賞し、今回は第四世代の卒業生の受賞になります。
環境研究総合推進費「S評価」のお知らせ (更新年月日:令和4年10月24日)
環境研究総合推進費「ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発 (2021-2023、課題番号:1G-2102、研究代表機関:産業技術総合研究所)」が中間評価で最高の「S評価」を受けました。研究成果資料の抜粋は環境再生保全機構のホームページで公開されています。(こちらをクリック)
本事業でPFASに関する技術実証型研究としては初めての「S評価」となり、類似プロジェクトの追従を許さない数多くの研究成果が高く評価されました。
最終年度では体制を一新し、本コンソーシアムの目標である「国内PFAS対策 (計測・処理) 技術の底上げ」に直結する研究成果を達成する予定です。
共同研究・技術相談他、本コンソーシアムの目標にご賛同いただける団体様はお気軽にご相談ください。
イベント情報(更新年月日:令和4年10月7日) 「11月21日特別講演会のお知らせ」
欧州最大規模のPFASプロジェクトであるPERFORCE3プロジェクトリーダの一人でもあるAhrens博士がPFAS対策技術コンソーシアムスーパーバイザーとして11月に来日します。これに先立ち、11月2日に予定するAhrens博士のご講演「スウェーデン軍等によるAFFF汚染環境修復技術について」および林則夫氏のご講演「燃焼イオンクロマトグラフを用いたフッ素化合物分析の現状 – PFASリスク評価も含めた国際的ニーズ」はコンソーシアム会員限定講演となりますが、内容の重要性を考慮し、前者については本講演の抜粋内容を、Ahrens博士ご本人の来日にあわせて、一般公演として配信します。当日はAhrens博士自身も参加しますので、オンラインでの質疑応答が可能です。
また、あわせて農業・食品産業技術総合研究機構の 殷 熙洙 博士に「PFASの問題解決に関する複数の視点からのアプローチ」と題してご講演をいただきます。
講演日時: 11月21日(月曜日)13:00-15:00 Microsoft Teams イベント
講演1. 「スウェーデン軍等によるAFFF汚染環境修復技術について(抜粋版)」
講演者:Lutz Ahrens博士(スウェーデン農業科学大学)及び産総研
講演2. 「PFASの問題解決に関する複数の視点からのアプローチ」
講演者:殷 熙洙博士(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部 高度分析研究センター 環境化学物質分析ユニット 上級研究員)
今回の特別講演会は「どなたでも」視聴できますので、下記よりご参加ください。
「PFAS対策技術コンソーシアム特別講演会(11月21日)」
(こちらをクリック)
MicrosoftTeams特別講演会内容は今後のコンソーシアム活動に役立てるために事務局で記録させていただきます。個人情報を特定する事はありませんが、不都合のある方は匿名のログイン(WEBよりゲストで入室)でお願いします。
イベント情報(更新年月日:令和4年9月20日)「システムデバイスロードマップ産学連携委員会(SDRJ)依頼公演のお知らせ」
講演日時 11月8日(火)14-15時
公益社団法人 応用物理学会 産学連携委員会 システムデバイスロードマップ産学連携委員会 (SDRJ) 様からのご依頼で講演を行います。
(詳細は下記参照)
https://www.sdrj.jp/(こちらをクリック)
・講演タイトル
国際的視点からのPFAS問題について
・講演者
山下信義 PFAS対策技術コンソーシアム会長
・講演概要
PFOSは過去、半導体製造フォトレジストなどに使われ、多くの企業で対策が進められた結果、直接の汚染は低減しましたが、PFAS問題としては前駆物質からの二次生成など、より複雑な研究に移行しています。
本講演では、PFAS研究の最新情報と環境修復技術の現状、ISO21675に代表される国際標準分析法、ストックホルム条約ガイドラインなど、国際的視点から説明します。
また時間が許せば2003年に国内で初めて開催された「PFOSコンソーシアム (産総研、経済産業省、日本化学工業協会、関連メーカー)」から現在までのPFAS対策の経緯についても概説します。
下記、PFAS対策技術コンソーシアムデータベースの一般向け講演を事前に視聴していただくと理解が深まります。
https://unit.aist.go.jp/mcml/rg-org/library_pfas.html(こちらをクリック)
イベント情報(更新年月日:令和4年8月19日)「Ahrens博士他、会員向け講演会のお知らせ」
次回会員向け講演会を11月2日(水曜日)に行います。 次回の講演会ではスウェーデンにおけるPFAS環境修復研究の中心人物の一人であるLutz
Ahrens博士他のご講演を予定しております。Ahrens博士は、PFAS対策技術コンソーシアムのスーパーバイザーとして国内PFAS汚染の現状視察と会員向け技術相談他に対応するために年内に来日を予定しております。
講演1. 「スウェーデン軍等によるAFFF汚染環境修復技術について」
講演者:Lutz Ahrens博士(スウェーデン農業科学大学)及び産総研
概要:Lutz Ahrens博士は、産総研招へい研究員として東京湾底質中のPFAS汚染の歴史的復元(2010年、https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.01.045)他の研究で博士号を取得し、カナダ環境省研究員、UNEPプログラムオフィサーアシスタントなどを経て現職。欧州で最も進んでいるAFFF環境修復技術について、スウェーデン軍の実例も交えて解説し、日本にどのような技術の導入が必要かについてもdiscussionを予定する。
Lutz Ahrens博士のホームページと関連プロジェクト
https://www.slu.se/en/ew-cv/lutz-ahrens/(こちらをクリック)
PERFORCE3
https://perforce3-itn.eu/(こちらをクリック)
StopPFAS
https://www.geo.uu.se/research/luval/disciplines/Hydrology/ongoing-research/geohydrology/pfa-remediation/(こちらをクリック)
PFASs-FREE:
https://www.slu.se/en/departments/aquatic-sciences-assessment/research/forskningsprojekt/active-research-projects/pfas/(こちらをクリック)
講演2. 「燃焼イオンクロマトグラフを用いたフッ素化合物分析の現状 – PFASリスク評価も含めた国際的ニーズ」
講演者:林 則夫 氏 (日東精工アナリテック株式会社)
概要: 2007年に産総研と三菱化学アナリテック(現日東精工アナリテック)が開発した超微量フッ素測定装置(AQF100F – AIST type)は、有機フッ素化合物のマスバランス研究領域の開拓につながり、最新装置であるAQF-2100Hは吸着体有機ハロゲン測定法の国際規格ISO/TC147/N2147の提案にもつながっている。特に5000種類を超えるPFAS類汚染の全体像を把握するためのマスバランス解析技術はTOP
assay法の開発を契機として世界的な注目を集めている。本講演では、国内には十分周知されていない、燃焼イオンクロマトグラフの様々な応用技術と国際的ニーズを中心に説明する。
イベント情報(更新年月日:令和4年7月26日)「土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)のお知らせ」
本コンソーシアムでは、国内には周知されていないPFASの高度計測技術と環境修復技術について、国外で実用化されている具体的な技術・実例を紹介することで高い評価を受けております。これにより当該コンソーシアムの目標である「産総研関連の技術シーズと海外の最新研究成果を国内産業界・地方自治体等に普及させ、国内PFAS対策(計測・処理)技術の底上げを行うこと」の実現に近づいています。
今年度の目標である「技術相談/見学会の拡充」につづき、より具体的な「技術移転」の試みとして、環境創生研究部門が代表機関である環境研究総合推進費「ペルフルオロアルキル化合物「群」のマルチメディア迅速計測技術と環境修復材料の開発」において、土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)を行います。これについて試験に参加して頂ける団体を募集しております。
下記内容になりますが、参加をご検討いただける団体様には、問い合わせよりお申し込みください。
【試験内容】
PFAS対策技術コンソーシアム第二回講演会「新機能性活性炭・電気/光化学技術を用いたPFAS処理技術開発」及び、第四回講演会「欧州における土壌及び水中PFAS処理技術の進展」で紹介された、液状PFAS吸着剤の土壌注入技術とPFAS安定化・除去効果の確認試験を実施します。試験に参加していただいた団体様には、本試験で検討する技術の詳細と評価試験結果などを標準操作手順書(SOP)として共有させていただきます。共有するSOPをもとに、皆様の今後の事業化に結び付けていただければ幸いです。また本試験結果をもとに地方自治体・政府事業等に応募される場合にも、引き続き技術的なサポートをさせていただきます。
【実施場所】 東京都内またはつくば市において実際の汚染土壌を想定 (産総研が手配)
【実施時期】 10月後半から今年度内
【実施期間】 一か月程度、現地参加者の従事時間は最長で三日程度
参加形態は基本的に下記のようになりますが、Teams面談により調整します。
・建設会社 (現場作業に必要な技術者派遣・機材貸与)
・分析機関 (処理前後の土壌試料・浸出水・灌漑水の分析)
・材料会社 (吸着剤の提供)
・その他の業種団体様からのご提案(データ解析・コンサルティング他)も歓迎します
申込締め切り 8月15日(月曜日)
・産総研の担当研究者
環境創生研究部門 谷保佐知
・問い合わせ先
M-PFAS-EMRI-ml"at"aist.go.jp (ご連絡の際は”at”を@に直してから送信してください)
・問い合わせ内容
土壌中PFAS除去技術実証試験(第二回分)に参加希望
イベント情報(更新年月日:令和4年6月21日)「研究施設見学会及びPFAS吸着剤評価試験開始のお知らせ」
6月6日の会員向け講演会内容はPFAS対策技術として既に事業化の端緒についています。そのため、現時点では一般公開は予定していませんが、会員向けリクエスト配信として再配信を予定しています。
また、コンソーシアムの今年度の目標として見学会・技術相談の拡充を目標にしており、下記を予定しています。
1. 見学会内容
最新のPFAS計測・処理技術やPFAS標準物質開発に関する実験室見学、及び必要に応じて座学。
予定時期:第一回見学会 10月予定。 第二回見学会 1月末または2月初旬予定。
2. 技術相談(PFAS吸着剤評価試験)
第二回及び第四回講演会で説明した44種類のPFAS吸着剤評価試験と同様の評価試験を、会員様ご提供の吸着剤について無償で実施します。
有償の技術コンサルティングの前に、お試しとして製品評価ができないかとの会員リクエストに対応しました。
活性炭・イオン交換樹脂・LDH他、
水溶液中でPFAS吸着能を評価できるものであれば種類は問いません。
ただし、試験数に限りがございますので、定員に達し次第受付を終了いたします。
イベント情報(更新年月日:令和4年5月10日) 「6月6日開催、会員向け講演会の内容など」
会員向け講演会が6月6日(月曜日13時より)に決定しました。特に、今回はコロナ後の正常化の試みとしてオンサイトとMicrosoft Teams会議のHybrid形式で開催します。講演概要は下記になります。
講演タイトル : 「欧州における土壌及び水中PFAS処理技術の進展(Advancements in PFAS soil and water remediation
technologies in the EU)」
演者 : Mattias Sorengard博士(スウェーデン農業科学大学、英語講演、事務局による逐次通訳有)
講演概要 : 欧州で実用化されているPFAS処理技術(コンソーシアムデータベースの第二回講演会「新機能性活性炭・電気/光化学技術を用いたPFAS処理技術開発」→こちらをクリック)について、最新情報を含めてアップデートし、現在産総研と共同で開発している新技術の一部についても紹介する。
講演タイトル : 「高温高圧水を用いた先端フッ素材料の高効率分解・無機化反応の開発」
演者 : 堀 久男 教授(神奈川大学理学部)
講演概要 : 現在使用されつつある新しい機能性有機フッ素化合物(フッ素系イオン液体、フッ素テロマー化合物、フッ素ポリマー)について、比較的低温の亜臨界水を用いてフッ化物イオンまで効果的に分解・無機化する方法について紹介する。
また時間が許せば、世界で初めて開発に成功、4月28日に公開された、大気中PFASのマスバランス解析技術と、当該コンソーシアム事務局の谷保が第39回とやま賞を受賞した研究内容についても簡単に説明予定です。
・大気中PFASのマスバランス解析技術
Fluorine Mass Balance Analysis and Per- and Polyfluoroalkyl Substances
in the Atmosphere. Huiju Lin, Sachi Taniyasu, Eriko Yamazaki, Rongben Wu,
Paul K.S. Lam, Heesoo Eun, Nobuyoshi Yamashita, Journal of Hazardous Materials
(IF 10.58), Available online 28 April 2022, 129025, doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.129025,
論文ページはこちらをクリック
・第39回 とやま賞受賞
谷保佐知 産業技術総合研究所環境創生研究部門 環境計測技術研究グループ長
*とやま賞のホームページはこちらのリンクからご覧いただけます→第39回「とやま賞」受賞者の決定について(富山県公式HP)
イベント情報(更新年月日:令和4年3月25日) 「3月9日開催会員向け講演会の抜粋配信、「Global PFAS Testing Virtual Symposium (Separation Science)」特別配信と次回講演会について」
・3月9日に開催した会員向け講演会のうち2件の抜粋版(一部sound only)をデータベースで公開します(4月20日公開予定)。→こちらをクリック
1) 「EU諸国におけるPFAS最新研究及び対策技術 (ノルウェー国立大気研究所」
2) 産総研におけるPFAS研究の歴史 A-18「Potential input of PFAS into the Japan Sea」(山崎ほか、DIOXIN2019、2019、Kyoto,
Japan)」
・Separation Scienceが5月4日に開催する「Global PFAS Testing Virtual Symposium」においてPFAS対策技術コンソーシアムより特別配信「Novel
Analytical Tools for Per- and Poly-fluoroalkyl Compounds and ISO21675,
Dr. Nobuyoshi Yamashita」を行います。英語の配信ですが、事前登録は下記よりお願いします。
※事前登録はこちらのリンクから→「Global PFAS Testing Virtual Symposium」
・6月上旬に予定する会員向け講演会では「コロナ以後」の正常化の試みとして、スウェーデン農業科学大学より招へい中のPFAS処理技術の専門家にリアルタイムで講演していただく予定です。特に対策立案が困難な汚染土壌処理技術についても最新情報を講演していただきます。
イベント情報(更新年月日:令和4年2月25日) 「会員向け講演会(3月9日)内容及び、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 環境分析Webセミナー特別配信について」
・3月9日開催予定の会員向け講演会では「EU諸国におけるPFAS最新研究及び対策技術 (ノルウェー国立大気研究所」と産総研におけるPFAS研究の歴史 A-18「Potential
input of PFAS into the Japan Sea」(山崎ほか、DIOXIN2019、2019、Kyoto, Japan)」他 を配信します。
・また、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社様のご依頼により、環境分析Webセミナー 2022で「PFAS分析法の国際標準化と最新技術」について特別配信します。(開催日時:2022年4月21日(木)13:15~17:00、申込期限:2022年4月14日(木)17:00)
招待講演「PFAS分析法の国際標準化と最新技術」
講演日時:2022年4月21日14:50-15:20
演者:山下 信義(国立研究開発法人産業技術総合研究所 PFAS対策技術コンソーシアム 会長)
概要:ペルフルオロアルキル化合物(PFAS)分析法は、水試料についてはISO25101やISO21675により国際標準化が達成され、世界中のだれでも信頼性の確保された測定値を得ることが可能となりました。一方で大気中に存在する揮発性PFASについては、標準分析法が確立されておらず、一般/作業環境測定値の信頼性に乏しく、適切な対策立案が困難なままです。本講演ではPFAS分析法の国際標準化の現状と、揮発性PFAS分析最新技術について説明します。
※PFAS対策技術コンソーシアムからの特別配信です。
※※詳細はこちらのリンクから→「環境分析Webセミナー 2022」
イベント情報(更新年月日:令和3年11月30日) 「PFAS対策技術コンソーシアム会員向け講演会及び打ち合わせ会議について」
PFAS対策技術コンソーシアム会員向け講演会及び打ち合わせ会議を11月24日に行いました。入会手続きが間に合わず、参加できなかった方にはお詫び申し上げます。
既に会員より再配信依頼を受けており「講演で説明されたPFAS最新技術はなぜ国内では知られていないのか?」「日本のガラパゴス化はここまで進んでいるのか」などのコメントをいただきました。事務局で検討した結果、運営会則に支障のない範囲で、会員向け講演会内容を一部抜粋して、一般公開することにしました。
また、運営会則に記載の通り、本コンソーシアムは令和6年3月31日までの3年間限定です。 3年間で「国内PFAS研究の失われた15年」を取り戻し、再び世界をリードできる最新技術を国内に普及する事が目標ですので、この機会に「最新のPFAS計測/処理技術の一端」に触れていただければ幸いです。
1. PFAS対策技術コンソーシアム打ち合わせ会議挨拶とPFAS関連認証標準物質について
2. 新機能性活性炭・電気/光化学技術を用いたPFAS処理技術開発(中国科学アカデミー・スウェーデン農業科学大学・産総研・材料/分析装置メーカー)
3. ストックホルム条約最新情報について(Global management of listed POP-PFASs in the Stockholm
Convention and some related research needs)(Roland Weber博士他、2021年版)
下記クリックで視聴可能(12月16日10時より公開予定)
(会員向け講演会内容の抜粋・修正版のため、大幅な省略、音声のみのスライドや、前後のつながりが悪い部分がありますが、これが仕様となります)
こちらをクリック(配信終了)
ポスドク及び契約職員募集(更新年月日:令和3年10月14日)
本コンソーシアム他の業務に従事するポスドク及び契約職員の募集を開始しました。 詳細は下記をご覧ください。
https://unit.aist.go.jp/hrd/keiyaku_koubo/tkb.html (環境創生研究部門)
イベント情報(更新年月日:令和3年9月21日) 「公開講演会の再視聴と会員向け講演内容について」
PFAS対策技術コンソーシアム公開講演会(8月31日、 9月2日)について、「内容密度が高いので時間をかけて視聴したい」「平日は時間がとりにくい」「Microsoft Teams録画ができることを知らなかった(一時停止可能です)」等のご要望をいただいていますが、現在でも基本的に再視聴は可能です。不定期にサーバーから削除されますので、その際は再配信を検討します。
また、11月に予定している会員向け講演会は、リクエストの多かった下記4件より2件程度を配信予定です。現在日程調整中ですが、10月22日までにご入会済みの会員の要望を優先して決定させていただきます。入会手続きには二週間ほどお時間をいただく場合がございますので、参加をご希望の方はこの点にご留意いただいた上でお申し込みください。
会員向け講演会(11月予定・全て日本語翻訳付き)
1. 新機能性活性炭・電気/光化学技術を用いたPFAS処理技術開発(中国科学アカデミー・スウェーデン農業科学大学・産総研・材料/分析装置メーカー)
2. REACH対応超高感度フッ素分析装置を用いた「全てのPFASのマスバランス解析技術」(産総研・エーレブルー大学・トロント大学)
3. ストックホルム条約最新情報について(Roland Weber博士他、2021年版)
4. PFAS対策技術コンソーシアム設立記念講演会「The first international online seminar for the
PFAS consortium in Japan and Asian supporters」
イベント情報(更新年月日:令和3年9月8日) 「会員向けサービスを11月に開始」
8月31日と9月2日に開催したPFAS対策技術コンソーシアム公開講演会では、60名を超えるご参加をいただき、本コンソーシアムへの社会的注目度が大きいことを確認できました。講演の再配信リクエストもすでに受けていますが、今後は会員向け活動に移行します。11月に初回の会員向けMicrosoft
Teams講演会及び本コンソーシアム打ち合わせ会議を予定しています。会員用メーリングリストで別途ご連絡させていただきます。
下記は打ち合わせ議題の一例になります。会員用メーリングリストご登録の方は、どのようなコンソーシアム業務が国内で必要とされているか、ご意見をお寄せください。会員登録フォームを事務局にご送付の際に、メール本文にご記載いただけますと幸いです。本コンソーシアムに関するご意見であれば、どのようなものでも歓迎です。
1. 国内産業界・地方自治体に必要なPFAS情報・技術とは何か?
2. 産業界自主管理や技能試験にふさわしいPFAS組成標準物質・材料の開発について。
3. 会員向け無料技術相談制度について。
4. 本コンソーシアムデータベースへの拡充希望(国外最新動向・最新技術実用化の現状等・・・)。
5. 会員向け講演会の開催頻度またはリクエスト対応配信について。
6. その他のご要望。
イベント情報(更新年月日:令和3年8月10日)
PFAS対策技術コンソーシアム公開講演会を8月31日と9月2日の二回配信します。内容は二回とも同一です。下記リンクより参加してください。
# 出席者の活動レポート(Office365アカウント表示名・メールアドレス、使用ソフトウェア、参加時刻・退出時刻)を今後の配信の効率化のために、コンソーシアム解散まで事務局で保管させていただきますのでご了承ください。WEBブラウザで「匿名で参加」を使用するとOffice365アカウント表示名・メールアドレスは記録されません。
※ご記入いただいた個人情報につきましては、本コンソーシアムに関する事務連絡以外の目的で使用することはございません。
8月31日(火)13時-17時
こちらをクリック(配信終了)
9月2日(木)13時-17時
こちらをクリック(配信終了)
イベント情報(更新年月日:令和3年7月30日)
・「PFAS対策技術コンソーシアム」設立記念講演会「The first international online seminar for the
PFAS consortium in Japan and Asian supporters」が7月29日に開催されました。中国、韓国、インド、日本に加え、EU諸国からも特別参加があり、計15件の講演が行われました。特にストックホルム条約評価委員として著名なRoland
Weber博士と香港公開大学大学長Paul Lam博士よりコンソーシアム設立について祝辞を頂き、ストックホルム条約最新情報についてコンソーシアム発足メンバー内で共有する事が出来ました。本講演会内容は後日会員向けに配信予定です。
・8月30日から9月3日の間に公開予定の講演会内容を以下の様に決定しました。全て日本語翻訳または字幕付きです。Microsoft TeamsのURLは近日中に本ホームページで公開します。また、事前登録された方に限り、講演後二週間限定で、講演内容に関するご質問を受け付けますので、事務局までお知らせください。
1. ISO21675基礎講座(39種類のPFAS一斉分析技術の国際規格であるISO21675の導入を検討している方向け)
2. 「PFAS研究の過去・現在・未来」An update on legacy and emerging perfluoroalkyl substances(PFASs)
(Kurunthachalam Kannan博士によるダイオキシン国際会議(Krakow, 2018)基調講演内容に最新情報を加え再構成)
3. 大気試料低温捕集装置/ガス・粒子一斉捕集装置を用いた揮発性・不揮発性PFAS一斉分析技術(part 1), (環境研究総合推進費「残留性有機フッ素化合物群の
全球動態解明のための海洋科学的研究」・戦略的基盤技術高度化支援事業「樹脂/金属接合技術を用いた大気中全マトリクス捕集装置の開発」他、
国家プロジェクト研究成果の社会実装)
・今年後半から開始する会員向けサービスでは下記を予定しています。
ISO21675応用講座(上記国際規格ISO21675(水質試料用)を応用し、土壌・食品・製品などの高感度分析を可能にする応用技術)、新機能性活性炭材料を用いたPFAS処理技術(スウェーデン農業科学大学/産総研)、REACH対応高感度総フッ素分析技術、大気試料低温捕集装置/ガス・粒子一斉捕集装置を用いた揮発性・不揮発性PFAS一斉分析技術(part
2)、人工知能網羅分析技術を用いた大気中PFAS一斉分析技術、中国における最新PFAS研究、他。
イベント情報(更新年月日:令和3年7月7日)
・「PFAS対策技術コンソーシアム」設立記念として「The first international online seminar for the
PFAS consortium in Japan and Asian supporters」が7月29日に開催されます。非公開ですが、後日会員向けに配信予定です。
・ダイオキシン国際会議2021(西安)の翌週、8月30日から9月3日の間に公開講演会をMicrosoft Teamsで配信します。プログラムは近日公開予定です。どなたでも参加できますが、参加人数によっては回線品質維持のために参加を制限する場合もあります。参加をご希望の方は、プログラム公開後に本コンソーシアム事務局まで事前登録をお願いします。【事務局メールアドレス:m-pfas_consortium-ml"at"aist.go.jp(ご連絡の際は”at”を@に直してから送信してください)】