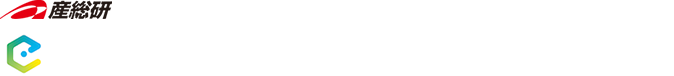研究概要
CO2から枯渇しつつある
炭素材料を作り、明日の産業を支える
石油は2030年から下り坂となり、このまま何の対策もせず使い続けると100年後には化石燃料が枯渇すると言われています。そのため化石燃料の枯渇という将来像からバックキャストして、代替となる資源を見つけることは人類にとっての大きな課題となっています。革新的な技術シーズを事業化につなげるための「橋渡し」「社会実装」機能に注力するAISTでは、CO2から炭素材料を作り出そうという研究にも取り組んでいます。
炭素材料は、身近なところではスマートフォンなどにも使用されており、自動車が動くうえで欠かせないタイヤにも使われています。炭素材料は軽量かつ高強度のため、タイヤはもとより幅広い産業の製品で使用されています。しかし先に述べた化石燃料の減少に伴い、原材料を入手することは年々、難しくなっています。一方、工業製品を作るときに排出されるCO2は増える一方です。もしCO2から既存の代替材料を作り出すことができれば、石油や石炭などのような化石燃料への依存からの脱却が可能になります。
現在、炭素材料を製造するためには、石油や石炭を蒸し焼きにして炭素材料を製造しています。しかし電気分解の技術を活用すれば、CO2から炭素材料を製造することが可能です。

上記の図を説明すると、たとえば食塩は約800℃になると液体になります。つまり粉体から液体へと形状が変化するわけですが、CO2から炭素材料を作る場合には、食塩等を溶かした溶融塩(ようゆうえん)を使用します。水は日常生活の室温の差で溶けたり、氷になったりしますが、塩の場合はさまざまな種類があり、種類によっては400~500度で溶融塩、つまり液体のような状態になるのです。なぜ水ではなく、融解塩を使用するのかという理由は、もし水を使用した場合CO2の分解が始まる前に水が分解してしまうからです。しかし溶融塩を使用すれば、CO2を電気分解しても液体の状態のままを保つことができるうえ、CO2からプラス極には酸素O2が生成され、マイナス極には炭素材料が生成されるのです。CO2から炭素材料を作り出すことは比較的容易なのですが、問題はそのクオリティー。工業製品として使える品質に仕上げるのにはまだまだ課題が山積しています。国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術術総合開発機構(NEDO)の支援のもと、CO2から炭素を合成する基盤研究を進め、現在は炭素の活用技術展開を模索しているところです。
CO2から枯渇しつつある化石資源を原料とする炭素材料を取り出すことができれば、今後、私たちのモノづくりはさらに躍進し続けられます。そのために私たちAISTでは、CO2から質の高い炭素材料を作り出すべく研究に取り組んでまいります。