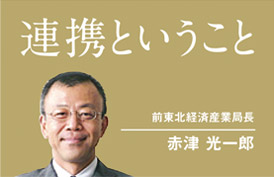 地域振興で重要なキーワードの一つに「連携」があります。産学官連携、農商工連携など、異業種や異分野との「連携」は新技術・製品開発や新たなノウハウの獲得などに不可欠のものと言えるでしょう。
地域振興で重要なキーワードの一つに「連携」があります。産学官連携、農商工連携など、異業種や異分野との「連携」は新技術・製品開発や新たなノウハウの獲得などに不可欠のものと言えるでしょう。
他方で、この「連携」と言う言葉、やや濫用されているのではないでしょうか。
法律などで使われているときは定義がはっきりしていますが、日常的に「よく連携して」などと使うような時には、必ずしも意味合いがはっきりしません。むしろ、意味合いをぼかすような使い方がされることさえあるように思います。
|
「協力」との違いもよくわかりません。強いて言えば「協力」には能動的なアクションのイメージがあるのに対して、「連携」はネットワークを重視したイメージでしょうか。「連携」と言われると、イメージとしては何となく納得してしまいますが、実際の使われ方を見ると、共同開発・研究や人事交流といったはっきりした形をとっているものから、たまに情報交換のための会議が開かれるだけといった「連携」に値しないようなものまでさまざまな意味合いがありえます。
これだけ広い意味合いを持たせられる言葉はそうはありませんから、使い勝手よく頻繁に使われるようになるのも無理はありません。
私の職場でも、「○○と連携して」と言われることが多いのですが、「具体的には?」と聞き返すことも多いのが現状です。
研究開発から事業展開まで、さまざまな場面で重要な役割を果たす概念であるだけに、贔屓の引き倒しにならないように、具体的なイメージをはっきり持った使い方をしたいものです。
|

