健康リスク評価(Health Hazard Assessment Team)は、昨年発足した新しいチームで、川崎 一をリーダーとして、4名のスタッフ(研究員1名およびテクニカルスタッフ2名)よりなる。以下に当チームが行っている研究について概要を述べる。
1)有害性評価研究
CRMでは当面の目標として約30物質について詳細リスク評価書を作成することになっており、当チームではこれらの物質の有害性について毒性プロファイルを把握するとともに有害性発現メカニズムについて考察し、ヒトにおける健康影響レベルの検証を行っている。
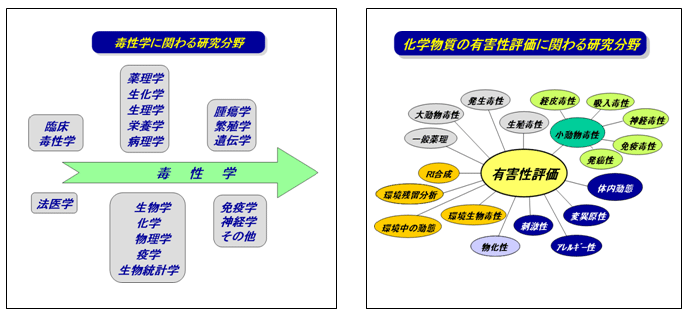
有害性評価研究は、図に示すようにライフサイエンスに関わる広い範囲の研究領域の成果と広い分野の研究手法を駆使して行われる。ライフサイエンス研究の進展はめざましいものがあり、そのため化学物質の有害性評価における有害性データの解釈も常に更新される。CRMが今、新たに評価を加える意義はここにある。
例えば、1,4-ジオキサンの発がん性のメカニズムについては各機関で以下の表に示すような違った見解を出している。評価対象としたデータは概ね共通にも拘わらず、データの解釈には大きな差がある。我々は最近の生理学的動態(PBPK)モデルを用いた解析結果を考慮して新しい見解を提出した(詳細リスク評価書シリーズ2 1,4-ジオキサン、丸善、2005年)。
表 1,4-ジオキサンの発がん性に関する評価の違い
|
|
WHO |
EU |
NIC |
IRIS |
BUA |
厚労省 |
環境省 |
CRM |
|
臓器 |
肝 |
肝 |
肝 |
鼻腔 |
その他 |
肝 |
評価 |
肝 |
|
閾値 |
あり/ |
あり |
あり |
なし |
あり |
なし |
評価 |
あり |
WHO:世界保健機関,EU:欧州連合,NICNAS:豪州工業化学品届出審査制度,IRIS:米国統合的リスク情報システム,BUA:ドイツ化学会の既存化学物質に関する諮問委員会
2)PBPKモデルの検証と有害性評価への応用
最近、PBPKモデルが化学物質のリスク評価に活用され、動物試験データをヒトに外挿する際の強力なツールとして注目されている。PBPKモデルを用いた解析により動物試験データからヒトへの外挿に関わる不確実性が小さくなり、定量的な推計の精度が高まる。同時に、有害性発現メカニズムについても有力な情報を提供することがある。当チームではPBPKモデルを開発するとともに公表されている多くのモデルの検証も併せて実施し、リスク評価の精度を高める努力を行っている。
3)工業用ナノ材料の有害性評価
工業用ナノ材料は、ナノスケールに起因する新しい特性を持つ素材で将来、身の回りの殆どの製品に使われると予想されている素材である。しかし、ナノスケールに起因する未知の有害性のあることが懸念されており、ナノ材料の安全性を早急に解析・評価する必要がある。当チームでは工業用ナノ材料の安全性評価の枠組みを構築するための研究プロジェクトに参加するとともにin vitroでの有害性評価試験法の開発研究を行っている。
4)ホルムアルデヒドの詳細リスク評価
ホルムアルデヒドは、in vitroでの変異原性が陽性であるとともにラットを用いた発がん性試験で鼻腔扁平上皮癌を発症する。しかし、ホルムアルデヒド暴露を受けた病理学研究者・解剖学研究者、工場労働者を対象としたコホート研究において、暴露と鼻咽腔腫瘍のリスク増加との因果関係について説得力のある証拠は殆どない。多くの発癌メカニズム研究によりラットで見られるホルムアルデヒドによる発がん性は、その強い反応性のため暴露局所で細胞障害が起こり、その細胞障害に対する代償性の細胞増殖反応が誘発され、それが持続することによるとするメカニズムが考えられている。従って、ホルムアルデヒドの発がん性には閾値があるとするのが、最も合理的な考え方であろう。WHO-ROE(World Health Organization-Regional Office for Europe)は、ホルムアルデヒドの空気質の指針値を30分間平均値で0.1
mg/m3(0.08 ppm)と設定しているが、その根拠は、この値がヒトの鼻粘膜へ障害を生じさせる推定閾値よりも1桁以上低い濃度であることによるとされており、我々も適切な考え方であると判断した。厚生労働省の室内濃度指針値は、このWHO-ROEの考え方に沿っている。このような考え方は、ホルムアルデヒドの定量的なリスク評価においては、ホルムアルデヒドの総暴露量(総摂取量)が問題となるのではなく、暴露濃度の評価が重要であることを示している。
(以上)