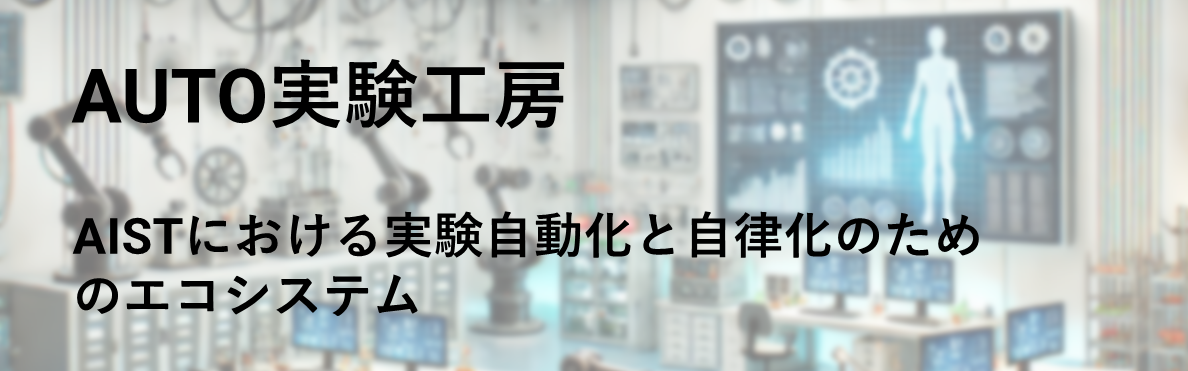AUTO実験工房とは
国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)では、研究の変革(Research Transformation:RX)を推進するために、「AUTO実験工房」という内部イニシアチブを立ち上げ、研究自動化や自律実験に積極的に取り組んでいます。AUTOkoboは、研究の分野を問わず広く活用できる実験システムの構築を目指した「エコシステム」であり、設備費の高さ、専門知識の必要性、ハードウェアやソフトウェアの標準化の不足といった、自律システム普及の障壁を乗り越えることを目的としています。モジュール式で再利用可能なプラットフォームを構築することで、研究へのアクセス性を高め、導入時のコストや技術的負担を軽減し、分野を超えた連携を促進しています。

申ウソク AUTO実験工房リーダー
AUTO実験工房へようこそ。
我々は自律実験の導入敷居を下げるために簡単に組み換え・改良できる低コストモジュールを開発し、
水平展開する新しい価値創造を行います。
システム開発支援、ノウハウ共有、研究者自らDIYができるように教育も行っています。
AUTO実験工房は全研究者の相棒です。
本部機能
(2) ワークショップ
(3) 情報共有
(4) 教育・セミナー
(1)モジュール開発と貸出
低コストで柔軟に再構成可能な実験システムを実現するための中核的なアプロ―との一つは、「モジュール」の開発です。モジュールとは、ロボットアームやディスペンサなど、特定の機能を持つ実験ツールを指します。これらの機能は、標準化されたインターフェースによって実現されており、研究者が必要に応じて容易に組み合わせ、自動化された実験系を構築できるようになっています。研究終了後にはモジュールが返却・再利用されるため、システムの変更が容易であると同時に、実験に伴う廃棄物の削減にもつながります。
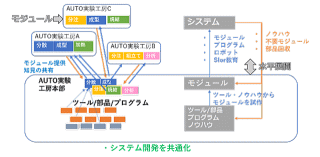
(2)ワークショップ
AUTO実験工房のワークショップは、たような実験自動化支援の中核拠点として機能しています。
一つの側面では、さまざまな自動かアクセサリを揃えた”コンビニ”的な役割を果たし、研究者が自身の実験システムを素早くモックアップできる場となっています。
また、次のセクションで説明するように、モジュールの開発もこの場所でおこなわれています。
さらに、実験システムは研究者の実験室へ設置される前に、この部屋で最終調整が行われます。

(3)情報共有
AUTO実験工房の主な取り組みの一つは、プログラムとノウハウを蓄積し共有するプラットとしての役割を果たすことです。そのために、ノウハウ、自動化アクセサリ、ベンチマーク情報などの収集・整理・保管に多くの労力をかけています。これらの情報は、AUTO実験工房のメンバーと共有される所内の情報データベースに蓄積されています。

(4)教育・セミナー
もう一つの重要な目標は、実験の自動化や自律化における技術的なハードルを下げるための教育プログラムの整備です。
AUTO実験工房では、ハンズオン形式、講義形式、少人数のワークショップ形式など、さまざまなスタイルで教育プログラムを提供しています。内容は、Pythonプログラミング、ロボットのリスクアセスメント、ロボットアームの操作、3D
CAD設計、3Dプリンティングなど、幅広いスキルをカバーしています。
こうした実践的で参加しやすい学びの場を通じて、研究者や技術者、学生の皆さんが自分自身の実験に自動化を取り入れられるよう、知識と自信を身につけることを目指しています。将来的には、それぞれの研究目的に合わせて柔軟で効率的、そして安全な自動化システムを設計・運用できる人材の育成を目指しています。

工房イベント
【2025年度】| 開催日 | 種類 | 講演タイトル | 講演者 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 教育コース1 | 「協働ロボット安全教育講習会」 | |
| 2026/01/20 | 第16回AUTO実験工房 全体会議 | ||
| 2025/11/10 | セミナー | 『Knowledge Graphs for Autonomous Experimentation in Material Science』 | Cogan Shimizu(Wright State Univ., USA) |
| 2025/10/10 | 第15回AUTO実験工房全体会議 |  |
|
| 2025/09/11 | 第14回AUTO実験工房全体会議 | ||
| 2025/08/21 | 『Closed-LoopとNIMO活用会議』 | ||
| 2025/07/24 | 第13回AUTO実験工房全体会議 | ||
| 2025/07/18 | セミナー | 『デジタル化が拓く新しい研究スタイル:日本の強みを世界へ』 | 一杉太郎 (東京大学) |
| 2025/06/06 | セミナー | 『バイオDXの実現に向けた実験自動化の目指す』 | 堀之内貴明 (理研) |
| 2025/05/20 | 教育プログラム初級① | 実験自動化のためのPython入門 (初級編4時間コース) |
|
| 2025/04/24 | キックオフ | 第12回AUTO実験工房全体会議-R7 | |
| 2025/04/16 | 教育プログラム中級① | 研究活動に活かす!3Dプリンタでものづくりワークショップ-治具・実験器具を自分で作れるようになろう- |
本部メンバー
(写真右から)- プロジェクトリーダー: 申 ウソク
- プロジェクトマネージャー: フタバ ドン
- システムインテグレーター: 井上 貴也

工房テーマ
(下図内 はクローズドループシステムを示しています)
はクローズドループシステムを示しています)
.jpg)
成果(論文、受賞、プレスリリースなど)
(2025)1. ”Self-driving laboratories in Japan”
N Yoshikawa, Y Asano, D.N. Futaba, K Harada, T Hitosugi, G.N. Kanda, S Matsuda, Y Nagata, K Nagato, M Naito, T Natsume, K Nishio, K Ono, H Ozaki, W Shin, J Shiomi, K Shizume, K Takahashi, S Takeda, I Takeuchi, R Tamura, K Tsuda and Y. Ushiku
Digital Discovery, 2025, 4, 1384.
連絡先
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ナノカーボン材料研究部門
〒305-8565 茨城県つくば市東1-1-1 中央事業所5群
Eメール:sgt-info-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信ください。)