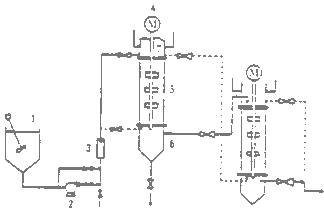
1.尨悈僞儞僋
2.億儞僾
3.棳検寁
4.潣漚婡
5.棳摦憌
6.僗儔僢僕
7.桘僞儞僋
亅丂壓岦棳
丒丒丒忋岦棳
丂杒奀摴偺傛偆側崀愥姦椻抧偵偍偄偰偼丄搤婜偺搥寢傗愊愥偺偨傔壏抔抧偺傛偆偵壓悈傗嶻嬈攔悈側偳偺張棟巤愝傪壆奜偵愝抲偡傞偙偲偑偱偒偢揔摉側忋壆傪昁梫偲偟丄峏偵悈壏傪張棟揔壏偵堐帩偡傞偨傔偵壛壏傪昁梫偲偡傞応崌傕偁傞丅摿偵丄杮摴偺嶻嬈偼擾椦丄抺嶻偍傛傃悈嶻側偳偺壛岺嬈偑懡偔偙傟傜偺嶻嬈攔悈偺張棟偵偼妶惈墭揇朄側偳偺旝惗暔張棟偑嵟傕岠壥揑偱偁傞偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅
丂偟偐偟側偑傜旝惗暔張棟偼悈壏偺掅壓偲偲傕偵妶惈傕掅壓偟丄5亅6亷埲壓偱偼尒妡偗忋妶摦偑掆巭偟偨偐偺傛偆偵側傞丅
丂廬偭偰丄旝惗暔張棟傪峴偆応崌偵偼悈壏傪彮側偔偲傕10亷埲忋偵曐偮昁梫偑偁傝丄姦椻抧偱偼偙偺偨傔懡妟偺擱椏旓偑梫媮偝傟傞丅埲忋偺偙偲傪憤崌偡傞偲丄廬棃壏抔抧曽偱晛媦偟偰偄傞旝惗暔張棟媄弍傪揔梡偡傞偲忋偵弎傋偨杊姦巤愝旓偍傛傃擱椏旓傪娷傔偰壏抔抧曽偺栺3攞偺宱旓偑偐偝傓偲尵傢傟丄偙傟偑杮摴偵偍偗傞嶻嬈攔悈張棟晛媦偺戝偒側瑗楬偵側偭偰偄傞丅偙偺傛偆側尰忬偐傜丄姦椻抧偵偍偗傞悈張棟偵懳偟偰敳杮揑尋媶偲媄弍奐敪傪憗媫偵峴偆昁梫偑偁傞偲敾抐偟杮尋媶偺棫埬偲側偭偨丅尋媶棫埬偵嵺偟偰偼
丂1乯 懳徾攔悈偺慖掕偍傛傃栚昗悈幙偺慖掕
丂2乯 奐敪懳徾偲偡傞悈張棟媄弍偺慖戰
丂3乯 1乯丄2乯偵懳偡傞姦椻抧岦媄弍奐敪
丂摍傪拞怱偵専摙傪廳偹偨寢壥丄惉壥偵晛曊惈傪帩偨偣傞偨傔摿掕偺攔悈傪懳徾偲偣偢庬乆偺攔悈傗壓悈偱墭愼偝傟偨壨愳悈傪忋幙側嶻嬈悈偲偟偰棙梡偡傞偨傔偺崅搙張棟媄弍偺奐敪傪峴偆偙偲偲偟偨丅尋媶奐敪偺嬶懱揑栚昗偼丄乮1乯張棟悈偺悈幙傪BODlO噐/l丄傾儞儌僯傾懺拏慺2噐/l丄偍傛傄僆儖僩儕儞巁懺儕儞0.2噐/l埲壓偲偡傞丅乮2乯張棟曽幃偼旝惗暔張棟傪庡懱偲偟悈張棟巤愝偼壆奜偵愝抲偟摼傞傕偺偲偡傞丅
丂偦偺偨傔偵丄愝抲偺愯桳嬻娫傪偱偒摼傞尷傝彫偝偔偡傞傛偆偵棫懱偐偮僐儞僷僋僩壔偟丄傑偨擬懝幐傪杊巭偡傞偨傔壜擻側尷傝枾暵峔憿偲偡傞側偳廬棃偺奐曻抮宆暯柺峔憿偵戙傢傞偄傢偽搩峔憿偺憰抲峔惉偐傜側傞僾儘僙僗奐敪傪庡娽偲偡傞丅
丂偦偟偰丄忋婰偺栚昗偵増偆崅搙張棟僾儘僙僗偲偟偰丄師偺扨埵張棟偵傛傞峔惉偑採埬偝傟偨丅尨悈仺a乯慳悈惈攠懱愙怗幃桘暘暘棧張棟仺b乯懡抜敇婥幃妶惈墭揇張棟仺c乯媧拝嵽傪巊梡偡傞旝惗暔扙拏張棟仺d乯扙儕儞傠夁張棟丅
丂a乯偼僄儅儖僕儑儞忬偵暘嶶偟偨桘暘傪娷傓攔悈傪慳悈惈攠懱乮億儕僄僠儗儞傗恖憿僑儉摍傪棻忬偵偟偨傕偺乯偵愙怗偝偣傞偙偲偵傛傝丄攠懱昞柺偵旝嵶桘暘棻巕傪晬拝崌亅偝偣戝偒側桘揌偵惉挿偝偣偰晜忋暘棧偡傞尨棟偵婎偯偄偰偄傞丅b乯偼丄廬棃庡偲偟偰奐曻柺偺戝偒偄抮宆敇婥憛傪梡偄偰峴偭偰偄傞妶惈墭揇張棟傪丄懡悢偺栚嶮偱巇愗傝傪偮偗偰懡抜壔偟偨僇儔儉宆敇婥憛拞偱峴傢偣傞傕偺偱斀墳岠棪偺憹戝丄憰抲偺僐儞僷僋僩壔偍傛傃擬懝幐偺杊巭摍傪恾傞丅c乯偼丄旐張棟悈傪揤慠僛僆儔僀僩廩揢憛偵捠偟偰傾儞儌僯僂儉僀僆儞傪媧拝彍嫀偟偮偄偱巊梡嵪僛僆儔僀僩傪徤壔憛偵堏偟徤壔嬠偺嶌梡偵傛傝媧拝偟偨傾儞儌僯僂儉僀僆儞傪徤壔扙棧偝偣偰嵞惗丄弞娐巊梡偡傞丅徤壔塼偼僛僆儔僀僩捠夁塼偲崌懱偟偰丄扙拏嬠傪晬拝偝偣偨妶惈扽偱拏慺偵娨尦偟偰傾儞儌僯傾懺拏慺傪彍嫀偡傞曽幃偱偁傞丅
丂d乯偼丄巇忋偘岺掱偱暋憌傠憛丄儕儞媧拝嵻廩?憛偍傛傃棻忬妶惈扽憛傪捈楍偵楢寢偟僆儖僩儕僲巁懺儕儞丄戺搙偍傛傃旝検桳婡暔側偳傪彍嫀偡傞偺偑栚揑偱偁傞丅暋憌傠憛傊捠偢傞摫悈僷僀僾偺拲悈岥晬嬤偱丄嬅廤嵻偍傛傄pH挷惍嵻 傪揧壛偡傞傛偆偵側偭偰偍傝憛撪偵偍偗傞愙怗嬅廤嶌梡偵傛傝扙儕儞傗彍戺岠壥傪岦忋偝偣傞傛偆偵側偭偰偄傞丅埲忋偺崅搙張棟僾儘僙僗偺尋媶偵偼奺扨埵張棟枅偵尋媶僌儖乕僾傪慻怐偟丄婎斦尋媶傪峴偭偰偦傟偧傟偺帋尡憰抲傪帋嶌偟丄屻敿偱偙傟傜傪捈寢偟偨堦楢偺崅搙張棟僾儘僙僗偵懳偡傞楢懕張棟帋尡傪峴偭偰昡壙傪帋傒偨丅
丂I 攠懱棳摦朄偵傛傞桘暘張棟
丂1丏傑偊偑偒
丂岺応偐傜攔弌偝傟傞桘惈墭悈偺庬椶偼嬌傔偰懡偔丄擹搙傕傑偪傑偪偱偁傝丄桘揌偺棻嶻傕懡庬懡條偱偁傞丅廬棃偐傜丄桘暘偺張棟偼杦傫偳偑壔妛揑曽朄偱峴傢傟偰偒偨丅偟偐偟丄椺偊偽壛埑晜忋朄傗揹夝晜忋朄偼桳岠側張棟朄偱偁傞偑丄憰抲偑暋嶨偱偁傝丄崅壙偵側傞偽偐傝偱側偔丄恖庤偑偐偐傞忋丄懡検偺僗僇儉傪惗偠傞寚揰偑偁傞丅偙傟偵斀偟丄暔棟揑張棟偺傒偵傛偭偰桘悈暘棧傪峴偊偽僗儔僢僕偺惗惉偼側偔丄暘棧偟偨桘偼擱椏偲偟偰傕巊梡偱偒傞丅偟偐傕帺摦壔偡傞偙偲傕梕堈偱偁傝丄儔儞僯儞僌僐僗僩偼埨壙偵側傞丅
丂摉強偱偼丄攠懱棳摦曽幃偵傛傞桘暘偺暘棧朄偺婎慴尋媶傪峴偭偰偒偨偑丄偙傟偼斾廳偑悈傛傝彫偝偄偐丄傑偨偼戝偒偄攠懱傪偦傟偧傟攔悈偺壓岦偒棳傑偨偼忋岦偒棳偺拞偵抲偔偙偲偵傛傝丄攠懱偑妶敪偵摦偒夞傝丄婍暻傗棻巕憡屳偲徴撍偡傞偙偲傪棙梡偟偨傕偺偱丄棳摦憌偺摿挜偲偟偰抦傜傟偰偄傞傛偆偵丄斀墳梕婍撪偺奺晹暘偼嬒堦側忬懺偵側傞丅
丂攠懱棳摦曽幃偵傛傞桘暘暘棧朄偼忋婰棳摦憌偺摿惈傪棙梡偡傞傕偺偱偁傝丄恊桘惈偲潧悈惈傪寭偹偦側偊偨攠懱乮僑儉椶丄摿庩僾儔僗僠僢僋椶摍乯傪桘暘偺嬅廤妀偲偟偰攔悈拞偵晜梀棳摦偝偣傞偙偲偵傛傝丄桘揌傊偺惗挿傪峴傢偣傞偲摨帪偵崿嵼偡傞寽戺暔幙偺嬅廤岠壥傪傕偁偘傞傕偺偱偁傞丅傑偨丄攠懱棻巕偺憡屳愻忩嶌梡偑偁傞偨傔丄攠懱嵞惗偑晄梡偵側傞偲峫偊傜傟傞丅偙偺攠懱棳摦張棟憰抲偺幚梡壔偺偨傔偵偼丄幚尡梡張棟憰抲偺惈擻偵偐偐傢傞場巕乮張棟悈検丄塼棳懍丄潣漚懍搙丄尨悈桘暘擹搙丄攠懱廩暬検丄棳摦張棟憰抲偺崅偝摍乯偵偮偄偰丄掕検揑偵攃埇偡傞偙偲偑廳梫偱偁傞丅
丂2丏幚尡曽朄
丂乮1乯幚尡憰抲
丂搩偺撪宎100噊丄崅偝1,000噊偺僷僀儘僢僩憰抲傪帋嶌偟丄偙傟傪幚尡梡張棟憰抲偲偟偰巊梡偟偨丅憰抲偺僼儘乕僔乕僩傪恾I亅1偵帵偡丅杮憰抲偼棳摦憛丄捑崀暘棧憛丄桘暘夞廂憛偺嶰憛偱宍惉偝傟偰偄傞丅嵟忋晹偺桘暘夞廂憛偼暘棧偝傟偨桘憌偺懾棷晹偱偁傝丄尨悈偼棳擖岥偐傜棳擖偡傞丅棳摦憛偵偼恊桘惈丄潧悈惈偺棻巕偵傛傞嬅廤妀乮攠懱乯傪廂擺偡傞丅張棟悈偑壓岦棳偺応崌偵偼丄嬅廤妀偺斾廳偼悈傛傝傕彫偝偄傕偺傪巊梡偡傞丅嵟壓晹偺捑崀暘棧憛偼悈傛傝傕廳偄晄弮暔偺捑崀傪峴偆傕偺偱丄嬅廤妀昞柺傛傝扙棊偟偨晬拝暔丄廳幙桘側偳偼丄偙偙偱悈偲暘棧偝傟丄捑崀暘棧憛攔弌岥傛傝攔弌偝傟傞丅桘暘偲暘棧偝傟偨悈偼棳弌岥傛傝庢傝弌偝傟傞丅忋壓偺懡岴斅偼嬅廤妀偺晜忋傑偨偼捑崀偵傛傞棳弌傪杊巭偡傞丅傑偨丄棳擖岥丄桘暘攔弌岥偺崅偝偼丄張棟偝傟傞傋偒暔幙偺忬懺丄斾廳側偳偵傛傝寁嶼偟偰寛掕偡傟偽丄帺摦揑偵桘悈暘棧忬懺傪曐偭偨傑傑悈偲桘偼攔弌偝傟傞丅偨偩杮憰抲偼僺僗僩儞僼儘乕偱偼側偄偨傔丄斀墳棪偑掅壓偡傞乮斀墳懍搙偵傛傞偑乯偲峫偊傜傟傞偺偱丄懳嶔偲偟偰懡搩壔偑峫偊傜傟傞丅
丂乮2乯楢懕張棟梡儌僨儖攔悈
丂儌僨儖攔悈偲偟偰偼丄摂桘傪僨傿僗僷乕僕儍乕偱丄10暘娫丄桘丗悈亖1丗9偱潣漚偟偨傕偺傪丄偝傜偵壠掚梡儈僉僒乕偱10攞偵婓庍偟丄桘暘10,000ppm偺僄儅儖僕儑儞塼偲偟偨傕偺傪尨悈挋憛偺潣漚婡偵傛偭偰丄強梫桘暘擹搙傑偱婓庍偟偰尨悈偲偟偨丅
丂乮3乯桘暘應掕
丂悈拞偺桘暘應掕偼丄桘暘應掕梡巐墫壔扽慺偱拪弌偟丄偦偺拪弌塼偺愒奜慄媧岝搙乮攇挿丄3.4乣3.5兪晅嬤偺CH怢弅怳摦偵傛傞媧廂乯傪應掕偟丄桘暘擹搙傪媮傔偨丅
丂2丏楢懕張棟幚尡
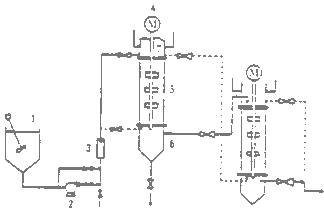 |
1.尨悈僞儞僋 2.億儞僾 3.棳検寁 4.潣漚婡 5.棳摦憌 6.僗儔僢僕 7.桘僞儞僋 亅丂壓岦棳 丒丒丒忋岦棳 |
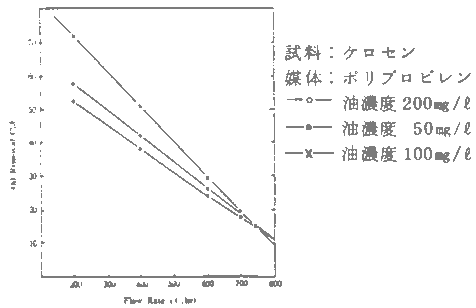
丂
丂(1)張棟悈検偲桘暘偺彍嫀棪
丂幚尡偺寢壥傪恾I亅2偵帵偡丅張棟悈検偺憹壛偵傛傝桘暘偺彍嫀棪偼掅壓偡傞偑丄偙傟偼丄懾棷帪娫偲棳懍偺椉曽偑塭嬁偟偰偍傝恾I亅3丄4偵帵偡捠傝丄懾棷帪娫偑戝偒偄掱丄傑偨棳懍傪彫偝偔偡傞掱丄彍嫀棪偑椙偔側傞偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅
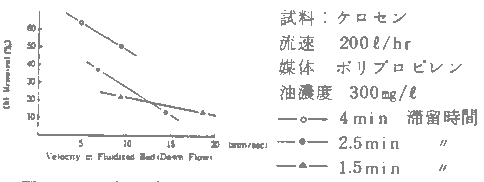
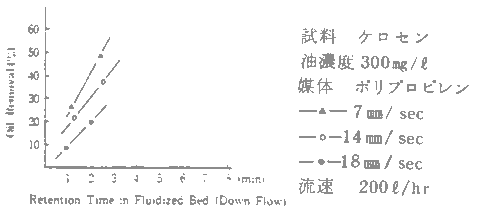
丂
丂(2)潣漚懍搙偲彍嫀棪
丂潣漚懍搙傪戝偒偔偡傞掱丄桘暘偺彍嫀棪偼椙偔側傞偑丄攠懱昞柺偺攋懝偑挊偟偔側傞偨傔丄50乣100rpm偺斖埻偱偺潣漚偱攠懱偺攋懝偵懳偡傞塭嬁偑彮側偄偙偲偑傢偐偭偨丅
丂(3)搩挿偲攠懱偺廩?棪
丂搩挿偲攠懱廩?棪偵傛傞桘暘彍嫀棪偺曄壔偵偮偄偰丄専摙傪峴偭偨丅偦偺寢壥丄棳摦憛偺挿偝偼丄1,400噊傑偱偼搩挿偺憹壛偲偲傕偵彍嫀棪偼椙偔側傞偑丄1,400噊埲忋偵偡傞偲彍嫀棪偑掅壓偡傞偙偲偑傢偐傞丅傑偨丄攠懱偺廩?棪傪憹偡偲桘暘偺彍嫀棪偼庒姳椙偔側傞偑丄偦偺塭嬁偑彫偝偄偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅
丂(4)桘暘偺廂巟
丂彍嫀偝傟偨桘暘偺峴曽偵偮偄偰専摙偟偨寢壥偺1椺傪昞I亅1偵帵偟偨丅
丂
| 尨悈拞偺 桘暘(A) | 張棟悈拞偺 桘暘(B) | 堨棳悈拞偺 桘暘(C) |
攠懱拞媧拝桘暘 D=A-(B+C) |
| (1)290g/hr | 120g/hr | 8g/hr | 162g/hr |
| (2)120g/hr | 44g/hr | 3g/hr | 73g/hr |
丂
丂II 懡抜偽偭婥朄偵傛傞旝惗暔張棟
丂1丏傑偊偑偓
丂桳婡惈攑悈傪張棟偡傞偨傔偵丄惗暔妛揑曽朄偺堦偮偱偁傞妶惈僗儔僢僕朄偑峀偔巊傢傟偰偄傞丅姦椻抧偵偍偄偰偼丄摿偵擬偺堩嶶傪梷偊悈壏偺掅壓傪側傞傋偔彮側偔偟偰旝惗暔偺妶惈傪堐帩偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅妶惈僗儔僢僕朄偵偍偄偰崅晧壸張棟偺忈奞偵側傞偺偼丄旝惗暔偺桳婡暔偲偺斀墳懍搙偺栤戣傛傝偼丄傓偟傠旝惗暔憡偑曄壔偡傞偙偲偵傛傝張棟悈偲旝惗暔僗儔僢僕偺暘棧偑崲擄偵側傞応崌偱偁傞偙偲偑懡偄丅偙偺偆偪丄巺忬惈旝惗暔偑桪愯庬偵側偭偰僗儔僢僕偑朿壔偟丄捑崀暘棧偑偆傑偔峴偐偢張棟悈偵僗儔僢僕偑棳弌偡傞忬懺偑巺忬惈僶儖僉儞僌偲屇偽傟傞尰徾偱偁傞丅
丂崅晧壸旝惗暔張棟傪栚巜偡偨傔偵偼丄旝惗暔偺忩壔擻椡傪嵟戝尷偵棙梡偟側偑傜捑崀惈偺椙偄旝惗暔憡傪堐帩偡傞偙偲偑昁梫偵側傞丅偽偭婥憛撪傪墴偟弌偟棳傟偵偡傞偙偲偵傛偭偰丄巺忬嬠偺憹怋偑梷惂偝傟傞偙偲偑抦傜傟偰偍傝丄姦椻抧偵偍偗傞崅晧壸偺惗暔妛揑張棟傪峴偆偨傔偵偼偙偺抦尒傪墳梡偡傞丅偡側傢偪丄憰抲撪偵棳傟曽岦偺媡棳傪杊巭偡傞偨傔偺巇愗斅傪擖傟傞偙偲偵傛傝懡抜壔偡傞偲丄墴偟弌偟棳傟偵嬤偯偄偨棳傟摿惈傪傕偨偣傞偙偲偑偱偒傞丅姦椻抧偵偍偗傞擬偺堩嶶傪彮側偔偡傞偨傔偵偼丄奐悈柺傪側傞傋偔彮側偔偟丄偐偮憰抲偺昞柺愊傕彫偝偔偡傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅偙傟傜偺揰傪峫椂偵擖傟丄杮僔僗僥儉偱偼桳婡惈墭戺暔偺旝惗暔張棟偵偍偄偰丄偨偰宆懡抜偽偭婥憛傪嵦梡偡傞偙偲偵偟偨丅
丂2丏偨偰宆懡抜偽偭婥憛偺巇條
丂杮僔僗僥儉偵嵦梡偟偨偨偰宆懡抜偽偭婥曽幃妶惈僗儔僢僕朄偺憰抲恾傪恾II亅1偵帵偡丅[1]偼6抜偐傜側傞墌摏偨偰宆偽偭婥憛偱丄撪宎0.31m丄崅偒3m乮1抜偺崅偝0.5m乯偱丄寠偁偒巇愗斅偵傛偭偰奺抜傪暘偗偰偄傞丅奺抜偺撪梕愊偼37.7倢丄憛慡懱偱22.6倢偱偁傞丅巇愗斅偼岤偝3噊偺傾僋儕儖庽帀惢偱丄捈宎4噊偺寠偑僺僢僠8噋偺嶰妏宍攝抲偱19屄偁偗偰偁傝丄偙偺奐岥斾偼0.32亾偱偁傞丅1抜栚偺掙柺偵偼丄僺僢僠4噊偺嶰妏宍攝抲偱55屄偺嬻婥悂崬傒儘偑偁傝丄僐儞僾儗僢僒乕偐傜偺嬻婥偑寁検偝傟偨屻丄暘攝偝傟偰奺悂崬傒岥偐傜憛撪偵憲傝崬傑傟傞丅奺抜偺偆偪敿暘丄偡傪傢偪崅偝偵偟偰0.25m偼僗僥儞儗僗峾惢偺僂僅乕僞乕僕儍働僢僩偵側偭偰偍傝丄峆壏憛偐傜偺堦掕壏搙塼偑弞娐偟偰偄傞丅懠偺敿暘偼傾僋儕儖庽帀惢偱丄僒儞僾儕儞僌岥偲梟懚巁慺揹嬌庢晅岥偑愝偗偰偁傞丅憛慡懱傪敪朅僗僠儘乕儖偱抐擬偟偰偁傞丅[2]偼捑崀憛偱丄堨棳晹偺奜宎0.4m丄墌摏晹怺偝0.4m媡墌偡偄晹怺偝0.4m偱憛撪梕愊偼65.3倢偱偁傞丅偽偭婥憛偐傜偺妶惈僗儔僢僕崿崌塼偼丄捑崀憛偺拞怱晹偵偼偄傝丄僗儔僢僕偑捑崀偟丄忋悷悈偑堨棳偟偰張棟悈偲側傝僗儔僢僕偼偽偭婥憛偵曉憲偝傟傞丅暻柺偵晅拝偟偨僗儔僢僕偼丄掅懍偱夞揮偡傞僗儔僢僕偐偒棊偟梡偺偔偝傝偱棊偝傟傞丅[3]偼婰榐幃懡揰梟懚巁慺寁偱丄偽偭婥憛奺抜偵庢傝偮偗偨梟懚巁慺揹嬌偐傜偺怣崋傪婰榐偟丄傾僫儘僌怣崋傪弌椡偡傞丅壏搙曗彏晅僈儖僶僯揹抮幃妘枌揹嬌傪12杮愙懕偱偒傞丅應掕斖埻偼0乣25傑偨偼0乣5噐俷2丒l亅1偱婰榐寁偲娭學側偔愗姺僗僀僢僠偵傛傝擟堄偺揰偮偄偰僨僕僞儖昞帵偱偒傞丅[4]偼巁慺徚旓検墘嶼憰抲偱丄僜乕僪幮惢儅僀僋儘僐儞僺儏乕僞M223MarkII傪巊偄丄[3]偐傜偺梟懚巁慺擹搙怣崋偲丄暿搑媮傔偰偍偄偨憤妵暔幙堏摦梕検學悢乮KLa乯偍傛傃壏搙偲悈埑偺曗惓傪偟偨朞榓梟懚巁慺擹搙偲偐傜奺抜偵偍偗傞巁慺徚旓懍搙傪媮傔傞丅強掕帪娫娫妘乮捠忢偼1暘娫乯枅偵庢傝崬傫偩應掕抣偼丄僼儘僢僺乕僨傿僗僋婰壇憰抲乮6抜偺奺揰偵偮偄偰1暘娫枅偺抣傪1廡娫暘偺梕検乯偵婰壇偡傞丅偙偺寢壥偼強掕偺帪娫偁傞偄偼昁梫側帪偵丄奺抜偺巁慺徚旓懍搙暘晍傑偨偼奺抜枅偺帪娫宱夁偲偟偰CRT偱僨傿僗僾儗乕偵昞帵偝偣丄傑偨XY僾儘僢僞乕偵彂偒弌偝偣傞偙偲偑偱偒傞丅[5]偼弞娐幃峆壏憛偱丄嬻椻幃0.75KW椻搥婡偲2KW僸乕僞乕偵傛偭偰梕検200l偺悈憛拞偺悈傪壏搙挷愡偟丄偙偺悈偑偽偭婥憛偺僂僅乕僞乕僕儍働僢僩偲偺娫傪弞娐偡傞丅
丂3丏楢懕張棟幚尡
丂(1)幚尡曽朄
丂尨悈偺挷惍偵偁偨偭偰偼丄幚攑悈偺梫慺偺偆偪懡惉暘傪娷傓揰偐傜搒巗壓悈偺堦師張棟悈傪儀乕僗偵偟丄偝傜偵岺応攑悈傪憐掕偟偨桳婡暔擹搙偵偡傞偨傔偵僐乕儞僗僠乕僾儕僇乕乮CSL乯擹岤塼傑偨偼CSL擹岤塼偲僌儖僐乕僗傪揧壛偟偨丅幚尡忦審偺堦椺傪昞II亅1偵帵偡丅偙偺拞偱丄尨悈BOD丄尨悈COD偍傛傃崿崌晜梀暔擹搙乮MLSS乯偼應掕抣偺婜娫暯嬒抣偱帵偟偰偁傞丅挷惍尨悈偼挿婜曐懚偱偒側偄偺偱1擔暘500l傪枅擔挷惍偟偨丅
丂堦師張棟悈500l偵懳偟丄S亅1偱偼CSL擹岤塼傪0.9l丄S亅2偱偼CSL擹岤塼0.4倢偲僌儖僐乕僗180g傪揧壛偟偨丅
丂掅壏偐偮崅晧壸偵偐偗傞懡抜偽偭婥憛撪偺拏慺偍傛傃儕儞偺摦岦傪挷傋傞偨傔偵丄尨悈偍傛傃張棟悈偵偮偄偰拏慺壔崌暔偍傛傄儕儞壔崌暔傪暘愅偟偨丅拏慺偵偮偄偰偼働儖僟乕儖朄偱慡拏慺傪媮傔丄僆乕僩傾僫儔僀僓乕偵傛偭偰媮傔偨傾儞儌僯傾懺拏慺偲偺嵎傪桳婡惈拏慺偲偟偨丅儕儞偵偮偄偰偼棸巁暘夝朄偵傛偭偰慡儕儞傪媮傔丄暿偵僆儖僩儞巁懺儕儞傪媮傔偰嵎傪桳婡惈儕儞偲偟偨丅
丂
| 尨悈惉暘 | 堦師悈+CSL | 堦師壓悈+CSL+Glucose |
| BOD[mg/l] | 864 | 942 |
| COD[mg/l] | 362 | 458 |
| 嫙媼懍搙[l/hr] | 19 | 19 |
| 曉憲墭揇[%] | 50 | 50 |
| 暯嬒懾棷帪娫[hr] | 8 | 8 |
| MLSS[g/l] | 3.34 | 3.32 |
| 壏搙[亷] | 5 | 5 |
| 偽偭婥懍搙[m/hr] | 10.8 | 10.8 |
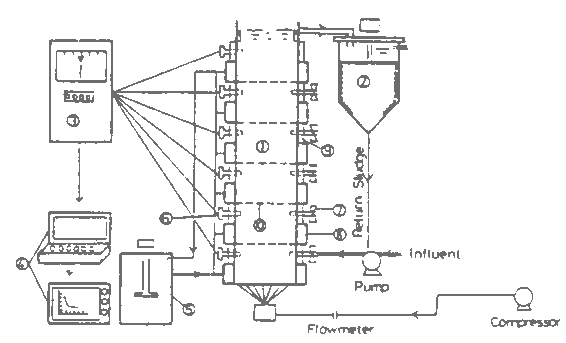
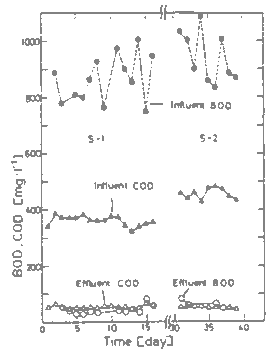
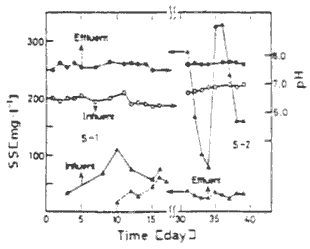
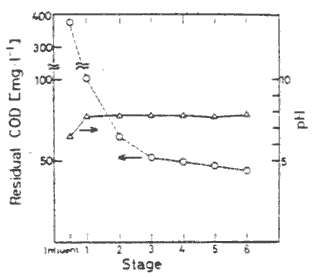
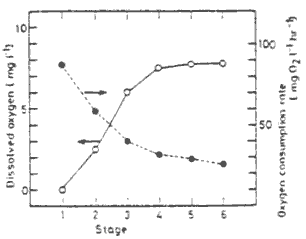
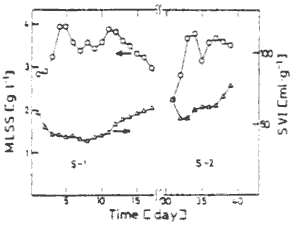
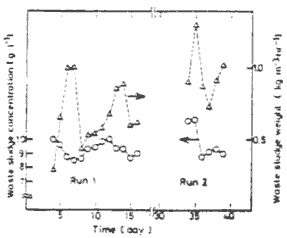

丂
丂(2)寢壥偲峫嶡
丂尨悈偲張棟悈偵偮偄偰BOD偲COD傪應掕偟偨寢壥傪恾II亅2偵帵偡丅尨悈偺挷惍偵偁偨偭偰偼CSL擹岤塼偺堦掕検傪揧壛偟偰偄傞偑丄尨悈擹搙偺偽傜偮偒偼旔偗傜傟側偄丅尨悈偵偮偄偰偼BOD抣偑COD抣偺2攞嫮偱偁傞偑丄張棟悈偵偮偄偰傎傏摨掱搙偱偁傞丅S亅1偍傛傃S亅2傪捠偟偰張棟悈偺BOD偍傛傄COD偼戝偒側曄摦偑側偔丄彍嫀棪偼BOD偍傛傄COD偵偮偄偰偦傟偧傟95亾埲忋偍傛傃85亾埲忋傪払惉偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅
丂恾II亅3偼丄尨悈偲張棟悈偵偮偄偰晜梀惈寽戺暔乮SS乯偲pH傪應掕偟偨寢壥傪帵偡丅尨悈偺SS偼丄儀乕僗偲側偭偨壓悈堦師張棟悈偺忬懺偵傛偭偰戝偒偔偐傢傝丄傑偨尨悈僞儞僋撪偱擔悢偲偲傕偵堦晹捑崀偡傞偙偲偺塭嬁傪庴偗傞偺偱曄摦偟偰偄傞丅偄偢傟偺応崌傕張棟悈偺SS偼摨掱搙偵側偭偰偄傞丅 pH偼丄尨悈偱栺6.5張棟悈偱栺7.8亾偲斾妑揑堦掕偟偨抣偵側偭偰偄傞丅
丂偽偭婥憛撪偺奺抜偵偍偗傞COD彍嫀偲pH偺宱夁傪恾II亅4偵帵偡丅彍嫀壜擻側COD偺栺85亾埲忋偑1抜栚偵偍偄偰彍嫀偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 pH偼1抜栚偵偼偄偭偨帪揰偱娚徴嶌梡傪庴偗丄偦偺屻6抜栚傑偱傎傎堦掕抣偱憲傜傟偰偄傞丅
丂奺抜偵偍偗傞梟懚巁慺擹搙偲丄偙傟傪傕偲偵嶼弌偟偨巁慺徚旓懍搙傪恾II亅5偵帵偡丅1抜栚偺梟懚巁慺擹搙偼傎偲傫偳0偵側偭偰偍傝丄巁慺徚旓懍搙偼KLa偺抣偵傛偭偰寛傑傞抣嶐偵側傞丅COD偺彍嫀偑1抜栚偵偄偰挊偟偄偺偵斾傋偰巁慺徚旓懍搙偼偦傟傎偳挊偟偔偼側偔1抜栚偵偍偄偰偼丄廫暘側巁慺偑側偔偲傕婎幙偺彍嫀偑恑峴偟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅
丂6抜栚偐傜敳偒弌偟偨塼偵偮偄偰丄30暘娫偺僗儔僢僕捑崀梕愊乮SV30乯偍傛傃崿崌塼晜梀暔擹搙乮MLSS乯傪應掕偟僗儔僢僕梕検巜昗乮SVI乯傪媮傔偰僘儔僢僕偺捑崀惈傪傒偨宱夁傪恾II亅6偵帵偡丅 SVI偼70ml丒g-i掱搙偱偁傝丄捑崀憛偵偍偗傞暘棧偵巟忈偼側偐偭偨丅MLSS傪堦掕偵曐偮偨傔偵曉憲僗儔僢僕偺堦晹傪堷偒敳偒丄堷偒敳偒塼偺MLSS偲塼検傪應掕偟偰堷偒敳偒梋忚僗儔僢僕偺姡憞廳検傪媮傔偨丅偙偺宱夁傪恾II亅7偵帵偡丅
丂尨悈擹搙丄尨悈棳検偍傛傃偽偭婥憛撪MLSS偺婜娫暯嬒抣偐傜僗儔僢僕摉傝晧壸傪寁嶼偡傞偲S亅1偍傛傃S亅2偵偮偄偰偦傟偧傟0.50偍傛傃0.57g(BOD)乛g(SS)丒day偲側傝丄壏搙偑5亷偱偁傞偙偲傪峫偊傞偲偐側傝偺崅晧壸偱偁傞偲尵偊傞丅崅晧壸偵偍偄偰偼梋忚僗儔僢僕偺惗惉偑栤戣偵側傞偑丄婜娫拞偺BOD偺憤検偲敳偒弌偟僗儔僢僕憤検偐傜僗儔僢僕惗惉棪傪媮傔傞偲丄S亅1偍傛傃S亅2偵偮偄偰偦傟偧傟0.38偍傛傃0.51g(SS)乛g(BOD)偲側偭偨丅S亅2偵偍偄偰偼尨悈拞偺SS暘偑懡偔丄偙傟偑庢傝崬傑傟偰僗儔僢僕惗惉検偑憹壛偟偨傕偺偲巚傢傟傞丅
丂拏慺壔崌暔偍傛傃儕儞壔崌暔偺暘愅寢壥偵婎偒丄奺乆偵偮偄偰丄暔幙廂巟傪尒偨寢壥傪恾II亅8偵帵偡丅垷徤巁懺偍傛傃徤巁懺偺拏慺偼専弌偝傟偢丄杮幚尡斖埻偺壏搙偲晧壸忦審偱偼徤壔偑婲偒偰偄側偄偙偲丄傑偨桳婡懺拏慺偼嬠懱偲偟偰屌掕偝傟丄梋忚僗儔僢僕偲偟偰敳偒弌偝傟傞晹暘偺懡偄偙偲偑傢偐傞丅儕儞偵偮偄偰傕僆儖僩儕儞巁懺儕儞偑戝晹暘梋忚僗儔僢僕拞偵屌掕偝傟偰彍嫀偝傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅
丂III 媧拝嵻傪梡偄偨旝惗暔扙拏張棟
丂1丏傑偊偑偒
丂壓悈丄攔悈拞偺拏慺壔崌暔偼丄桳婡懺拏慺丄傾儞儌僯傾懺拏慺丄徤巁懺拏慺丄垷徤巁懺拏慺偺宍偱懚嵼偡傞丅偙偺偆偪丄桳婡懺拏慺偼丄張棟偺懳徾偲側傞壓悈丄攔悈偑丄張棟偺慜抜偱旝惗暔張棟乮妶惈墭揇張棟乯傪宱偰偄傞応崌偵偼丄BOD惉暘偺彍嫀偺嵺偵丄旝惗暔偺嶌梡偵傛傝彍嫀偝傟丄堦晹偼傾儞儌僯傾懺拏慺偵揮姺偝傟偰偄傞傕偺偲尒傜傟傞丅偙偺尋媶偱偼丄妶惈墭揇張棟屻偺棳弌悈傪懳徾偲偟偰丄拏慺壔崌暔偺彍嫀偺専摙傪峴偆偑丄彍嫀偺懳徾偼丄忋弎偺棟桼偵傛傝柍婡懺拏慺丄偡側傢偪傾儞儌僯傾惈拏慺偲偡傞丅偦偟偰丄扙拏慺張棟朄偲偟偰丄旝惗暔張棟偲僛僆儔僀僩偵傛傞傾儞儌僯傾偺媧拝彍嫀朄偲傪慻傒崌傢偣丄掅壏搙偺壓偵憖嶌壜擻側拏慺彍嫀朄偺奐敪傪帋傒偨丅
丂2丏幚尡曽朄偍傛傃憰抲
丂幚尡偼丄廩?僇儔儉偵傛傞乮敿乯夞暘幃棳捠帋尡偍傛傃潣漚憛宆帋尡憰抲偵傛傞楢懕幃尡傪峴偭偨丅僇儔儉帋尡偵偼捈宎栺60噊丄崅偝1000噊偺摟柧傾僋儕儖庽帀惢墌摏傪梡偄丄撪晹偵偼價乕僘忬妶惈扽乮屶塇壔妛岺嬈惢乯傪廩?偟偨丅帋椏悈偼忋晹傛傝棳壓偡傞壓岦棳偲偟丄岲婥惈帋尡乮徤壔乯偺偲偒偼挜壛埑偲偟偰丄庒姳検偺嬻婥傪帋椏悈偲嫟偵嫙媼偟偨丅幚尡偵梡偄偨帋椏悈偼崌惉帋悈偱偁傝丄徤壔帋尡偵嫙偟偨帋椏悈偺慻惉偼K2HPO4丒3H2O乮49.8噐亴乯KH2PO4乮28.0噐亴乯Na2HPO4丒12H2O乮55.5mg亴乯MgSO4丒7H2O乮50.0噐亴乯FeCI3丒6H2O乮3.0 mg亴乯MnSO4丒nH2O乮5.0丄噐亴乯CaCI2丒2H2O乮37丏O噐亴乯GIucose乮0乣250噐亴乯乮NH4乯2SO4乮27.3乣163噐亴乯傪扙僀僆儞悈1l偵梟夝偟偨傕偺偱偁傞丅傑偨丄扙拏慺帋尡偵嫙偟偨帋椏悈偺慻惉偼丄NaNO3乮121mg亴乯K2HPO4丒3H2O乮40噐亴乯MgSO4丒7H20乮180mg亴乯FeCI3丒6H2O乮0.75噐亴乯KCI乮0.5g乯CH30H乮55噐亴乯傪扙僀僆儞悈1l偵梟夝偟偰挷惢偟偨丅偨偩偟丄棸巁僫僩儕僂儉偍傛傃儊僞僲乕儖傑偨偼僌儖僐乕僗偺検偼幚尡寁夋偵傛傝揔媂曄峏偡傞偙偲偵偟偨丅
丂潣漚憛宆帋尡憰抲偺奣梫傪恾III亅1偵帵偡丅嫙帋悈偼掕検億儞僾偵傛傝潣漚憛偵摫偐傟丄偙偙偱僛僆儔僀僩偲愙怗偟丄戝晹暘偺傾儞儌僯傾偼媧拝偝傟傞丅師偄偱丄彿攓憛2偵堨棳偟丄偙偙偱徤壔嬠偺摥偒偵傛傝徤壔嶌梡傪庴偗丄傾儞儌僯傾偺堦晹暘偼徤巁僀僆儞偵曄偊傜傟傞丅潣漚憛2傪弌偨僛僆儔僀僩偲帋悈偼丄師偓偵丄捑崀憛偵擖傝丄偙偙偱忋悷塼偲屌懱偵暘偐傟丄忋悷塼偼扙拏張棟傪庴偗傞丅屌懱偼潣漚憛3偵擖傝丄偙偙偱徤壔嬠偵傛傝廫暘側徤壔嶌梡傪庴偗丄傾儞儌僯傾偺媧拝椡傪夞暅偟丄張棟悈偺堦晹偲嫟偵僗儔儕乕忬偱潣漚憛1傊曉憲偝傟傞丅傑偨丄僛僆儔僀僩偼帋尡拞偵杹柵偟丄彊乆偵棳幐偟偰偄偔偺偱丄拲擖岥A傛傝帪乆曗媼偡傞丅巊梡偟偨僛僆儔僀僩偼丄廐揷導僯僢堜嶻偺揤慠僛僆儔僀僩偱丄巊梡偵嵺偟偰丄億乕儖儈儖偱攋嵱偟饪暘偗偟丄棻搙傪100乣150儊僢僔儏偵懙偊偨丅
丂潣漚憛2丄3偼撪梕栺1.5倢偺墌摏宍偱偁傞丅堦曽丄捑崀憛偱暘棧偝傟偨忋悷塼偼億儞僾偱妶惈扽傪廩?偟偨扙拏慺摏偵憲傝丄儊僞僲亅儖傪揧壛偟偨偺偪扙拏慺張棟傪峴偆丅廩?偟偨妶惈扽偼婎慴帋尡偲摨偠價乕僘忬妶惈扽偱偁傞丅
丂巊梡偟偨徤壔嬠偍傛傃扙拏慺嬠偼丄摉帋尡強偺嬤朤偵嶶嵼偡傞栰嵷敤偺偛偔昞憌傛傝嵦庢偟丄廤愊攟梴傪峴偭偨傕偺偱偁傞丅
丂傾儞儌僯傾僀僆儞偺暘愅偼僀儞僪僼僃僲乕儖惵朄偵傛傝丄徤巁僀僆儞偺暘愅偼僋儘儌僩儘乕僾巁朄偵傛傝丄傑偨丄儊僞僲乕儖偺暘愅偼搰捗惢嶌強惢GC亅7A宆僈僗僋儘儅僩僌儔僼傛傝丄廩?嵻偲偟偰TenexGC傪梡偄偰丄偦傟偧傟暘愅偟偨丅
丂3丏幚尡寢壥偍傛傃峫嶡
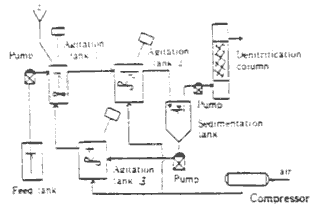
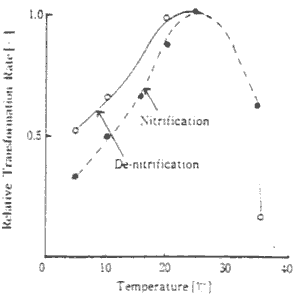
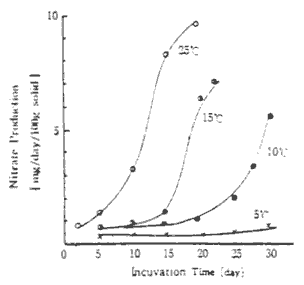
丂(1)僇儔儉帋尡
丂徤壔嬠偺幚尡寢壥傪恾III亅2偵帵偡丅徤壔嬠偺廫暘偵晅拝偟偨僇儔儉帋尡偵傛傞偲丄徤壔斀墳偼20乣25亷晬嬤偵嵟揔側壏搙斖埻偑懚嵼偟丄偙傟傛傝壏搙偑掅壓偡傞偲嫟偵徤壔擻椡偼偄偪偠傞偟偔掅壓偡傞丅偟偐偟丄50亷偵偍偄偰傕傑偭偨偔徤壔擻椡偑掆巭偡傞傢偗偱偼側偔丄25亷偺偲偒30亾埲忋偺張棟擻椡傪傕偭偰偄傞丅
丂偙偙偱栤戣偲側傞偙偲偼丄徤壔嬠傪偁傜偐偠傔彮検揧壛偟偨偺傒偱徤壔帋尡傪峴偆偲偒丄斀墳壏搙傪5亷偵愝掕偡傞偲丄傾儞儌僯傾偺徤壔偑傎偲傫偳恑峴偟側偄偙偲偱偁傞丅偡側傢偪丄妶惈墭揇張棟偺傛偆偵BOD巁壔嬠偑嫟懚偡傞忦審偺傕偲偱偼丄徤壔嬠偼悽戙帪娫偑挿偄偙偲偐傜傒偰丄5亷偱偼乬Washout乭尰徾偵傛傝嬠偑棳弌偟尭彮偡傞偺偱丄徤壔張棟傪峴偆偙偲偑晄壜擻偵側傞傕偺偲悇掕偝傟傞丅
丂師偵丄扙拏慺嬠偺幚尡寢壥傪恾III亅3偵帵偡丅扙拏慺嬠偼掅壏搙偵偍偄偰偼丄嵟揔壏搙椞堟偵偔傜傋偰丄扙拏慺擻椡偼掅壓偡傞傕偺偺丄5亷偵偍偄偰傕嬠懱偺崌惉乮憹怋乯偼廫暘偵峴傢傟傞丅5亷丄嬠懱枹朞榓偺忦審偺傕偲偱巒傔偨扙拏慺帋尡偵偍偄偰傕丄帪娫偑宱夁偡傞偵偮傟扙拏慺嬠偱朞榓偟偨僇儔儉帋尡偲摨掱搙偺扙拏慺擻椡傪帵偡丅偡側傢偪丄扙拏慺偵娭偟偰偼掅壏壓偵偍偄偰丄嵟揔壏搙偵偍偗傞傛傝傕扙拏慺擻椡偼掅壓偡傞傕偺偺丄扙拏慺張棟偼壜擻偱偁傞丅偟偐偟丄徤壔張棟偼徤壔嬠偑掅壏宑偱偼憹怋偑傎偲傫偳掆巭偡傞偙偲偐傜丄嬠懱擻搙傪堐帩偡傞岺晇偑昁梫偱偁傞丅
丂(2)楢懕帋尡
丂僛僆儔僀僩偵傛傞傾儞儌僯傾媧拝帋尡偱偼恾III亅4偵帵偡傛偆偵丄僀僆儞嫮搙偺彫偝偄偲偒偵偼丄摿偵偦偺岠壥偺偄偪偠傞偟偄偙偲偑傢偐傞丅
丂旝惗暔傪梡偄傞傾儞儌僯傾偺徤壔憖嶌偵偍偄偰丄棷堄偟側偗傟偽側傜側偄揰偼丄徤壔嬠偼悽戙帪娫偑挿偔乮10乣30帪娫乯丄傑偨丄廬懏塰梴嬠偵偔傜傋偰嬠懱廂棪偑偒傢傔偰彫偝偄偙偲偱偁傞丅偙偺偨傔丄徤壔偵偼挿偄墭揇椷傪昁梫偲偡傞丅傑偨丄BOD巁壔嬠偵偔傜傋偰丄奜奅偺偝傑偞傑側場巕偵傛傞塭嬁傪庴偗傗偡偔丄娐嫬偺曄壔偵偒傢傔偰晀姶偵斀墳偡傞揰偱偁傞丅偦偺塭嬁偼徤壔嶌梡傛傝傕丄偙傟傪搚戜偵偟偰恑峴偡傞擇巁壔扽巁偐傜惗懱惉暘傪崌惉偡傞嶌梡偺曽偑丄偼傞偐偵塭彂傪庴偗傗偡偄丅偙偺偨傔丄掅壏壓偱旝惗暔偵傛傞徤壔傪埨掕偵峴偆偨傔偵偼丄徤壔嬠偺棳幐傪嬌椡杊巭偟丄偐偮嬠懱偺憹怋傪偼偐傞昁梫偑偁傞丅偦偺偨傔偵偼張棟偺懳徾偲側傞尨悈偵嵟揔側張棟曽朄傪慖偽側偗傟偽側傜側偄丅
丂杮帋尡偵憐掕偟偨棳擖悈偼丄慜抜張棟偲偟偰丄旝惗暔張棟乮妶惈墭揇張棟乯傪庴偗偰偍傝丄桳婡懺拏慺偼傎偲傫偳懚嵼偣偢丄BOD50噐乛l埲壓丄NH4亅N20噐乛l埲壓偲偡傞丅偦偙偱僛僆儔僀僩偺慖戰揑側傾儞儌僯傾僀僆儞媧拝擻椡偲丄徤壔岺掱傪張棟悈偺庡棳偐傜愗傝棧偟丄徤壔嬠偺棳幐傪偼偐傞偙偲偲偟偨丅偙偙偱丄強梫僛僆儔僀僩検偼徤壔張棟岺掱偐傜棳弌偟偰偄偔張棟悈拞偺傾儞儌僯傾擹搙傪婯掕偡傞偙偲偵傛傝恾III亅4偐傜梕堈偵媮傔傞偙偲偑偱偒傞丅杮曽幃偵傛傞傾儞儌僯傾彍嫀偼崅擹搙偺傾儞儌僯傾娷桳悈傪懳徾偲偡傞偲偒偼丄僛僆儔僀僩偺揧壛検偑戝偒偔側傝丄揔梡偼擄偟偄傕偺偲峫偊傜傟傞丅偟偐偟丄傾儞儌僯傾擹搙偑10噐乛l掱搙偺掅擹搙偺偲偒偵偼懠偺旝惗暔張棟曽朄偵偔傜傋偰弞娐悈検丄傑偨偼丄懾棷帪娫偑彫偝偔棙揰偑偁傞丅恾III亅5偵偼弞娐悈検偲枹張棟傾儞儌僯傾擹搙偲偺娭學傪帵偟偨丅COD嫟懚壓偱偺弞娐悈検偲偺娭學偼柧妋偱偼側偄偑丄COD70乣210噐乛l偺斖埻偱偼丄偍傛偦90亾埲忋偺彍嫀棪偑摼傜傟偨丅傑偨丄傾儞儌僯傾偺彍嫀棪偼弞娐棪偑憹偡偵偮傟偰岦忋偟偨丅
丂僛僆儔僀僩傪徤壔憛偵搳擖偟偰丄徤壔丄媧拝傪摨堦憛撪偱峴偆曽幃丄偡側傢偪丄僛僆儔僀僩傪傾儞儌僯傾張棟偵偍偗傞娚徴嵻偲偟偰梡偄傛偆偲偡傞帋傒偑偁傞丅偙偺応崌憛撪偺僛僆儔僀僩偑偮偹偵張棟悈拞偺傾儞儌僯傾擹搙偲媧拝暯峵偺忬懺偱懚嵼偡傞偨傔丄徤壔憛撪偵偍偗傞旝惗暔偵傛傞徤壔懍搙丄棳擖悈拞偺傾儞儌僯傾擹搙偺曄摦側偳偺梫場偱丄傾儞儌僯傾偺彍嫀棪偑晄埨掕偲側傝丄張棟悈拞偺傾儞儌僯傾擹搙偼曄摦偡傞偙偲偵側傞丅張棟憛拞偺僛僆儔僀僩偺堦晹傪敳偒弌偟偰傾儞儌僯傾偺廫暘側扙拝傪偼偐傞偙偲偵傛傝丄僛僆儔僀僩偼媧拝擻椡傪夞暅偟丄傛傝埨掕側憖嶌偑婜懸偱偒傞偙偲偵側傞丅偙偺傛偆側峫偊偵棫偪丄潣漚憛3傪愝偗丄嵞敇婥傪峴偆偙偲偵傛傝丄僛僆儔僀僩偺傾儞儌僯傾媧拝擻椡偺夞暅傪偼偐傞偙偲偑偱偒傞丅
丂張棟憰抲撪偺僛僆儔僀僩擹搙偼丄廳梫傪憖嶌場巕偺堦偮偱偁傞丅偦偺幚尡寢壥傪恾III亅6偵帵偡丅幚攔悈偺僀僆儞嫮搙偼恾III亅4偺偍傛偦A亅B偺斖埻偵偁傞偲峫偊傜傟傞偲偙傠偐傜丄杮帋尡偺摉弶偺張棟栚昗偱偁傞傾儞儌僯傾擹搙2mg乛l埲壓傪棳弌擹搙偲婯掕偡傞偲丄僛僆儔僀僩偺岎姺梕検偼弮悈傪梡偄偨応崌偺傾儞儌僯傾岎姺梕検偺偍傛偦1/3乣1/4偵掅壓偟丄僛僆儔僀僩1僌儔儉偁偨傝偺傾儞儌僯傾媧拝検偼悢儈儕僌儔儉偵側傞傕偺偲悇掕偝傟傞丅
丂埲忋偺寢壥傪傑偲傔傞偲掅壏搙偱偼丄扙拏慺張棟擻椡偼帄揔壏搙偺偲偒傛傝掅壓偡傞偑丄張棟偼壜擻偱偁傞丅偟偐偟丄徤壔張棟偱偼丄掅壏搙偵偍偄偰徤壔嬠偺憹怋懍搙偑嬌傔偰彫偝偄偨傔丄徤壔嬠偺擹搙傪堐帩偡傞偨傔偺岺晇偑昁梫偱偁傞丅
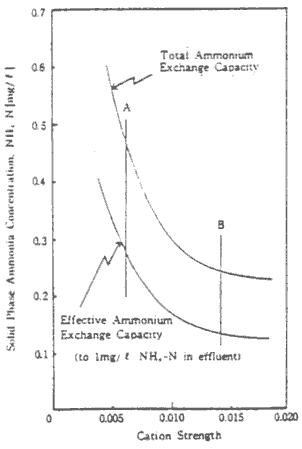
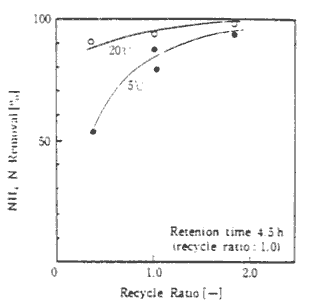
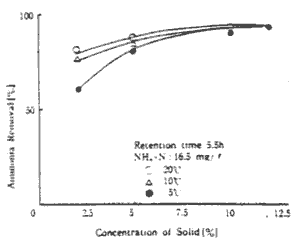
丂
丂IV 扙儕儞傪栚揑偲偟偨媧拝傠夁張棟
丂1丏傑偊偑偒
丂偙偺曬崘偼丄姦椻抧宆崅搙悈張棟僾儘僙僗偺堦娐偲偟偰丄扙儕儞傪栚揑偲偟偨媧拝傠夁朄偵偮偄偰丄偦偺慜張棟偲偟偰暋憌傠夁抮偵傛傞愙怗嬅廤朄偺揔惓忦審傪尒弌偟丄偮偄偱懡抜傠夁懠偵傛傞媧拝傠夁朄偵偮偄偰専摙偟偨傕偺偱偁傞丅
丂2丏暋憌傠夁抮偵傛傞愙怗嬅廤朄
丂(1)栚揑
丂扙儕儞傪栚揑偲偟偨媧拝傠夁張棟傪幚巤偡傞偵偁偨傝丄懳徾悈偍傛傃張棟岺掱摍偐傜偐側傝偺晜梀暔偑梊憐偝傟偨偺偱丄暋憌傠夁抮偵傛傞愙怗嬅廤朄偲偟偰偼丄1乯崅戺幙偺尨悈偱傕崅懍傠夁偑壜擻偱偁傞丄2乯嵟彫偺僐僗僩偱嵟崅偺悈幙偑摼傜傟丄張棟擻椡偑憹戝偡傞丄3乯愻忩悈検偑彮側偄偲偄偆摿挜傪傕偮媡棻搙慻惉偺暋憌傠夁抮傪梡偄偨丅傑偨丄儕儞彍嫀偵偮偄偰偼丄懡検偺僗儔僢僕傪攔弌偡傞廬棃偺嬅廤捑揳朄偵戙傞怴偟偄張棟媄弍偺奐敪偑昁梫偱偁偭偨偑丄1乯摿桳側媧拝傪峴偆揤慠暔幙摍偺専嶕偑暿搑偵峴傢傟偰偄偨丄2乯掅戺幙偺彍嫀傪栚揑偲偡傞愙怗嬅廤朄偱偼丄嬅廤嵻偵傛傞摨帪彍嫀偲偟偰偺扙儕儞岠壥偑婜懸偝傟偨偙偲側偳偐傜丄媧拝嵽傪庡懱偲偡傞挜抜張棟憰抲傊偺儕儞擹搙晧壸偺掅尭壔傪峫椂偟偨愙怗嬅廤朄傪梡偄偨丅偙傟傜偺扙儕儞張棟偼丄慜抜張棟偲偟偰扙儕儞棪傪60亾偲偡傞栚昗抣傪愝掕偟偰峴傢傟偨丅
丂(2)幚尡曽朄
丂慜弎偺愝掕忦審偵偍偗傞扙儕儞岠壥傪媮傔傞偨傔丄暋憌傠嵽偲偟偰傾儞僗儔僒僀僩丄宂嵒傪梡偄丄扙儕儞傠夁摿惈偵昁梫側暔棟壔妛揑側梫慺乮傠憌斾丄傠夁懍搙丄嬅廤嵻拲擖検摍乯偵偮偄偰偺婎慴幚尡傪峴偄丄儕儞偺彍嫀棪亾偵偍偗傞僆儁儗乕僔儑儞僷儔儊乕僞乕偐傜惗嶻悈検傪媮傔丄扙儕儞岠壥偍傛傃傠夁擻椡傪専摙偟偨丅
丂幚尡曽朄偼埲壓偺擛偔偱偁傞丅
丂(a)傠夁憰抲
丂僼傿儖僞乕僇儔儉偼奐曻宆媫懍傠夁曽幃偱丄撪宎155噊丄崅偝3,400噊偺墫價偲傾僋儕儖惢偱丄張棟悈検偼嵟戝0.2m3/hr偱偁傞丅嵎埑應掕梡僞僢僾偼200噊娫妘偵6働強丄尨悈棳擖岥偼忋晹懁柺乮儅僀僋儘僼僢僋朄梡乯偲壓晹懁柺乮愙怗嬅廤朄梡乯偵愝偗偨丅偙偺憰抲偼掕悈摢偺掕懍偱塣揮偝傟傞偺偱忋晹偵堨棳岥偑偁傞丅
丂(b)寁應丒惂屼憰抲
丂偙偺憰抲偼丄棳検寁應惂屼丄嵎埑寁應丄戺搙寁應丄pH寁應惂屼憰抲傛傝峔惉偝傟偰偄傞丅嬅廤忦審傪僐儞僩儘乕儖偟丄僆儁儗乕僔儑儞僼傽僋僞乕傪帺摦楢懕婰榐偡傞丅
丂(c)暘愅曽朄
丂儕儞壔崌暔乮PO4亅P乯偺暘愅偼丄岺応攔悈帋尡朄乮JIS亅KOlO2乯偵傛傞斾怓朄傪梡偄丄擔棫101宆暘岝岝搙寁偱應掕偟偨丅嬅廤嵻偺AI検偵偮偄偰偼丄摨條偵JIS亅KOlO2偵傛傞尨巕媧岝朄傪梡偄丄僶儕傾儞僥僋僩儘儞AA亅1100宆尨巕媧岝憰抲偱應掕偟偨丅
丂(d)幚尡忦審
丂幚尡梡尨悈偵梡偄偨儌僨儖悈偼丄悈摴悈偵儕儞惉暘偲偟偰儕儞巁1僇儕僂儉傪揧壛偟丄PO4亅P擹搙傪4丒5亇0.5噐/l偵挷惍偟偨傕偺偱偁傞丅嬅廤嵻偲偟偰棸巁傾儖儈僯僂儉傪梡偄丄揧壛偡傞擹搙偼丄JarTest偍傛傃嬅廤嵻揧壛検偵傛傞傠夁摿惈偺梊旛幚尡寢壥偐傜峫椂偟偰AI5噐/l偲偟偨丅傑偨丄pH偺挷惍偼悈巁壔僫僩儕僂儉傪梡偄丄愝掕抣7.0偵帺摦惂屼偟偨丅幚尡偵懏偄偨傠憌偼丄忋晹偵傾儞僗僒僀僩丄壓晹偵宂嵒傪傠彴巟帩梡嵒棙憌忋偵晘偄偰峔惉偟偨丅傠憌慡岤偼丄900噊偲偟丄傠憌斾乮傾儞僗儔丗宂嵒乯傪奺乆1丗1丄2丗1丄3丗1偲偟偨丅僆儁儗乕僔儑儞僷儔儊乕僞乕偲偟偰偼丄傠夁懍搙丄嵎埑丄戺搙傪梡偄偨丅傠夁懍搙偼5m/hr丄7.5m/hr丄10m/hr丄嵎埑偼嵟戝嫋梕懝幐悈摢傪3m丄戺搙傠夁悈戺搙傪5噐/l偲偟偰楢懕婰榐偟偨丅愻忩憖嶌偼丄嵎埑偍傛傃戺搙偺愝掕婎弨抣傑偨偼儕儞彍嫀棪60亾埲壓偺抣偺偄偢傟偐偑帵偝傟偨応崌丄幚尡傪掆巭偟偰媡棳愻忩傪峴偭偨丅
丂(3)幚尡寢壥偲峫嶡
丂傠憌斾偍傛傃傠夁懍搙偵傛傞扙儕儞傠夁摿惈傪偦傟偧傟恾IV亅1偍傛傃IV亅2偵帵偟偨丅偙偺寢壥偐傜丄儕儞彍嫀棪60亾偵偍偗傞暋憌愙怗嬅廤偺傠夁摿惈偲偟偰丄埲壓偺偙偲偑敾柧偟偨丅
丂(a)傠憌斾乮傾儞僗儔丗宂嵒乯1丗1丄傠夁懍搙5m/hr偺応崌丄惗嶻悈検40m3/ m2偺嵟戝抣傪帵偟偨丅
丂(b)摨堦傠憌斾偱偼丄傠夁懍搙偺憹壛偲偲傕偵惗嶻悈検偼尭彮偟丄尭彮棪偼37.5乣70.6亾傪帵偟偨丅
丂(c)傠憌斾傪1丗1丄2丗1偍傛傃3丗1偲曄偊偨応崌丄忋晹傾儞僗儔憌偑岤偔側傞傎偳摨堦傠夁懍搙偺惗嶻悈検偼掅壓偡傞孹岦偵偁傞偑丄2丗1偐傜3丗1偺夁掱偱偼丄摨堦偐丄傑偨偼憹壛傪帵偟偨丅
丂(d)AI/P儌儖斾偼1.03乣1.18偺斖埻偱峴傢傟偨偑丄弶婜偵偼70乣90亾偺儕儞彍嫀棪傪帵偟偨丅傑偨儕儞彍嫀棪60亾偵嬤偯偔偲嬅廤嵻AI偺楻弌偑尒傜傟偨丅
丂(e)嵎惓偵偮偄偰偼丄傠夁懍搙偺憹壛偍傛傃傠憌斾偵偍偗傞傾儞僗儔憌偺憹壛偲偲傕偵忋徃偡傞岡攝偑戝偒偔側傞孹岦傪帵偟偨丅
丂埲忋憤崌揑側寢壥偐傜儕儞壔崌暔60亾彍嫀偵偍偗傞暋憌偵傛傞愙怗嬅廤偺嵟揔側忦審偲偟偰偼丄傠憌斾乮傾儞僗儔丗宂嵒乯1丗1丄傠夁懍搙5m/hr丄AI/P儌儖斾偺1.0乣1.2丄pH7.0偑懨摉偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅
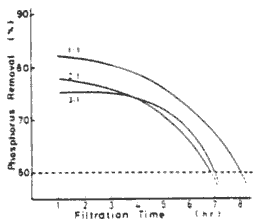
| 儕儞壔崌暔 | 4.5亇0.5mg/l |
| 傾儖儈嵻 | 4.5亇0.5mg/l |
| 嬅廤忦審 | pH7.0亇0.2 |
| 傠懍 | 5m/hr |
| 憌斾 | 3:1丄2:1丄1:1 |
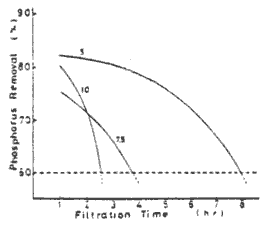
| 儕儞壔崌暔 | 4.5亇0.5mg/l |
| 傾儖儈嵻 | 4.5亇0.5mg/l |
| 嬅廤忦審 | pH7.0亇0.2 |
| 傠懍 | 5丄7.5丄10m/hr |
| 憌斾 | 1:1 |
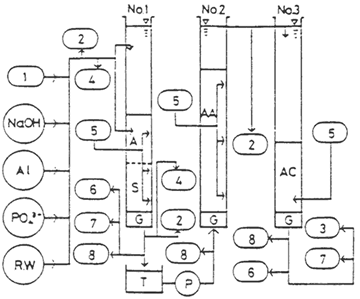
丂
丂3丏懡抜傠夁抮偵傛傞媧拝傠夁朄
丂(1)栚揑
丂堦斒偵扙儕儞傪栚揑偲偡傞傠夁張棟朄偼丄攔悈偺崅搙張棟偺柺乮嬅廤捑揳張棟偺寚娮丄張棟旓偺掅尭壔丄憰抲偺娙堈壔摍乯偐傜嬅廤傠夁僔僗僥儉傪揔梡偡傞孹岦偵偁傞丅偙傟傜偼丄傠憌偺峔惉傪扨憌偲偡傞怺憌傠夁乮慹棻搙慻惉丄傑偨偼丄峔惉傪懡憌偲偡傞暋憌傠夁丄嶰憌傠夁偄偢傟傕媡棻搙慻惉乯側偳傪巊梡偟偰偄傞丅
丂偟偐偟丄儕儞擹搙偺婯惂抣傪枮懌偝偣傞彍嫀偺偨傔偵偼丄傠夁偺摿惈乮傠夁岠棪偵偍傛傏偡尨悈偲傠夁偺僷儔儊乕僞乕偲偺憡屳嶌梡摍偍傛傃儕儞彍嫀偵塭嬁傪梌偊傞彅場巕乮儕儞偺宍懺丄儕儞検偵懳偡傞嬥懏墫偺儌儖斾丄pH摍乯偺柺偐傜崲擄偑梊憐偝傟傞丅
丂偙傟傜偺懪奐嶔偲偟偰丄戞堦抜傠夁偐傜戞擇抜傠夁傊偲懡抜壔偡傞曽朄偑峫偊傜傟傞丅偡側傢偪戞擇抜埲崀傪媧拝嵽偵傛傞媧拝憖嶌偲偡傞曽朄偱偁傞丅偙偙偱偼丄儀儞僠僗働乕儖偵傛傞幚攔悈傪懳徾偲偟偨楢懕帋尡偵偮偄偰傑偲傔偨傕偺偱偁傞丅
丂(2) 幚尡曽朄
丂(a) 楢懕憰抲
丂幚尡偵梡偄偨楢懕憰抲偼恾IV亅3偵帵偟偨傛偆偵3婎偺寴宆搩傪楢寢偝偣偨傕偺偱峔惉偝傟傞丅偟偐偟丄幚攔悈偵傛傞慡岺掱乮桘暘張棟丄妶惈墭揇張棟丄徤壔扙拏張棟丄扙儕儞張棟乯偺楢懕塣揮偱偼丄奺岺掱偵梡偄傞憰抲偺張棟検偑嬒堦偱側偔丄傾儞僶儔惀惓偺偨傔偵嵟彫梕検偺憰抲偵崌偣偨偨傔丄嵟廔岺掱偵偍偗傞憰抲憖嶌偺彅尦偍傛傃栚昗抣偵偮偄偰傕晹暘揑偵曄峏偟偨丅戞堦抜傠夁憰抲偱偼傠夁懍搙乮LV乯3.5m/hr丄張棟検66.2倢/hr偲偟丄栚昗偼彍戺棪90亾埲忋丄扙儕儞60亾埲忋偱偁傞丅戞擇抜傠夁憰抲偱偼憌崅1,900噊丄嬻娫懍搙乮SV乯1.8偲偟栚昗偼扙儕儞棪乮戞堦抜丄戞擇抜傪娷傔偰乯80亾埲忋偱偁傞丅戞嶰抜傠夁憰抲偱偼憌崅900噊偲偟丄栚昗偼扙儕儞乮戞堦抜偐傜戞嶰抜傑偱娷傔偰乯90亾埲忋偱偁傞丅悈幙偵偮偄偰偼攔悈婎弨抣埲壓傪栚昗偲偟偨丅
丂(b)寁應惂屼憰抲
丂(c)帺摦儕儞暘愅憰抲
丂(d)暘愅曽朄
丂埲忋丄慜崁偲摨條偱偁傞丅
丂(e)幚尡忦審
丂幚攔悈偼壓悈1師張棟悈傪儀乕僗偲偟偰丄揔媂僐乕儞僗僠乕僾儕僇乕乮CSL乯丄擕壔摂桘丄僌儖僐乕僗摍傪揧壛偟偨傕偺傪巊梡偟偨丅幚攔悈偵偮偄偰偼桘暘100mg乛l丄COD500乣1,000mg乛l偺傕偺傪張棟偡傞寁夋偱偁偭偨丅廬偭偰丄偙傟傜偺晄懌偡傞惉暘偍傛傃擹搙傪挷惍偟偨丅S亅1僔儕乕僘偼壓悈1師張棟悈乮500l乯偵CSL乮0.9倢乯傪揧壛偟偰挷惍偝傟偨幚攔悈偱偁傞丅S亅2僔儕乕僘偼壓悈1師張棟悈乮500倢乯偵CSL乮0.4l乯偲僌儖僐乕僗乮180倗乯傪揧壛偟偰挷惍偝傟偨幚攔悈偱偁傞丅扙儕儞岺掱偱偼丄偙傟傜偺幚攔悈偺徤壔扙拏張棟悈偑梡偄傜傟偨丅嬅廤嵻偲偟偰偼棸巁傾儖儈僯僂儉傪梡偄丄揧壛偡傞擹搙偼AI偲偟偰6.0亇0.4噐/倢偲偟偨丅嬅廤忦審偼pH7.0偲偟丄悈巁壔僫僩儕僂儉偵傛傝挷惍傪峴偭偨丅楢懕憰抲偺僆儁儗乕僔儑儞僷儔儊乕僞乕偼儌僨儖悈偺応崌偲摨堦偱偁傞丅戞堦抜傠夁憰抲偵偍偄偰愝掕婎弨抣乮傠夁懍搙3.5m/hr埲壓丄偦偺懠偼曄傜側偄乯偵払偡傞偲憰抲奺抜偺塣揮傪掆巭偟偰1僒僀僋儖偲偟偨丅愻忩憖嶌偍傛傃愻忩偼慜崁偲摨堦偱偁傞丅帋悈偼尨悈乮徤壔扙拏張棟悈乯偍傛傃憰抲奺抜偺弌岥偱1帪娫枅偵嵦悈偟丄PO4亅P丄AI摍偵偮偄偰應掕傪峴偭偨丅
丂(3)幚尡寢壥偲峫嶡
丂扙儕儞張棟岺掱偺楢懕帋尡寢壥傪昞IV亅1偵帵偟偨丅S亅1僔儕乕僘偵偍偗傞徤壔扙拏張棟悈偺惈忬偼丄戺搙51.5mg/l丄PO4亅P21.5噐/l偱偁傞丅戞堦抜傠夁張棟偱偼丄尨悈擹搙乮PO4亅P乯偑崅偔丄AI/P儌儖斾乮0.3乯偑彫偝偄偨傔丄張棟岠壥偑掅壓偟偰偄傞丅戞擇抜傠夁張棟偱偼丄崅擹搙椞堟乮PO4亅P乯偵偍偗傞妶惈傾儖儈僫偺張棟岠壥偑尠挊偱偁傞丅戞嶰抜傠夁張棟偱偼丄掅擹搙椞堟乮PO4亅P乯偵偍偗傞妶惈扽偵傛傞張棟岠壥偑尒傜傟傞丅彍戺偵偮偄偰偼戞堦抜傠夁張棟偵偍偗傞嬅廤岠壥偑旕忢偵戝偒偄丅
丂S亅2僔儕乕僘偵偍偗傞徤壔扙拏張棟悈偺惈忬偼丄擹搙54.9噐乛l丄PO4亅P2.36噐/l偱偁傞丅戞堦抜傠夁張棟偱偼丄尨悈擹搙乮PO4亅P乯偑掅偔丄AI/P儌儖斾乮2.5乯偑戝偝偄偨傔丄張棟岠壥偑椙岲偱偁傞丅戞擇抜傠夁張棟偱偼丄掅擹搙椞堟乮PO4亅P乯偵偍偗傞妶惈傾儖儈僫偺張棟岠壥偑晄椙偱偁傞丅戞嶰傠夁張棟偵偮偄偰偼丄(PO4亅P)偺抣偑憹壛偟偰偄傞丅尨場偵偮偄偰偼晄柧偱偁傞丅彍戺偵偮偄偰偼丄尨悈戺搙偑S亅1僔儕乕僘偲傎偲傫偳摨偠側偺偱丄孹岦傕摨堦偱偁偭偨丅
丂埲忋偺幚尡偵偍偄偰戞堦抜傠夁張棟偵偍偗傞扙儕儞岠壥偼丄AI/P儌儖斾偵傛傞塭嬁偑尠挊偱偁傞丅傑偨彍戺岠壥偵偮偄偰偼丄愙怗嬅廤偵傛傝椙岲側寢壥偑摼傜傟偨丅戞擇抜傠夁張棟偵偍偗傞扙儕儞岠壥偼丄掅壏搙椞堟偱偺彍嫀懍搙偺塭嬁偑尒傜傟傞丅戞嶰抜傠夁張棟偵偍偗傞扙儕儞岠壥偼丄崅擹搙椞堟偱偼枮懌偡傋偒寢壥偑摼傜傟偨丅
丂
| 尨悈 | 堦師壓悈+CSL |
| 棳擖悈 | 扙拏憌傛傝 |
| PO4-P | 21.5mg/l(AV) |
| 戺搙 | 51.5mg/l(AV) |
| 丂 | 侾抜傠夁搩 | 俀抜傠夁搩 | 俁抜傠夁搩 | |
| 儕儞壔崌暔 | 棳弌偟偨PO4-P(mg/l) | 10.8 | 1.78 | 0.81 |
| 丂 | 奺搩偺彍嫀擹搙(mg/l) | 10.7 | 9.02 | 0.97 |
| 丂 | 幚應抧(%) | 49.8 | 93.7 | 96.2 |
| 丂 | 愝掕抣(%) | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
| 戺搙 | 棳弌戺搙(mg/l) | 3.5 | 3.3 | 2.8 |
| 丂 | 慡彍嫀棪(%) | 93.2 | 93.6 | 94.6 |
丂
| 尨悈 | 堦師壓悈+CSL+僌儖僐乕僗 |
| 棳擖悈 | 扙拏憌傛傝 |
| PO4-P | 2.36mg/l(AV) |
| 戺搙 | 54.9mg/l(AV) |
| 丂 | 侾抜傠夁搩 | 俀抜傠夁搩 | 俁抜傠夁搩 | |
| 儕儞壔崌暔 | 棳弌偟偨PO4-P(mg/l) | 0.57 | 0.35 | 0.62 |
| 丂 | 奺搩偺彍嫀擹搙(mg/l) | 1.79 | 0.22 | - |
| 丂 | 幚應抧(%) | 75.8 | 85.2 | 73.7 |
| 丂 | 愝掕抣(%) | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
| 戺搙 | 棳弌戺搙(mg/l) | 2.5 | 2.1 | 1.3 |
| 丂 | 慡彍嫀棪(%) | 95.4 | 96.2 | 97.6 |
丂
丂V 掅壏椞堟偵偍偗傞妶惈僗儔僢僕偺摿惈
丂1丏傑偊偑偒
丂杒奀摴偺傛偆側愊愥姦椻抧偵偍偄偰丄妶惈僗儔僢僕朄傪嵦梡偡傞応崌丄搤婜娫偱偼悈壏掅壓偺偨傔偵丄攑悈張棟擻椡偺掅壓偁傞偄偼旝惗暔憡偺曄壔偵傛傞屌塼暘棧偺埆壔側偳偑惗偠傗偡偔側傞丅偙傟傜偺栤戣傪杊偖偵偼丄妶惈僗儔僢僕偑掅壏壓偱嵟戝擻椡傪敪婗偱偒傞傛偆傪廩暘側娗棟傗撻梴偑昁梫偵側傞丅杮嬝偵偍偄偰偼丄掅壏壓偱妶惈僗儔僢僕偑廩暘側擻椡傪敪婗偱偒傞傛偆側撻梴曽朄傪専摙偟丄傑偨媫寖側壏搙曄壔偵懳偡傞妶惈僗儔僢僕偺嫇摦偵偮偄偰傕専摙偟偨丅
丂2丏幚尡憰抲偲曽朄
丂巊梡偟偨幚尡憰抲偼恾V亅1偵帵偟偨丅悈壏掅壓偵敽偆妶惈僗儔僢僕偺婎幙彍嫀擻椡偲巁慺徚旓検傪抦傞偨傔偺幚尡曽朄傪丄埲壓偺2捠傝偱峴偭偨丅
丂僌儖僐乕僗亄儁僾僩儞傪桳婡惉暘偲偡傞恖岺壓悈傪梡偄20亷偱挿婜娫夞暘幃偱攟梴偟偨妶惈僗儔僢僕傪
丂1乯悈壏傪堦搙偵5亷傑偱壓偘偰丄偦偺30擔娫攟梴偟偨応崌丅
丂2乯枅擔彮偟偢偮悈壏傪壓偘偰丄30擔娫偱5亷傑偱壓偘偨応崌丅
丂媫寖側壏搙曄壔偵懳偡傞妶惈僗儔僢僕偺摿惈傪抦傞偨傔偺幚尡曽朄偼埲壓偺2捠傝偱峴偭偨丅
丂1乯7亷偱1働寧埲忋僌儖僐乕僗亄儁僾僩儞傪桳婡惉暘偲偡傞恖岺壓悈傪梡偄丄挿婜娫夞暘幃偱攟梴偟偨妶惈僗儔僢僕傪20亷偵媫寖偵壏搙傪忋偘偰丄1帪娫偍傛傃24帪娫屻偵婎幙傪夞暘揑偵揧壛偟丄偦偺屻偺婎幙彍嫀懍搙偲巁慺徚旓検傪應掕偟偨丅
丂2乯摨偠恖岺壓悈傪梡偄丄20亷偱1働寧埲忋夞暘幃偱攟梴偟偨妶惈僗儔僢僕傪媫寖偵7亷傑偱壏搙傪壓偘偰丄1帪娫偍傛傄24帪娫屻偵偦傟偧傟婎幙傪夞暘揑偵揧壛偟丄偦偺屻偺婎幙彍嫀懍搙偲巁慺徚旓検傪應掕偟偨丅
丂3丏幚尡寢壥偲峫嶡
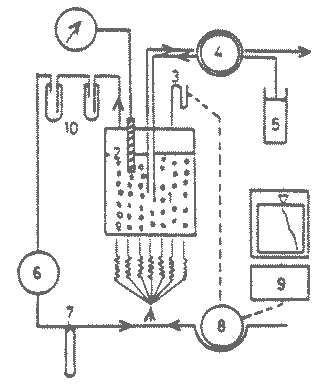
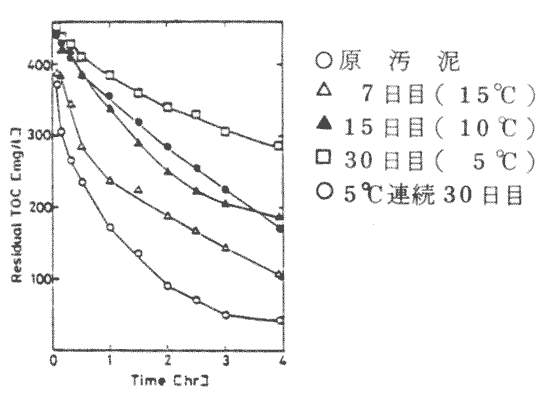
丂
丂恾V亅2偼丄悈壏掅壓偵敽偆妶惈僗儔僢僕偺婎幙彍嫀懍搙偲巁慺徚旓検傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅堦搙偵5亷傑偱悈壏傪壓偘偰30擔娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偺曽偑丄枅擔彮偟偢偮壏搙傪壓偘偰30擔娫偱5亷傑偱壓偘偨妶惈僗儔僕傛傝傕TOC偺彍嫀擻椡偑椙偄偙偲偑傢偐偭偨丅恾V亅3偼媫寖側壏搙曄壔偵懳偡傞妶惈僗儔僢僕偺婎幙彍嫀懍搙偺曄壔傪帵偟丄恾V亅4偼偦偺帪偺巁慺徚旓懍搙嬋慄偲巁慺徚旓検傪帵偟偰偄傞丅
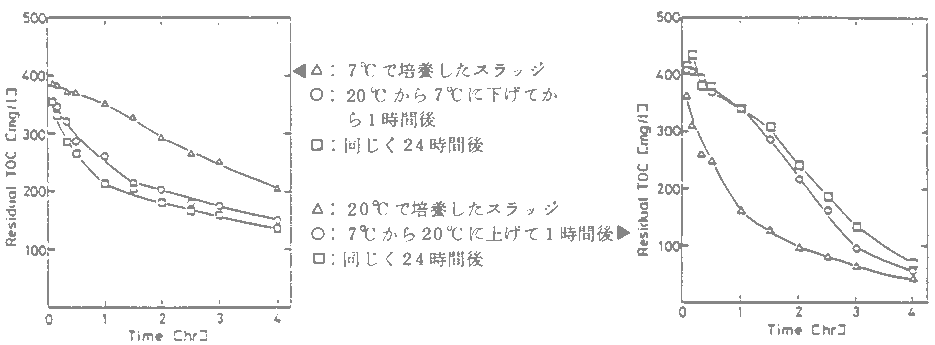
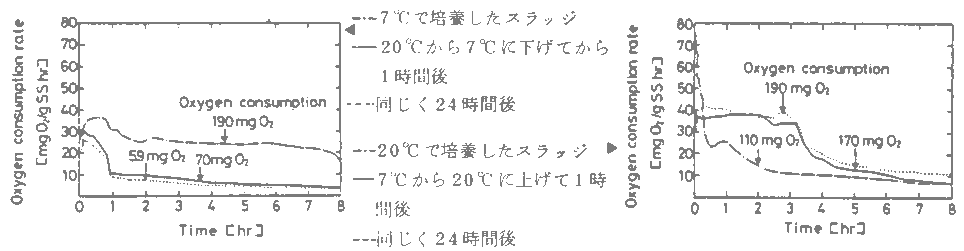
丂
丂1乯20亷偱挿婜娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕傪丄媫寖偵壏搙傪壓偘偰7亷偵娐嫬傪曄壔偝偣偨応崌丄7亷偱挿婜娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偵斾傋偰丄婎幙偼懍偔彍嫀偝傟傞偑丄TOC彍嫀検摉傝偺巁慺徚旓検偼彮側偔丄7亷偱撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偺栺1/3掱搙偱偁偭偨丅
丂2乯7亷偱挿婜娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偼丄媫寖偵壏搙傪忋徃偝偣偰20亷偵娐嫬傪曄壔偝偣偰傕丄20亷偱挿婜娫撻梴偟偰偄偨妶惈僗儔僢僕偵斾傋偰婎幙彍嫀擻椡偼掅偔丄傑偨丄TOC彍嫀検摉傝偺巁慺徚旓検偼戝偒偔丄20亷偱撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偺栺2攞掱搙偵側偭偨丅
丂師偵偦傟傜偺寢壥偵偮偄偰峫嶡傪壛偊傞丅
丂1乯掅壏壓偱攑悈張棟傪峴偆応崌丄摨偠撻梴婜娫傪偐偗傞偲偡傟偽丄忢壏偱攟梴偟偰偄偨妶惈僗儔僢僕傪彊乆偵壏搙傪壓偘偰偄偔曽朄傛傝傕堦搙偵掅壏偵偟偰攟梴偟偨曽偑丄掅壏壓偱偺張棟擻椡偑椙偐偭偨丅
丂2乯妶惈僗儔僢僕偵懳偡傞媫寖側壏搙曄壔偺塭嬁偼丄崱夞偺幚尡偵尷傞斖埻偱偼丄7亷偱挿婜娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偼丄20亷偱挿婜娫撻梴偟偨妶惈僗儔僢僕偵斾傋丄婎幙彍嫀擻椡偼掅偔丄扨埵婎幙彍嫀検摉傝偺巁慺徚旓検偼戝偒偐偭偨丅堦斒揑偵偼丄婎幙彍嫀検偑彮側偗傟偽巁慺徚旓検傕彮側偔側傞偲巚傢傟傞偑丄崱夞偺応崌偼堘偆寢壥偵側偭偨丅偙傟傜偺帠偐傜丄幚憰抲傪塣揮娗棟偡傞応崌丄忢偵妶惈僗儔僢僕偺婎幙彍嫀擻椡偍傛傃巁慺徚旓検傪娔帇偟丄揔愗側巁慺嫙媼傪偟側偗傟偽側傜側偄偙偲偑傢偐偭偨丅
丂VI 崅搙張棟僾儘僙僗偵傛傞楢寢帋尡
丂1丏傑偊偑偒
丂I乣IV偵弎傋偰偒偨奺扨埵憖嶌偵娭偡傞尋媶傪婎斦偲偟偰丄偙傟傜傪堦楢偺悈張棟僾儘僙僗偲偟丄楢懕帋尡傪峴偭偨丅
丂2丏帋悈偍傛傃憰抲
丂帋悈偼丄巗撪偺壓悈張棟応乮朙暯壓悈張棟応乯偺堦師張棟悈傪掕婜揑偵僞儞僋儘乕儕乕偱桝憲偟偰挋棷偟丄偙傟偵僐乕儞僗僠乕僾儕僇乕傪COD尮偵丄僄儅儖僕儑儞壔偟偨摂桘傪桘暘尮偲偟偰偦傟偧傟強掕偺擹搙偵側傞傛偆揧壛偟偰挷惍偟偨丄楢懕帋尡偼COD擹搙偺堎側傞3庬椶偺僔儕乕僘偱峴偭偨丅尨悈COD曄摦暆偼500噐/l乣1000噐/g偱偁傞丅傑偨丄張棟悈壏傪5亷偲偟奺扨埵張棟偵墬偗傞悈壏挷惍偼偦傟偧傟偵晬懏偡傞椻媝憰抲傪梡偄偰峴偄慡僾儘僙僗傪捠偠偰堦掕偺悈壏傪堐帩偡傞傛偆偵偟偨丅帋尡憰抲偼奺扨埵張棟偺尋媶偺偨傔偵帋嶌偟偨傕偺傪桘暘暘棧憰抲亅懡抜敇婥憛亅旝惗暔扙拏憰抲亅媧拝傠夁憛偺弴偵捈楍偵楢寢偟偰巊梡偟偨丅恾VI亅1偵偦偺僼儘乕僔乕僩偍傛傃僒儞僾儕儞僌億僀儞僩偺婰崋傪帵偟偨丅
丂帋尡憰抲偼丄奺扨埵張棟偺尋媶栚揑偵崌傢偣偰帋嶌偟偨偨傔張棟擻椡偑憰抲偵傛偭偰堎側傞偺偱丄憰抲娫偵挋棷憛傪愝偗偰棳検挷惍傪峴偭偨丅廬偭偰丄棳検偺戝偒側憰抲乮媧拝傠夁憰抲乯偱偼昁梫側悈検傪挋棷偡傞偺偵帪娫傪梫偟丄偦偺娫偵庒姳偺悈幙曄摦傪惗偠偨丅
丂3丏幚尡曽朄偍傛傃應掕崁栚
丂楢懕帋尡偼1擔8帪娫丄廡5擔娫偺僗働僕儏乕儖偱峴偄丄奺憰抲偑掕忢忬懺偵払偟偨帪揰偱廡1夞堦惸偵僒儞僾儕儞僌傪峴偄丄強掕偺悈幙崁栚傪暘愅偟偨丅傑偨丄偙偺娫偵奺扨埵張棟偺愝寁傗塣揮娗棟偵昁梫側僨乕僞傪廂廤偟偨丅
丂悈幙暘愅朄偼庡偲偟偰JIS亅K亅0102偵弨嫆偟偨丅傑偨丄傾儞儌僯傾懺拏慺偼僇僪儈僂儉娨尦朄偵傛傝僆乕僩傾僫儔僀僓乕偱應掕偟BOD偼愭偵摉強偱奐敪偟偨僋乕儘儊乕僞偱應掕偟偨丅
丂4丏楢懕帋尡偍傛傃峫嶡
丂楢懕張棟帋尡寢壥偺偆偪丄奺岺掱弌岥偺悈幙偍傛傃尨悈偲嵟廔張棟悈偺忋悈婎弨崁栚偵傛傞暘愅抣偺堦椺傪昞VI亅1丄2偵帵偟偨丅悈壏偼椻媝憰抲傪帩偨側偄媧拝傠夁憰抲偱庒姳忋徃偟偨偑丄懠偺岺掱偱偼5亅6亷傪堐帩偟偨丅桘暘暘棧憛偵偍偗傞桘暘彍嫀棪偼桘暘傪抧壓悈偵暘嶶偝偣偨応崌偵斾傋偰庒姳掅壓偟偨偑丄奺張棟悈偱岺掱拞偵媧拝偦偺懠偺棟桼偱彍嫀偝傟丄嵟廔張棟悈偱偼専弌偝傟側偐偭偨丅懡抜敇婥憛偵偍偗傞BOD丄COD偍傛傃TOC側偳偱昞偝傟傞桳婡暔偺彍嫀惈擻偼尠挊偱偁傞丅峏偵丄5乣6亷偺掅壏悈偱忋婰惉暘偺彍嫀棪偑偦傟偧傟95亾丄90亾偍傛傃91亾偲梊憐埲忋偺惉壥偑摼傜傟偨偙偲偼姦椻抧偵偍偗傞旝惗暔張棟偵懳偡傞怴偟偄曽岦傪帵嵈偡傞傕偺偲巚傢傟傞丅傑偨丄偙偺岺掱偱偼拏慺壔崌暔丄摿偵桳婡惈拏慺偍傛傃慡儕儞偺尪憐偑栚棫偮偑偙傟偼丄偙傟傜偺惉暘偺暔幙廂巟偐傜尒偰嬠懱傊庢傝崬傑傟偨偨傔偲巚傢傟傞丅
丂傑偨丄堦斒嵶嬠丄戝挵嬠偑偙偺岺掱偱偲傕偵90亾彍嫀偝傟偰偄傞丅師偺丄媧拝嵻暪梡偵傛傞扙拏岺掱偱偼扙拏嬠偲偟偰壓悈張棟応偺梋忚墭揇偐傜攟梴偟偨傕偺傪棻忬妶惈扽偵晅拝偝偣偨廩?搩偵偮傔偰梡偄偨偑昞VI亅1偵帵偡傛偆偵徤巁懺拏慺偑偐側傝儕乕僋偟偰偄傞丅
丂
| 崁栚乢應掕揰 | 昿搙 | 尨悈 | 懡抜敇婥 憛弌岥 | 扙拏 憛弌岥 | 媧拝傠夁 憛弌岥 |
| 亷 | D | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 |
| pH | D | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| OIL ppm | D | 98.5 | 8.3 | - | - |
| COD(T) ppm | D | 449 | 51 | 24 | 1.38 |
| COD(D) ppm | D | 430 | 43 | 220 | 丂 |
| 儼P ppm | D | 6.50 | 1.76 | 3.22 | 0.65 |
| ORG-P ppm | D | 1.76 | 0.24 | 0.47 | 0 |
| PO4-P ppm | D | 4.74 | 1.52 | 2/75 | 0.65 |
| ORG-N ppm | D | 42.5 | 6.0 | 3.2 | 1.1 |
| ORG-N(D) ppm | D | 33.3 | 5.3 | 2.8 | 0.8 |
| NH3-N ppm | D | 33 | 37.1 | 10.3 | 1.8 |
| NH3-N(D) ppm | D | 30.2 | 22.7 | 8.0 | 1.3 |
| NO2-N ppm | D | 0 | 0.02 | 0.25 | 0 |
| NO3-N ppm | D | 0.02 | 0.26 | 5.73 | 0.86 |
| TURB ppm | D | 273 | 37 | 65.2 | 0.7 |
| BOD ppm | O | 885 | 47 | 43 | 10 ppm |
| TOC(T) ppm | O | 384 | 36.6 | 19.3 | 2.2 |
| TOC(D) ppm | O | 336 | 32.0 | 17.4 | 2.2 |
| BACTERIA ct/ml | O | 49x105 | 68x104 | 27x104 | 15x102 |
| COLIFORM G. ct/ml | O | 30x103 | 26x102 | 50x103 | 13x10 |
| MLSS ppm | D | 丂 | 33.568 | 丂 | 丂 |
| SV(%) | D | 丂 | 245 | 丂 | 丂 |
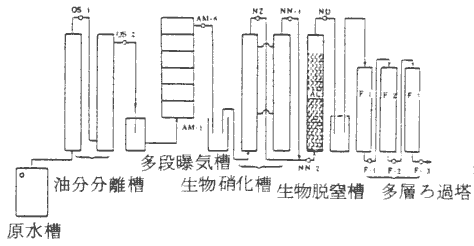
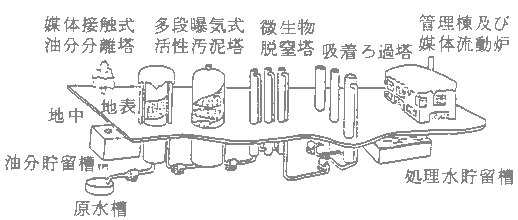
丂偙偺尨場偲偟偰丄1)捠忢巊梡偝傟偰偄傞扙拏嬠偼掅壏偱偼妶惈偑掅壓偡傞丅2)張棟棳検傪懠偺岺掱偵崌傢偣傞搒崌忋嫋梕検傪墇偊偰塣揮偟偨偨傔扙拏慺嬠偑棳弌偟偨摍偑峫偊傜傟傞偺偱丄扙拏岺掱偺傒傪暿搑偵彫宆帋尡憰抲偱摉強偱暘棧偵惉岟偟偨岲椻扙拏嬠傪梡偄偰幚尡傪峴偭偨丅扙拏攟梴塼傪晍忬妶惈扽傪摍検廩?偟偨撪宎3噋丄挿偝60噋偺僈儔僗惢僇儔儉3杮偵掕検億儞僾偱憲傝崬傒妶惈扽憛撪偵晬拝斏怋偝偣丄傎傏朞榓偵払偟偨屻幚尡偵嫙偟偨丅幚尡偼扙拏嬠偺掅壏偵偍偗傞扙拏惈擻傪挷傋傞偙偲傪栚揑偲偟丄偦偺偨傔偵忋婰僇儔儉傪峆壏幒撪偵慻棫偰丄幒壏傪忢壏(15乣18亷)丄10亷偍傛傃5亷偵挷惍偟奺壏搙偺掕忢忬懺偵偍偗傞徤巁懺拏慺彍嫀棪傪媮傔偨丅帋悈偼壓悈擇師張棟悈偵徤巁懺拏慺尮偲偟偰徤巁僇儕傪庬乆偺擹搙偵側傞傛偆偵揧壛偟挷惍偟偨丅幚尡偺寢壥埲壓偺偙偲偑暘偐偭偨丅
丂
| 崁栚乢帋悈 | 昿搙 | 尨悈 | 張棟悈 | 暘愅曽朄 |
| pH | D | 6.9 | 7.5 | JIS-K0102 |
| OIL ppm | D | 100 | Trace | JIS-K0102 |
| COD(T) ppm | D | 449 | 1.38 | JIS-K0102 |
| COD(D) ppm | D | 430 | 1.38 | JIS-K0102 |
| 儼P ppm | D | 6.50 | 0.63 | JIS-K0102 |
| ORG-P ppm | D | 1.76 | 0 | JIS-K0102 |
| PO4-P ppm | D | 4.74 | 0.4 | JIS-K0102 |
| ORG-N ppm | D | 42.5 | 丂 | JIS-K0102 |
| ORG-N(D) ppm | D | 33.3 | 0.8 | JIS-K0102 |
| NH3-N ppm | D | 33.5 | 丂 | JIS-K0102 |
| NH3-N(D) ppm | D | 30.2 | 1.5 | JIS-K0102 |
| NO2-N ppm | D | 0 | 0 | JIS-K0102 |
| NO2-N(D) ppm | D | 0 | 0 | JIS-K0102 |
| NO3-N ppm | D | Trace | Trace | JIS-K0102 |
| NO3-N(D) ppm | D | 0.02 | 0.80 | JIS-K0102 |
| TURB ppm | D | 133 | 0 | JIS-K0102 |
| BOD ppm | O | 970 | 3.2 | JIS-K0102 |
| TOC(T) ppm | O | 403 | 6.0 | JIS-K0102 |
| TOC(D) ppm | O | 361 | 5.8 | JIS-K0102 |
| BACTERIA ct/ml | O | 49x105 | 15x102 | 忋悈帋尡朄 |
| COLIFORM G. ct/ml | O | 30x103 | 13x10 | 忋悈帋尡朄 |
| 崁栚乢帋悈 | 尨悈 | 張棟悈 | 暘愅曽朄 |
| F mg/l | 0.19 | 0.18 | JIS-K0102 |
| Cd mg/l | 0.001埲壓 | 0.001埲壓 | JIS-K0102 |
| Zn mg/l | 0.35 | 0.23 | JIS-K0102 |
| Cu mg/l | 0.017 | 0.004 | JIS-K0102 |
| Fe mg/l | 2.1 | 0.04 | JIS-K0102 |
| Mn mg/l | 0.21 | 0.01埲壓 | JIS-K0102 |
| T-Cr mg/l | 0.01埲壓 | 0.01埲壓 | JIS-K0102 |
| T-Hg mg/l | 0.0005埲壓 | 0.0005埲壓 | 娐嫬挕崘帵 戞64崋晬昞2 |
| S-SiO2 mg/l | 34 | 18 | JIS-K0101 |
| Ca mg/l | 24 | 7.4 | JIS-K0101 |
| Mg mg/l | 19 | 5.7 | JIS-K0101 |
| ABS mg/l | 1.1 | 0.03 | 忋悈帋尡朄 |
丂
丂(1)嫙帋嬠姅偼5亷偱傕扙嬠妶惈傪帵偡偙偲偑擣傔傜傟丄張棟憰抲撪偱嬠懱傪擹弅偡傞曽朄傪専摙偟偨傝丄懾棷帪娫傪挷惍偡傞偙偲偵傛傝姦抧岦掅壏扙拏張棟偺幚梡壔偑廩暘婜懸弌棃傞丅(2)壓悈擇師張棟悈偼丄C/N抣偑掅偔扙拏斀墳偵昁梫側扽慺尮偑晄懌偟偰偄傞偺偱奜晹偐傜偺揧壛偑昁梫偱偁傞乮幚尡偵偼僋僄儞巁傪扽慺尮偲偟偰巊梡乯丅偟偐偟側偑傜BOD偺崅偄攔悈傪懳徾偵偡傞応崌偼丄BOD惉暘偑扽慺尮偲偟偰巊梡弌棃傞丅乮3乯掅壏扙拏張棟偼嶨嬠墭愼偺塭嬁偑彮側偔丄嬠懱傕挿婜埨掕壔偟摼傞棙揰偑偁傞丅偡側傢偪丄扙拏張棟偼寵婥惈張棟偱偁傝丄偟偐傕杮幚尡偺応崌偼廬棃偵斾偟挊偟偔掅壏偱憖嶌偝傟傞偺偱嶨嬠偺崿擖丄斏怋偑惂尷偝傟埨掕偟偨旝惗暔憡偵傛傞張棟偑壜擻偱偁傞丅杮幚尡偱偼柵嬠慜偺壓悈擇師張棟傪帋悈偵梡偄偨偑丄3働寧偵傢偨傞幚尡婜娫拞僇儔儉撪偵嶨嬠偺斏怋偼尒傜傟側偐偭偨丅埲忋偺寢壥偐傜崱夞怴偨偵暘棧偝傟偨岲椻扙拏嬠偼壓悈丄攔悈偺旝惗暔扙拏張棟偵揔梡偟摼傞惈擻傪桳偟崱屻嬠懱偺擹弅丄曐帩摍偵娭偡傞惗暔岺妛揑尋媶傪敪揥偝偣傞偙偲偵傛傝姦椻抧偵揔偟偨掅壏扙拏張棟偺幚梡壔偑恾傜傟傞傕偺偲巚傢傟傞丅
丂側偍丄揤慠僛僆儔僀僩媧拝傪暪梡偟偨徤壔岺掱偱偼丄傎傏梊憐捠傝偺惉壥偑摼傜傟偨丅偡側傢偪丄僛僆儔僀僩偺僀僆儞岎姺嶌梡偵傛傝傾儞儌僯傾懺拏慺偺懠偵僇儖僔儏僂儉僀僆儞丄儅僌僱僔儏僂儉僀僆儞摍偺峝搙傗廳嬥懏偺堦晹偑彍嫀偝傟偰偍傝丄傑偨巊梡嵪僛僆儔僀僩偺嵞惗偵旝惗暔徤壔朄偑棙梡偟摼傞偙偲偑暘偐偭偨丅崱屻丄媄弍揑夵慞傪寁傞偙偲偵傛傝丄幚梡惈偺崅偄張棟朄偵敪揥偡傞傕偺偲婜懸偝傟傞丅嵟廔岺掱偺媧拝傠夁張棟偱偼丄婛弎偟偨傛偆偵戞1搩偵傠夁嵒偲傾儞僗儔僒僀僩偺暋憌傠憛丄戞2搩偵棻忬妶惈傾儖儈僫廩?憛丄偦偟偰戞3搩偵棻忬妶惈扽憛傪偦傟偧傟捈楍偵楢寢偟偰梡偄偨偑丄戞1搩偵梡偄傜傟偰偄傞愙怗嬅廤朄偼懡擭摉強偱尋媶偑懕偗傜傟偰偒偨傕偺偱丄彮検偺嬅廤嵻偺揧壛偵傛傝傠憌撪偵埨掕偟偨僼儘僢僋傪宍惉偝偣偙傟偵傛傞墭戺暔彍嫀岠壥傪棙梡偟偰傠夁惈擻偺岦忋傪恾傞傕偺偱偁傞丅
丂楢懕帋尡偱偼庡偵扙儕儞丄彍戺岠壥偑専摙偝傟偨偑丄僆儖僩儕儞巁懺儕儞彍嫀棪76亾丄彍戺棪95亾偲丄偦傟偧傟強掕偺栚昗傪忋夢傞岲寢壥傪摼偨丅杮幚尡偵巊梡偟偨帋悈偼偐側傝墭戺搙偺崅偄晹椶偵懏偡傞偑嵟廔張棟悈偼柍怓摟柧偱丄摉弶偺栚昗偱偁傞BOD10噐/l埲壓丄徤巁懺拏慺2噐/l埲壓偍傛傄僆儖僩儕儞巁懺儕儞0.2噐/l 埲壓偺婎弨抣傪僆儖僩儕儞巁懺儕儞傪彍偄偰偦傟偧傟壓夢偭偰偍傝丄傑偨懠偺忋悈帋尡崁栚偲側偭偰偄傞惉暘傕崅搙偵彍嫀偝傟偰偄傞丅楢懕帋尟偵偼嶦嬠岺掱傪娷傑側偐偭偨偑丄堦斒嵶嬠丄戝挵嬠偼嫟偵奺扨埵張棟岺掱偱戝晹暘彍嫀偝傟偰偄傞偺偱彫検偺嶦嬠嵻偺揧壛偵傛傝柍嬠偐偮忋幙側梡悈偲側傝摼傞偙偲偑擣傔傜傟偨丅
丂傑偨丄偙偺僾儘僙僗偼尨悈偺惈忬傗梡悈偺巊梡栚揑偵墳偠偰扨埵張棟偺慖戰丄慻崌傢偣偑帺桼偵弌棃傞墳梡惈偺峀偄傕偺偱偁傞偙偲偑帵偝傟偨丅
丂杮尋媶偼丄姦椻抧岦偗偺攔悈崅搙張棟僾儘僙僗偺奐敪傪庡娽偲偟偰恑傔傜傟偨偑丄楢懕張棟帋尡偺寢壥丄奐敪偝傟偨僾儘僙僗偑栚昗傪忋夞傞忋幙側梡悈傪惗嶻偡傞惈擻傪帩偪丄偐偮栰奜愝抲壜擻側憰抲峔惉偱偁傞偙偲偑徹柧偝傟偨丅恾V亅2偵幚梡婯柾偺崅搙張棟僾儔儞僩梊憐恾傪帵偟偨丅
丂摿挿
丂偙偺尋媶偼丄姦椻抧宆攔悈張棟偲偟偰丄崅搙張棟媄弍偺奐敪傪栚揑偲偟偰峴傢傟偨傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄墭愼偝傟偨攔悈傪忋幙側嶻嬈梡悈偲偟偰棙梡偱偒傞偲偙傠傑偱峫偊偰偄傞丅
丂偦偺偨傔丄尋媶奐敪偺嬶懱揑栚昗偼丄(1)張棟悈偺悈幙偲偟偰丄BOD10噐/l丄傾儉儌僯傾懺拏慺2噐/l丄偍傛傃僆儖僩儕儞巁懺儕僜0.2噐/l埲壓偲偡傞丅(2)張棟曽幃偼旝惗暔張棟傪庡懱偲偟丄偐偮悈張棟憰抲偼壆奜偵愝抲偟摼傞傕偺偲偡傞丄側偳偲偟偨丅
丂傑偢丄扨埵憰抲偺奐敪偲偟偰偼丄(1)慳悈惈攠懱偵傛傞桘暘暘棧憰抲丄(2)懡抜敇婥幃妶惈墭揇張棟丄(3)媧拝嵻傪巊梡偡傞旝惗暔張棟丄(4)扙儕儞傠夁憰抲丄偦偺懠偵偮偄偰暆峀偔峴側偭偨丅
丂偟偐傞屻丄偙傟傜偺惉壥傪傆傑偊偰丄堦楢偺僾儘僙僗偲偟偰楢寢偟丄嶥憖巗偺朙暯壓悈張棟応偺攔悈偵丄僐儞僗僞乕僠丄桘暘側偳傪壛偊偨傕偺偵傛偭偰楢懕幚尡傪峴側偭偨丅
丂偦偺寢壥偼丄忋婰尋媶栚昗傪枮懌偟丄偐偮敿抧壓曽幃偺姦椻抧宆悈張棟憰抲偑壜擻偱偁傞偙偲傪幚徹偟偨丅
丂姦椻抧偵懚嵼偡傞丄悈嶻壛岺嬈丄擾嶻壛岺嬈丄偍傛傃壓悈張棟娭學摍丅